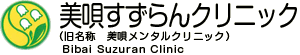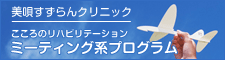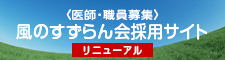- ホーム(法人トップ) >
- 美唄すずらんクリニック >
- コラム >
- 2016年9月
コラム
2016年9月★スペシャルコラム「刑事カイカン 夕焼けの丘 (下)」
*このコラムはフィクションです。
■第四章① 〜前島浩之〜
午後5時半を回った。横浜方面に走る車中、カーステレオにはずっとあの曲が流れている。通り過ぎていく景色…道も空も風も海もまるで歌詞そのままに、全てはオレンジ色に染まっていた。
「大丈夫?車酔いしてない?」
「うん、大丈夫」
しらべは夕焼けに包まれながら、CDケースを胸に抱いてまっすぐに進行方向を見つめている。そして時々小さく曲に合わせて歌を口ずさんでいた。
「ちょっと道が込んでるけど、日が暮れるまでには着くと思う」
「うん。…こんなに綺麗な夕焼け見たの初めて」
そういうものかな。確かに空は大きなスクリーンのように染み一つなく、遠くに見える海も星屑を浮かべたようにキラキラ輝いているけど…俺には特段綺麗には思えない。ずっと病室にいた彼女にとっては、こんな世界でも美しく見えるのだろうか。俺はハンドルを握る手を少しだけ緩めた。
「よかった、勇気出して飛び出してみて。世界はこんなに広いんだね」
「そうだな…」
俺はそんなふうに感じたことはない。この世界は狭くて退屈で…どこにも居場所なんかないと思っていたから。
…会えてよかった、君に。心の中でそう呟く。ただの暇潰しのつもりだったけど、俺は今とても幸福な時間を与えられている。
「本当にありがとう、前島くん」
少し沈黙を挟んでからそう言った彼女に俺は「こっちこそ」と返す。
「しらべちゃん、今日だけって言わずにこれからも仲良くしようぜ。今度お見舞いも行くからさ」
「ありがとう…でも、ごめんね」
急に声が小さくなった。助手席を見ると、彼女は涙を流して俯いていた。CDケースごと胸を強く押さえている。
「おい、どうしたんだよ!」
「違うからね。う、嬉しくて泣いてるんだからね」
息が詰まっていくように声はどんどん弱くなる。俺は急いで車を路肩に停めた。
「おい、しっかりしろって!」
「今までありがとう、前島くん」
「しらべちゃん!」
「でももう…」
ダメみたい、と囁いた瞬間…CDケースが落ちた。
■第四章② 〜ムーン〜
1
ショッピングモールの横、日没の屋外駐車場で謎解きが始まる。
「いいかいムーン?つまりこういうことだよ。確かに凪野しらべさんは前島さんの所にいたんだけど…」
いつもどおり右手の人差し指を立てる警部。語られた推理はこうだ…実はあのアパートにはもう一部屋あり、彼女はそこに隠れていた。私が見せてもらった左壁の収納、実はあれは収納ではなく隣室に繋がるドア。ぴったり合う棚をはめ込んで収納に見せかけていたのだと。
「でも私は抜き打ちで訪問したんですよ?そんなすぐにぴったりはまる棚を用意できますか?」
「もちろん偶然そんな棚があったわけじゃない。普段からそうやって利用していたんだ…テレビがあることを隠すためにね」
「どうしてテレビを隠すんです?」
「フフフ…持っていたら支払わなくちゃいけないからね」
警部が少し笑う。そうか…つまり有料放送の受信料を払わないための策というわけだ。確かに集合住宅では共同の有料放送アンテナを設置されてしまうと、テレビを所持する住人全員に支払いを求められる場合がある。あのアパートの屋上にはそのアンテナがあったし、そういえば廊下で受信料を聴衆している女性を見かけた。
「おそらく前島さんはテレビは持っていないと主張して、支払いから逃げていたんだろうね。そして信用しない聴衆員には実際に室内を見せていた。だからその棚はもともと用意されて痛んだよ」
確かに収納のトリックを使えば一見テレビがない部屋に見える。
「もちろん他の住人の部屋と比較されたら間取りが違うのはすぐバレちゃうけどね。でも普通は玄関先で支払うから、徴収員に部屋の間取りを見せる可能性は低い。まあ仕送りで暮らす浪人生の生活の知恵ってところかな」
「そういうことでしたか…」
一応筋は通っている。アパートの隣には家具屋もあったから手ごろな棚を入手することもできただろう。しかし…いかんせん推測の域を出ていない気がする。不動産屋に確認したわけでもないのに、警部はどうしてもう一部屋存在すると言い切れるのか。私はその疑問をぶつけてみた。
「…トンボだよ」
先ほどトンボがとまったハットを左手で触りながら最後の解説が始まる。
「君が前島さんの部屋を訪ねた時、ソファに置かれた毛布の間からトンボが二匹飛び出した。部屋には出窓があったけど開くのは5センチほど。そこからトンボが二匹も入ってきて、しかも揃って毛布の間に入り込むなんて有り得ないよ」
「ではどうして…」
「簡単なことさ。毛布を干した時にトンボが貼り付いて、そのまま取り込んでしまったんだ。つまり毛布を干せるだけの大きな窓、あるいはベランダがあるってこと。つまり…」
「もう一部屋あるはず…ってことですね」
私がそう言うと警部は「そのとおり」と立てていた指をパチンと鳴らした。まさかあのトンボがヒントになるなんて…この人の想像力は計り知れない。納得するしかない結論だった。
おそらく前島は寝床がない不自然さを誤魔化すために慌ててソファに毛布を置いたのだろう。しかしそのことが逆にトリックを露呈させてしまった。
待てよ、ということは…彼女は今もあのアパートに?
「行きましょう!」
私はまた警部を助手席に押し込むと、急いで車を発進させた。
2
アパート前に到着する。午後7時、日は完全に暮れ辺りは夜に包まれていた。私は遺産で車を出たが、警部はやはり動こうとしない。
「行きましょう、警部」
「ムーン…、私たちにそこまでする権限はないよ」
「でも、前島さんは彼女が部屋にいることを警察に隠したんですよ?」
「…それが犯罪とは限らないさ。凪野しらべさん自身が望んだことかもしれない」
だとしても彼女には心臓の病がある。命の危険がある。それにずっと病院暮らしで世間知らず…軽薄な男に騙されているのかもしれない。取り返しのつかないことになるかもしれない。そう、今まさにこの瞬間にも…。
私はくり返し訴えるが警部は黙ったままだ。
「じゃあどうして警部は母親や主治医に会いに行ったんですか?彼女を心配されてるんじゃないですか?だったら早く保護を…」
「私が情報を集めたのは、いざという時のためさ。彼女からSOSがあった時、警察がすぐに動けるようにね」
「Sosできない状況かもしれないじゃないですか!もういいです、私は…行きます」
駈け出す私の足。警部は何も投げかけてこなかった。
*
インターホンに応答がなかったのでまた最上階の大家を訪ねる。そして事情を説明した上で合鍵を預かり再び305号室前に戻った。
「前島さん、失礼しますよ、警察です」
鍵を開けて中に入ると室内は暗い。電気を点けて先ほどの部屋に進むが誰もいない。私は迷わず左壁のドアを開ける…警部の推理どおり、そこはもう一つの部屋だった。
「凪野さん、凪野しらべさん、いらっしゃいますか?」
呼びかけながら電気を点ける。室内にはテレビ、ラジカセ、ベッド、そして収納としてドアにはめ込まれていた棚もあった。奥には小さなベランダも見える。しかし…人間の姿はない。
私は八畳ほどの室内を探索する。そして絨毯の床に長い黒髪が落ちているのを発見した。間違いない…凪野しらべはここにいたのだ。
では今は一体どこに?まさか前島に連れられて…?
*
急いで外に戻ると、警部が車の前に立っていた。明かりの少ない郊外…ハットと前髪でその表情はわからない。
「あの、警部…」
報告しようとした私より先に、その低い声が言った。
「今…病院の先生から連絡が合ったよ」
「え?」
「前島さんが病院に駆け込んだらしいよ」
そして警部は続けた…「もう冷たくなった彼女を抱えてね」と。
■第五章① 〜前島浩之〜
病院からパトカーで連行され、俺は警視庁の取調室に座らせられた。そして厳しい事情聴取…今日一日のことを細かく尋問された。それがようやく終わったのが午後10時過ぎ。かといって解放されたわけではなく、未だ取調室で待機を指示されている。
色々訊かれたが正直何を話したかもよく憶えていない。彼女が死んでしまった…そのことだけがずっと頭の中を占有していた。呆然というのか困惑というのか…まるで空回りしているCDみたいに、悔しいくらい何も気持ちが流れない。涙の一滴も出て木やしない。俺はただ一人脱力して椅子にもたれていた。
「しらべちゃん…」
ポツリと呟いてみる。左頬が今頃になって痛み出す。
彼女が横たわる病室に飛び込んできた母親…泣き叫びながら何度もその体を揺さぶった。そして怒りと憎しみに満ちた瞳で俺に詰め寄り、言葉を探す時間も与えず平手打ち。さらに立ち尽くすしかない俺に「この人殺し!」「ろくでなし!」と何度も罵声を浴びせた。医師と看護師によって俺はその部屋から引きずり出され、おそらく病院が通報したのだろう、制服警官が到着した。
「人殺し、人殺し…」
声に出して言ってみる。そう、紛れもなく俺は人殺しだ。役立たずのくせに人助けなんかしようとするからこんなことになるんだ。
「人殺し、人殺し、人殺し…」
壊れたレコードのようにくり返した時、トントンと正面のドアがノックされた。
*
返事をする気も起きず無言でいると、数秒待ってから「失礼します」と低い声が入ってくる。さっき事情聴取した刑事ではない。視線を上げると、ボロボロのコートにハットの男が立っていた。
「どうも、警視庁のカイカンといいます」
その異様な名前も風貌も本来なら疑問を投げかけたいところだが…今そんな気力はない。そんなことどうでもいい。
続いて彼の後ろからもう一人、「失礼します」と入ってくる。今度は知っている顔…昼間に俺の部屋に来た女刑事だ、確かムーンとかいう。彼女はカイカンの横に立つと、厳しい眼差しで俺を見た。無理もないか…あの時騙したわけだから。
ここにも俺を憎む人間が一人…本当に最低だな、俺は。役立たずどころかいない方がいいろくでなしにまで成り下がっちまった。
「前島浩之さんですね。日中は部下がお世話になりました。事情聴取に立ち会えなくてすいません。先に病院の方へ行っていたので」
そう話しながら俺の正面に腰を下ろすカイカン。その隣にも椅子はあったが、女刑事は立ったままだった。
「前島さん…お気持ちはお察しします」
狭い室内によく通る声が響く。黙ったままの俺に、カイカンはさらに「悔やんでおられますか?」と尋ねた。俺は小さく「そうですね」と返す。
「凪野しらべさんがずっと一つの曲を探しておられたのはご存知ですね。いくつもレコードショップを回って、それでも見つからなくて…。でもあなたに巡り会えた。その曲のことを知っているあなたに。まるで奇跡です」
「奇跡なんかじゃ…ありませんよ。たまたま俺が口ずさんでいたのを彼女が聴いただけです」
「ナルホド、そういうことでしたか」
「偶然…本当に不運な偶然です」
「ご自分を責めておられますね」
刑事は長い前髪に隠れていない左眼で俺をじっと見る。そしてコートのポケットからあの『夕焼けの丘』のCDケースを取り出した。
「あなたの車の中に落ちていました。これがしらべさんがずっと探していた曲ですね。私も聴かせて頂きましたが…素直に良い曲だと感じましたよ」
そんな話どうでもいい。慰めようとしてくれてるんなら余計なお世話だ。軽蔑して怒鳴りつけてくれた方がまだいいくらいだ。
俺の苛立ちにはお構いなしに、カイカンはケースを開き中から一枚の紙を取り出す。
「これ、しらべさんからの手紙です」
…え?
「おそらくあなたのアパートで、奥の部屋に隠れていた時に書いて入れておいたんでしょうね…もしもの時のために。お母さんに宛てたものですが、あなたのことも書いてあります」
しらべちゃんが…手紙を?カイカンはそこで優しい声になってゆっくりと朗読を始めた。
「お母さん、勝手なことをして本当にごめんなさい。でもどうしても、一日だけでも自由に生きてみたかったんです。あの日ラジオから流れてきたあの曲を、どうしても自分で探したかったんです…」
胸の奥がじんわりと熱くなる。涙も滲んできた。
「それでね、見つかったんだよお母さん。前島くんっていうとっても親切な人に出会えて、CDを聴かせてもらったの。信じられる?ずっと探してたあの曲を聴けたんだよ。
だからねお母さん、もし私に何かあっても絶対に前島くんを怒らないで。全部私がお願いしたことだから。前島くんはそれを聞いてくれただけなの。前島くんのおかげで、とっても嬉しかったんだから」
俺は膝の上で拳を強く握った。視界がぼやけて喉が痛くなる。しらべちゃん…。
「お母さん、親孝行できなくてごめんね。いつも看病ありがとう。お母さんの娘に生まれてよかったです。…凪野しらべ」
「う、う、うう…」
言葉にならない声が漏れる。涙も止まらない。カイカンは手紙をそっとたたむと、穏やかに言った。
「長い入院生活、くり返される発作の中で…しらべさんは自分の最期を感じ取っていたのかもしれませんね。だから危険も承知で病院を飛び出した。でもそのおかげであなたに出会えた。とても…感謝されてると思いますよ」
「感謝されるようなことはしてない!」
思わず声を荒げた。
「俺なんかに、俺なんかに会わなければ…」
声が詰まる。そうだ、こんな最低野郎に会わなければしらべちゃんは…。クソ、クソ、クソ!どうして俺はこうなんだ。どうしてすぐ病院に戻るように言わなかったんだ。
君と過ごすのが楽しくて…嬉しくて…。ごめんよ、しらべちゃん。ごめんよ。君に感謝される資格なんて、俺にはない!
「俺は…俺は…」
「今日のことだけではありません」
カイカンはそう言って俺の嘆きを遮る。
「実はこのcDケースの歌詞カードにステッカーが挟まっていたんです。…ご記憶ですか?」
…ステッカー?
カイカンはケースからそれを取り出して俺に手渡す。これ、確か…。
「これが何です?昔俺が聴いてたラジオの景品です。ハガキが読まれたらもらえる…」
「そうです。ステッカーの裏にも書いてありますね。『ドリームドクターさん、いつもリクエストありがとう』と。このドリームドクターっていうのがあなたのペンネームですか?」
「ええ…」
そういえば昔ラジオに『夕焼けの丘』をリクエストした時、そんな名前にしたっけ。もらったステッカーを歌詞カードに挟んでたなんてすっかり忘れてた。
「お母さんから伺ったんですけどね、しらべさんが初めてラジオで『夕焼けの丘』を聴いた時、曲名や歌手名は聞き逃してしまった。でも、曲の最後のDJの言葉だけは憶えていたそうです…『ドリームドクターさん、リクエストありがとうございました』って」
まさかそんな…。
「そうなんです。彼女の心をずっと支えてくれたこの曲をリクエストしたのも…前島さん、あなただったんですよ。きっと彼女もステッカーを見つけてそのことに気付いたんだと思います」
…「今までありがとう、前島くん」。
彼女の最後の言葉が聞えてくる。そんな…。
「信じてあげてください、しらべさんはあなたに感謝されていますよ。それに…お母さんも」
「どういうことですか?」
「実はこの手紙、先にお母さんに見せたんですが、そうしたらあなたにも見せてくれって言付かったんです。そして…ありがとうございましたと伝えてほしいと」
「う、うう、ううう…」
胸が焼けるように熱い。唇を噛んで抑えようとしたが、俺はたまらず声を上げた。
「わあああ!」
止まっていた感情が暴れだす。悔しいのか、悲しいのか、それともほっとしたのか、嬉しいのか…とにかくそれはどうしようもない爆発だった。俺はみっともなく声を上げて泣く。
「わああああ…」
机に頭を伏せた。すると、ずっと黙っていた女刑事がツカツカと俺に歩み寄る。そしてそっと手にハンカチを握らせてくれた。
「…ご苦労様でした」
そう静かに言うと、彼女は部屋を出ていく。残されたカイカンはもう何も語らず、ただ泣き続ける俺を見ていた。
■第五章② 〜ムーン〜
前島の聴取に立ち会う資格がない気がして、私は取調室を出た。部屋に戻るといつも警部が使っているソファに座ってみる。
「はあ…」
思わず溜め息が出る。
あの前島という生年は…悪人ではなかった。凪野しらべにとっては救世主にも値したのかもしれない。病院の霊安室で初めて対面した彼女はとても安らかな顔をしていた。
でも…。
私はどうすればよかったのだろう。警部の言うように最初から捜索などするべきではなかったのか。それともアパートを訪ねた時にトリックを見破って彼女を病院に連れ帰るべきだったのか。…わからない。わからなくなってしまった。
もちろん満足感ではなく、かといって喪失感とも言い切れない疲労に包まれながら私は部屋の電気を点けるのも忘れて考え続けていた。
*
パチン、と急に部屋が明るくなる。
「どうしたんだい、真っ暗な中で」
そう言って警部が入ってきた。私は「失礼しました」と慌てて立ち上がる。
「警部、前島さんの聴取は終わったんですか?」
「一応ね。まあしらべさんのお母さんの口添えもあるから、彼が罪に問われることはないと思うよ。病院でも彼女の死因は病死だと診断されてるしね。もうじき前島さんのお父さんが迎えに来て、一緒に帰ってもらうことになりそうだ」
「そうですか…」
力なく答えた私に、警部は「今日は一日走り回って大変だったね、お疲れ様」と言った。
「いえ…私が勝手にしたことですから。それより、質問してもよろしいですか?」
「どうぞ」
警部は窓辺に立って夜の東京を見ている。その背中に私は尋ねた。
「警部はどうしてしらべさんを保護しようとなさらなかったんですか?」
別に責めるつもりではない。保護してもしなくても結果は同じだったかもしれない。それでも訊かずにはいられなかった。
…返される沈黙。室内に蛍光灯のジリジリという音と壁の時計のチクチクという音が際立つ。
もしかして警部も…考えあぐねているのだろうか。優秀な頭脳を持ちながらボロボロで異様な格好に身を包んだその姿が、不思議と今はとても人間らしく見えた。この人はこの人なりに…ここに落ち着くしかない理由があったのかもしれない。いや、きっとあったに違いない。
「そうだね…」
数分おいてからようやく口が開かれる。
「確かに…無理をせずに病室にいたら、彼女はもっと生きられたのかもしれない。でもそうすれば今日のような感動は一生なかっただろう」
警部は振り返らずに話す。
「どっちの人生が幸福かなんて…私にはわからない。警察は捜査の専門家だけど、生き方の専門家じゃないからね」
どこか寂しそうな声だった。私はその一言一言を噛みしめる。
確かに…警部の言うとおりかもしれない。安全や健康はわかりやすい指標ではあるけれど、それだけで測れるほど幸福とは単純なものではない。
「そもそもこの世に生き方の専門家なんていない。だから…本人が選ぶしかないんだ。生き方を自分で選ぶこと、それが人間の誇りだからね」
「ですが警部…」
思わず反論する。
「何が幸福かを選ぶのはその人の権利です。でも…やはり命があってこその幸福だと思います。生きてさえいれば、幸福はまた見つけられます」
警部は小さく「うん」と頷く。私は続けた。
「しらべさんだって、もし前島さんに出会えなければ、探していた曲にも出会えずにただ命を落としたかもしれません。それでも彼女は後悔しなかったでしょうか」
「わかってる。彼女のしたことは我儘だしたくさんの人に迷惑をかける行為だ。でも私は…できるだけその我がままを許してあげたいって思ったんだよ」
「…何故です?」
そこで警部はこちらを振り返った。
「私も許されてる人間だからさ。だからきっとしらべさんもみんなに感謝してると思うよ。前島さんにも、お母さんにも、病院の先生にも…そしてもちろん君にもね」
「そんな…」
昼間に私が前島の部屋を調べていた時、隣室で息を潜めながら彼女は何を思っていたのだろう。母親が自分を案じて警察に相談したことを知りながら、それでも姿を見せようとはしなかった…それが彼女の選んだ生き方だったのか。
生き方を選ぶ誇り…。もう一度自分の心に問いかけてみる。確かにそれは尊い。でも…誇りよりも生きることにしがみついてこそ辿り着ける未来もあるのではないか?
警部の考えは理解できる。それを裏打ちする経験もあるのだろう。でも私にはその逆を真とする経験がある。そう、あの時…女としての誇りを捨てなければ私は生きてはいけなかった。
「警部…」
私は両方の拳を硬く握り、そして正直に言った。
「すいません。やはり私は…誇りよりも命を守るべきだと思います。警部よりもまだ経験も能力も少ない私ですが、今はこれが私の答えです」
警部はそっと微笑む。
「うん…わかったよ、ありがとう」
そこで「お疲れ様」ともう一度言うと、警部はそれ以上の言葉を止めた。そして再び窓の方を向く。私も黙って自分のデスクに戻る。
ふと見ると向かいの警部のデスクには、昼食用のハンバーガーがそのまま手付かずで置かれていた。
■エピローグ 〜前島浩之〜
あれから一週間経った。俺は彼女と来ることができなかった場所に来ていた。そう、あの曲のモデルになった丘がある公演に。
辺りは夕焼けに染まり、子供連れの夫婦や恋人たちが通り過ぎていく。
「夕焼けの中飛んでいくトンボを見つめて…」
そっと口ずさんでみる。
あの日、取調室を出してもらう時にカイカンは言った。
「実は謎を解くヒントになったのもトンボでした。あのトンボ、私の地元では『神様トンボ』って呼ばれてましてね、死者が姿を変えて戻ってきたとか、死者の魂を運ぶとか言われてるんです。そして、幸福を運んでくるともね。
…彼女の最後の一日が幸福だったと、私は信じています」
オレンジ色の空に向かってトンボがまっすぐ飛んでいく。しらべちゃん…こんな広い空に一人で…。いや、もう心配はしないよ。きっとそっちで楽しくやれるよな。だって神様は君の味方なんだから。
あの時…上りエスカレーターに乗った君と、下りエスカレーターに乗った俺の人生が交差した。本来ならそのまますれ違うはずだったけど、あの曲が二人を繋いでくれた。そして君は、下りエスカレーターに乗り換えて俺を追いかけてきてくれた。
…次は俺が走る番だ。
「さて」
腕時計を見る。午後5時、そろそろ帰らなきゃ。今夜は予備校で集中講義だ。
「よし、今度こそ絶対医学部合格してやるぞぉ!」
俺は決めたんだ。もう一度頑張る…自分を信じて。
車に乗り込みエンジンをかける。カーラジオからはdjの声。
「それではドリームドクターさんから懐かしのリクエストです。ベイシティボーイズで『夕焼けの丘』をお聴きください…」
THE END.
■あとがき
今回のお話は、一言で言うと「もはやミステリーではない」。謎解き要素は少ないですが、いつも従順なムーン刑事の反乱を書いてみたくて考えた物語です。「本人が持つ生き方を選ぶ権利、そこに他者はどこまで介入してよいのか」というのは僕たちの仕事でもいつも頭を悩ますテーマです。たいそれたメッセージを持つ内容ではありませんが、読んで下さった方が何かを考えるきっかけになれたら嬉しいです。
平成28年9月12日 福場将太