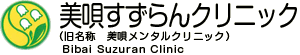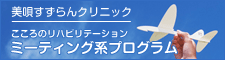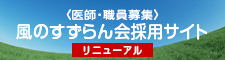- ホーム(法人トップ) >
- 美唄すずらんクリニック >
- コラム >
- 2018年8月
コラム
2018年8月★スペシャルコラム「刑事カイカン 空と毒薬(前編)」
*このコラムはフィクションです。
■プロローグ
見上げることしか叶わない天上の世界。そこは本来人間が立ち入ることを禁じられた場所。無理に踏み入ればイカロスのように罰を受ける。
しかし一人の女が今、毒薬を持ち込もうとしている。人間が造り出した巨大な鉄の鳥に乗って。そしてその手の中の毒薬はただ一つの命を奪うためにある。
■第一章 DEPARTURES
1
「北海道へはご旅行ですか?」
私が青い旅行バッグを受け取りながらそう尋ねると、彼女は控えめな笑顔で「ええ、まあ」と返した。細身の体、その腕はこんな大きなバッグを持っていたら折れてしまうんじゃないかと心配になるくらい華奢だった。
「ちょっと長いお休みをとって、日本を色々回ってるんです」
「それは楽しそうですね。よいしょっと」
頭上の荷物入れに彼女のバッグを押し込む。
「あの…どうもすみません、荷物を上げてもらっちゃって」
「いえいえ、自分のを上げたついでですから。ささ、お席にどうぞ」
大袈裟に頭を下げる彼女に着席を促す。可愛く、そしてどこか儚く笑ってから彼女は窓際の35のA席へ腰を下ろした。一つ空席を挟んで私は通路側の35のC席に座る。
「あの、そちらもご旅行ですか?」
遠慮がちに彼女が尋ねてきた。
「いえ、私はその…仕事ですね」
「ご出張ですか?」
「まあ、そんなところです」
「素敵ですね。かっこよく働く女性ってあたしも憧れてたんですよ」
「いえいえ、そんなたいそうなものじゃありませんよ」
自分で答えながら少し憂鬱になる。せっかく北海道に行くというのにまるで余暇の時間がない明日からの研修スケジュールが頭を過ぎった。
「私はあなたがうらやましいですよ。日本を色々回られたとのことですが、どちらへ行かれたのですか?」
「かなり無計画なんですけどね、九州の九重山とか、広島の宮島とか、京都の銀閣寺とか…これまで行きたかった場所を南から北へ巡ってます」
「南から北…まるで渡り鳥ですね。それで次が北海道というわけですか」
「そうですね。まあ北海道で最後の予定ですけど。今、渡り鳥の最終居留地に向かってるんです」
粋な表現だと思った。そこでまた彼女は笑顔を作る。20代半ば…私と同じくらいだろうか。言葉を続けたものか思案しかけたところで機内アナウンスが流れた。
「皆様、この度はガーネット航空をご利用頂き誠にありがとうございます。当機はビーイング609便、新千歳空港行きです。現在お客様を機内にご案内しております…」
羽田から発つ便。機内は平日の夜ということもあって満席ではない。それでもビジネスマンを中心に8割方は埋まっている。会話している乗客も少なく、乗務員を含め機内にはどこか一日の疲労感のような雰囲気が漂っている。彼女と私はそのまま会話を終了した。淡いクラシック音楽が流れる中、アナウンスと飛行機のエンジン音だけが響いている。私はシートベルトを締めた。
ふと腕時計を見るともう出発時刻の午後8時だが…まだ動き出す様子はない。点検に時間がかかっているのだろうか。
「ほんとにごめんなさいね、つい買い物に夢中になっちゃって」
遠くから場違いに陽気な声が聞こえてきた。見ると派手な服装の若い女性客が乗務員に誘導されてこちらにやって来る。明るく話すその女性の傍らには夫とおぼしき大柄な男の姿もある。
「お客様、大丈夫ですのでご安心ください。間に合われてよかったです」
漏れ聞こえる会話から推測すると、どうやらこの夫婦が搭乗手続きを済ませているにも関わらずゲートに姿を見せないので出発が遅れていたらしい。そういえば時々「お客様のお呼び出しを申し上げます」なんてアナウンスを空港で耳にする。客を連れて疾走している地上係員の姿も目にする。今機内で夫婦を誘導しているあの女性乗務員もきっと内心では「遅れてんじゃねーよ、さっさとしろよ」くらい思ってるかもしれないがそんなことはおくびにも出さない。大変な仕事だなあ、と私は勝手に想像して感心する。
「それにしても席が遠いわね。歩くの疲れちゃうわ」
悪びれもせず妻が言う。機内の穏やかな空気にナイフを入れながら夫婦はどんどんこっちに近付いてくる。そして通り過ぎるかと思ったらなんと私の目の前で立ち止まったではないか。しかも夫は妻の目を盗んで一瞬私を舐めるように見た。
…またか。私の人生にことあるごとにまとわりついてくる不快な視線。込み上げる怒りと悲しみを私は奥歯を噛んで抑え込んだ。
それにしてもおかしい。私の左側の空席はB席一つしかないし、通路を挟んだ右側のC・D・E席も埋まっている。夫婦はどうしてここで立ち止まるのか。
「あれ、変ね。ねえヒロくん、あたしたちの席は35のAとBだよね」
「うん、そのはずだけど」
チケットを確認して夫が答える。そして彼は私の頭越しに窓際席の彼女に不機嫌そうに呼びかけた。
「あのすいません。あなた、席を間違っていませんか?そこは俺たちの席なんですけど」
外を向いていた彼女は振り返って目を丸くする。数秒そのまま固まっていたが、慌てて自分のチケットを確認した。
「ええと、あの、ここ36のA席じゃ…」
「何言ってんのよ、よく見なさいよ。ここは35の列じゃない」
今度は妻。窓際の彼女は急いで立ち上がると「すみません、すみません」と激しく頭を下げた。女性乗務員が両者をなだめるように「お客様、大丈夫ですのでゆっくり移動してください」と仲介する。席の入れ換えの都合上私もシートベルトを外して通路に立った。
「すみません、ごめんなさい」
「いえいえ、大丈夫ですから。あ、荷物も移した方がいいですよね。俺、やりますよ」
女性乗務員の優しさにほだされたのか、それとも邪な気持ちからか、男も急に柔らかい物腰に変わる。返事も待たずに彼は頭上の荷物入れから彼女の青いバッグを取り出すと、「あらよっと」と一つ後ろの荷物入れに入れてやった。大柄で長身のため特に労力もなくひょいといった感じだ。
「本当にすみませんでした、ありがとうございました」
泣きそうな顔で彼女は本来の居場所である36のA席に落ち着いた。男の妻は「荷物なんて自分でやらせればいいじゃない」と小さく、しかし確実に彼女に聞こえるように舌打ちした。綺麗な身なりをしていても人間そのものは安っぽいな…と私は密かに軽蔑する。
「それではお客様、席におつきください。間もなく出発致しますので」
女性乗務員は如才なく言い、足早にその場を離れた。男は手慣れた感じで妻と自分のバッグを頭上の荷物入れに押し込む。
「ほらヒロくん、座ろう。またヒロくんが窓際ね」
「オッケー。でもその前にジャンパーを脱ぐよ。さすがに暑くなってきた」
男は首元までジッパーを上げて厚手のジャンパーを着ていた。彼はそれを脱ぐと、適当に丸めて荷物入れに押し込んだ。仕立ての良いブランドのスーツ姿が現れる。
「だから北海道に着いてから着ればいいって言ったのに」
「まあそうプリプリすんなって、せっかくの旅行じゃないか」
男が窓際のA席、妻が隣のB席に座る。私も心の中で溜め息をつきながら、すっかり環境の変わってしまったC席に腰を下ろした。そして五分としないうちにドアが閉められ、機体がのっそりと動き出す。
「皆様、ご搭乗ありがとうございます。この便の機長は坂井、チーフパーサーは大畔でございます。当機はこれから滑走路に向かって移動致します。お座席のベルトをしっかりお締めください。機内で安全にお過ごし頂くためのご案内を致しますので正面のスクリーンにご注目ください…」
と、アナウンス。続いてスクリーンに注意事項や緊急脱出時の説明映像が流れる。隣の夫婦…特に妻の方はそんなのお構いなしに喋り続けている。夫の方はまだ妻よりは自分たちに向けられている空気を感じ取れているのか、どこかよそよそしく相槌を打っていた。
私はもう一度心の中で溜め息をつく。旅の恥はかき捨てとはよく言ったものだ。まあいいか、もともと楽しむための旅ではないのだから一期一会を期待するべきではない。それによくよく考えればこの三日間まともに寝ていなかった。左側が少々騒がしいが、このフライトは睡眠時間に当てることにしよう。
やがて説明映像が終わり機体も滑走路に進入する。
「皆様、これより離陸致します。もう一度お座席のベルトをご確認ください…」
アナウンスを聞きながら、私はそっと目を閉じた。
2
人が動く気配で私は目を醒ます。どうやらあっという間に眠りに落ちていたらしい。腕時計を見ると四十分ほどが過ぎていた。通路にはドリンクをサービスしている女性乗務員。離陸前の騒動にも立ち会っていた彼女だ。前列の乗客に紙コップで飲み物を振る舞っている。
「ヒロくん、なんか今日ノリが悪くない?あ、もしかしてまた乗り物酔い?」
隣の席の妻が言った。窓際の男は緊張した面持ちで「そうかもしれない」と答えている。
「だったらもう1錠薬飲んだら?ちょうど飲み物も来たしさ」
「そうだな」
少し耳がツンとする。そう、ここはもう地上を遥か彼方に離れた上空なのだ。
「お飲み物はいかがですか?冷たいお茶にお水、アップルジュースにホットコーヒーをご用意しております」
ドリンクサービスがこの列に来た。男はジュース、妻はお茶をリクエストした。私は冷たい水をお願いする。彼女は「かしこまりました」と慣れた手つきでカートに積まれたポットから紙コップに飲み物を注いでいく。
「どうぞ、お召し上がりください」
窓際の席から順に手渡される。
「ねえヒロくんのも飲ませて。あたしのもあげるから」
「まったくお前は…ほらよ」
夫婦はキャッキャと紙コップを交換し合っている。う~ん、昼休憩の中学生カップルなら微笑ましい光景かもしれないが、こんな夜分に機内で大人がこのテンションなのはやっぱり痛い。私と同じ気持ちなのか、女性乗務員も夫婦に冷たい一瞥を送ってからまた次の乗客へとドリンクサービスを続けていった。
受け取った水を一気に飲むと、私は再び目を閉じる。今どの辺りを飛んでいるのか。まあ到着するまでもう一眠りできるだろう。
*
「…ねえヒロくん、大丈夫?ねえ、ちょっと」
また左側が騒がしくなってきた。今度は何だ?睡魔に奪われかけていた意識をなんとか奮い立たせ私は目を開ける。見ると男が喉を押さえながら苦悶の表情で呻いていた。
「う、うう、うう…」
「ちょっとヒロくん、気分悪いの?しっかりして!」
鈍い声を漏らす夫の肩を妻が掴む。どうやらただ事ではない。どうかしましたかと声をかけようとした時、後ろの列でドリンクサービスしていた乗務員の彼女が異変を察して引き返してきた。
「お客様、どうかされましたか」
「あ、CAさん。ヒロくんが苦しんでるの。何とかして」
ヒステリックに言う妻。周囲の乗客からもにわかに注目が集まってくる。私は身を乗り出して「とにかく、呼吸が楽になるように彼のシートベルトを外しましょう」と進言した。その時鼻につく臭い…これは…。
「うう、奈々…」
妻がシートベルトを外した直後、男はその言葉を最後にピクリとも動かなくなった。目を見開き、口を歪めたその顔はまるで悪魔に出会ってそのまま恐怖で凍りついてしまったようだ。妻が体を揺さぶるが全く反応はない。
「ヒロくん、ヒロくん、しっかりして!」
「大丈夫ですか、三枝様!」
乗務員の彼女も声を上げた。まずい、これは一歩間違えるとパニックになりかねない。
私は自分のシートベルトを外して立ち上がる。落ち着け、何が起こったのかはわからないが、今はとにかく最適の動きをしなくては。
「乗務員さん、急病かもしれません。どこか応急処置ができる場所はありませんか?」
「は、はい。医務室が…」
「ではそちらに移しましょう。手伝ってください」
大柄な男を私と乗務員が両側から肩を貸してなんとか立ち上がらせ、そのまま狭い通路を進む。否が応でも視線が集まる。ふと見ると36のA席の彼女もこちらを見て青い顔をしていた。
*
機内にこんな部屋があったのか…と感心している場合ではない。私たちは男を簡易ベッドに寝かせる。彼はぐったりとしたままやはり微動谷しない。手早く生体反応を確認する。肩を貸している時から気付いていたが、呼吸も脈も完全に停止していた。交代で心臓マッサージをするが全く効果はない。機内には「お医者様はおられませんか?」のアナウンスも流されたが名乗りを上げる者はいなかった。いたとしてもおそらく手の施しようがなかっただろう。
「人工呼吸をしますか?」
乗務員の彼女がそう言ったが、私はやんわりとそれを制する。そして腕時計の時刻を記憶すると、医務室の壁際に立ちすくむ妻に慎重な声で伝えた。
「残念ですが、お亡くなりになっています」
言葉が届くまでに十数秒を要した。妻は腰が抜けたように突然その場に崩れると、定まらない視線を虚空に送る。先ほどまでのはしゃいでいた姿とはまるで別人だった。
「お客様…」
彼女に寄り添いながら女性乗務員もしきりに自分の髪を触っていた。明らかに動揺している。プロとはいえ突然の緊急事態に冷静さを欠いているのだろう。
…こんな時、実感してしまう。自分はショックに慣れているのだと。もともと無感動な素質な上に、職業病でさらにそれが強化されてしまった。
「あの、すいません」
ようやく理性が働きだしたのか、乗務員の彼女がこちらを振り向いて問う。
「お客様、あの、失礼ですが、あなたは…」
そういえば名乗っていなかった。私も自分が思うほど冷静ではないらしい。内ポケットから黒い手帳を示すと私は告げた。
「警察の人間です」
そう…私の名前はムーン、警視庁捜査一課の女刑事である。もちろんこんなふざけた名前の日本人がいるはずもなく、ムーンというのは職場上のニックネームのようなものだ。これは一般の方はあまりご存じないのだが、警視庁捜査一課はミットと呼ばれるいくつかのチームに分かれており、私の所属するミットではお互いをニックネームで呼び合うのが古くからの慣例らしい。ちなみに私の上司はカイカンなる私以上に奇異なニックネームで呼ばれている。
普段はそのカイカン警部の指示のもと捜査に当たる私だが、今この場ではそうはいかない。先ほどは周囲に動揺を与えぬよう急病と言ったが、実は病死の可能性は極めて低い。というのも、男の口からアーモンド臭がしていることに気付いたからだ。唇や肌の色、苦悶した様子などから見てもおそらく間違いない。これは、青酸系化合物による中毒死だ。
となると可能性として考えられるのは二つ…自殺、あるいは他殺。もちろん詳しい検死や鑑識作業は空港に到着してからだが、今のうちにできるだけの初動捜査はしておかねば。
■第二章 SUSPECTS
1
天空で落命した男の名は安土弘樹(あづち・ひろき)、40歳。安土グループの若き支社長。そして妻の名は奈々(なな)、26歳。放心状態の妻からなんとかそれだけの情報を聞き出したが、これ以上の聴取はもう少し落ち着いてからでないと難しいだろう。
妻には夫の遺体が横たわる医務室とは別の静養室で休んでいてもらい、乗務員の彼女にそばにいてもらうことにした。彼女の名は岡本仁美(おかもと・ひとみ)、29歳であることも確認した。
それにしても安土グループとは…。詳しくは知らないが確か土地開発とか学校経営とか、とにかくかなり手広くやっている巨大複合企業だ。その総帥は政界にまで影響力を持つとさえ言われる。やれやれ、これはマスコミ発表が必要になるかもしれない。
私は機長の坂井とチーフパーサーの大黒に経過を説明し、他殺の可能性も否定できないので今できる捜査をしておきたい旨を伝えた。二人は一瞬難色を見せたが、「他のお客様に動揺を与えないよう配慮してくださるのなら」と許可してくれた。
とりあえず現場保存ということで夫婦の座っていた席はそのままにしてもらう。そして客室乗務員には乗客たちの動きにさり気なく気を配ってもらうこととした。
「あともう一つ、警察に連絡をお願いしたいのですが」
「はい、航空無線でお伝えしましょう。新千歳の空港警察でよろしいですか?」
「ご協力感謝します、坂井機長」
そこまで言ってちょっとだけ考える。そして…警視庁のカイカン頸部にも連絡してもらうよう私はお願いした。機長は「珍しいお名前ですね」と快く了解してくれた。
雲の上でまでミットの恥をさらすことになろうとは…。私は「そうなんですよ」と苦笑いし、自分に関してはこの場では本名を名乗ることにした。さすがにムーンでは珍しいお名前ですねでは通らないだろうから。
さて、ここからどうするか。警部ならまず『取っ掛かり』を探すだろう。この事件における取っ掛かり…実はそれらしきものをすでに私は見つけている。
そう、安土弘樹が急変した時、乗務員の岡本仁美は確かに「三枝様」と呼びかけた。安土と三枝…似ても似つかぬ名前だ。私が聞き間違えたとも思えない。まずはそこから当たってみるか。
2
乗務員の控室を借りて仁美の聴取を開始する。先ほどまでの動揺から立ち直り、体面に座っている彼女は凛とした客室乗務員のオーラを放っている。表情は穏やかだが眼差しは厳しい。
「すいません、殺人事件の可能性もありますのでどうか聴取にご協力を」
「もちろんです。何なりとお尋ねください」
滑舌の良い語り口で彼女は答える。そこでまず私は安土夫妻が遅れて搭乗した時のことを確認する。
「はい。ご夫妻は登場手続きも済ませ保安チェックも済まされていましたが、奥様が売店でお買い物に夢中になられ搭乗ゲートにお越しになるのが遅れてしまったそうです。そこで地上係員が促し急いで頂きました。機内に入られてからは席まで私が誘導しました」
「それで着席の際に席を間違えたお客さんとちょっとトラブルになったんでしたね」
「はい。まああのようなことは珍しくありませんのでトラブルというほどではございませんが」
「実はその後、私はすぐに眠ってしまったんです。岡本さんがドリンクサービスにいらっしゃった際に目が覚めたのですが…、その間の安土ご夫妻の様子を教えて頂けませんか?」
仁美はそこで少しだけ考えてから答える。
「そうですね…楽しそうにずっとお話をされていましたよ。特に奥様がたくさん話されていて、ご主人は頷いていらっしゃる感じでした。機内の他のお客様は皆様お静かに過ごされていましたから、少し目立ってはおられましたね」
「席を立たれたりは?」
「ございませんね。離陸してから化粧室を利用されたお客様は誰もいらっしゃらなかったように記憶しております」
明瞭な返答だった。まあ事態が発生したのが離陸から四十分そこそこなので立って歩き回る乗客もいなくて当然か。その他にも夫婦や他の乗客について気になったことがなかったか尋ねてみたが、特に目ぼしい情報は出てこなかった。
「それではもう一つだけお伺いしたいのですが…」
と、私は本題に切り込む。
「ご主人が急変された時、あなたは『三枝様』と口にされました。彼の名前は安土ですが…」
そこで言葉を止めて反応を見てみる。それまで毅然としていた彼女の目が明らかに落ち着きをなくしていた。訪れる沈黙…飛行機のエンジン音だけがその場を占有する。
「実は…。あの、お客様の個人情報を話してはいけないのですが…」
「情報は捜査以外の目的で使用しないとお約束します」
「わかりました。実はあの方、前は三枝というお名前だったんです。以前にも何度か我が社の飛行機をご利用頂いたことがございまして…その時の記憶があったんです」
「…なるほど。となれば最近名字が変わったということでしょうか」
「だと思います」
もしかしたら彼は婿養子で結婚したのかもしれない。これで三枝の謎は解けたが、そうなると別の疑問が湧いてくる。
「しかし、よく名前を憶えていましたね。私なら出会った乗客の名前を全員記憶するなんて無理ですよ…何か印象に残る相手でなければ」
少し意地悪な言い回しになってしまった。彼女は再び目を泳がせ、視線を外してから答えた。
「それが、あの、以前に機内でお会いした時に自己紹介されまして。あの、その…今度食事でも行きましょうと。それで印象に残っていたんです」
「それはいつ頃のことですか?」
「確か…去年の今頃です」
一年前か。それにしても機内で客室乗務員をナンパとは。まあそれなら悪名として彼女に記憶されても無理はない。私は一応「実際にお食事に行かれたのですか?」と確認する。彼女はブンブン首を振って「とんでもないです」とそれを否定した。
*
続いて亡くなった男の妻である安土奈々に入室してもらう。「少しは落ち着かれましたか」と尋ねると、彼女は無言のまま泣き腫らした目で頷いた。
「ご主人の死について私は捜査をせねばなりません。おつらいでしょうがご協力をお願いします。まずは今回のご旅行のことから教えてください」
「うん…」
彼女はこちらの質問に対してぽつりぽつりと必要最小限の単語で答えてくれた。それによると、夫婦は東京に暮らしており今回は二泊三日の北海道旅行だったという。日中は夫の仕事があったので退勤後の夕刻にマイカーで羽田空港に二人で向かい、そのまま搭乗した。
「仕事の後の出発ですか。お休みをもらって朝から出るというわけにはいかなかったのですか?」
「ヒロくんは今とっても忙しいの。支社長になって…だから簡単に休めないの。新婚旅行だってまだなんだから」
「失礼ですが、ご結婚はいつ頃で?」
「…半年前」
そこでまた彼女の目に涙が滲む。警部に習って私は相手をいたわりながら情報を引き出していく。実際にやってみると難しい…というより心苦しい。いかんいかん、これは仕事だ。
奈々は安土グループ総帥の末娘。二人は一年ほど前にとあるパーティで知り合った。間もなく交際が始まり半年でゴールイン。先ほど岡本仁美の聴取で推測したように彼は婿養子となり、晴れて安土一族の仲間入り、その後間もなく支社長の座に就任した。まあ俗な言い方をすれば、総帥令嬢のハートを射止めて地位を手に入れた逆玉というわけだ。
もちろん地位は副産物で愛情が結婚の理由なのかもしれないが、二人が出会った一年前といえば彼が岡本仁美をナンパしていた時期。その点を考えても、そして私に向けてきたあのいやらしい視線を考えても、どうしても彼の愛情を疑ってしまう。
「実は、ご主人の死には毒物が関与している可能性がありまして」
私は少し角度を変えて質問を続けた。彼女はそこで明らかな驚きを見せる。
「え、毒?ヒロくんは毒で死んだの?病気じゃなくて?」
「あくまで可能性ですが、身体にはそれを疑わせる所見がありました」
「どういうこと?誰かに毒を盛られたの?」
そこまで言うと彼女ははっとし、急にこちらを睨みつける。
「まさか刑事さん、あたしを疑ってるの?あたしがヒロくんに毒を飲ませたって?ふざけないでよ!」
「違います。今は全てが可能性の段階なのです。誰に毒を飲まされたのかわかりません。それにご自身で飲まれた可能性だってあります」
「ヒロくんが自殺するわけないじゃない!」
「すいません、まず落ち着いてください。まだ何もわからないのです」
立ち上がって退室しようとする彼女をなんとかなだめて座らせる。相手を感情的にさせてしまうとは…私もまだまだだな。
「奥さん、怒らせてしまってすいません。ご主人に何が起こったのかを確かめるためにどうかご協力を」
「わかったわよ。それで何を答えればいいの?」
「はい。機内に入ってからご主人が口にされた物は何かありますか?」
彼女は少し考えてから答えた。彼にはガムや飴を口にする習慣はなくタバコも吸わない。機内では乗務員が振る舞ったアップルジュースと一緒に酔い止め薬を1錠飲んだだけだという。
「酔い止め薬ですか。それはどのような物ですか?」
「ヒロくんは乗り物に弱いのよ。だからいつもポケットに錠剤を入れて持ち歩いてるの。いつでもすぐ飲めるように。飛行機に乗る前にも1錠飲んだんだけど、なんかまだ気分悪そうだったからあたしがもう1錠飲むように言ったのよ。
まさか、あれに毒が入ってたの?だっていつも飲んでるやつだよ」
「薬はどこのポケットに入っていたのですか?」
奈々によると彼はいつも数種類の酔い止め薬をスーツの左ポケットに入れていたという。しかも機内で着ていたスーツは仕事から帰宅した後に着替えたおろしたての物であり、薬も彼が自分で準備していた。となると事前に誰かが酔い止め薬に毒を仕込むというのは難しそうだ。
酔い止め薬は関係ないのか?では飛行機に乗るよりも前、例えば日中仕事をしている時に毒を飲まされたとしたらどうだろう。カプセルに毒を仕込めば飲んでから実際に効き目が出るまでにタイムラグを作れる。
「これもあくまで可能性ですが、ご主人が日中どなたかにカプセルを飲まされる…もちろん毒とは言わずにですが、そういったことは有り得るでしょうか?」
「日中って…職場で?それはないわね。ヒロくん、まだ支社長になったばかりで部下とうまくいってないみたいで誰も信じられないって言ってたから。誰かにカプセルを渡されて素直に飲むわけないわ」
まあ総帥令嬢と結婚したというだけでいきなり支社長になれば周囲は面白くないだろう。恨んでいた者はいたかもしれないが不仲の相手にカプセルを飲ませるというのは難しい。
…他殺説はここで行き詰ってしまう。となれば自殺?
「奥さん、先ほど自殺するはずがないとおっしゃいましたが、彼が悩んでいたとか、少しでも心当たりはありませんか?」
「ないわよ。あるはずないでしょ。家庭のことも仕事のことも、これからこうしていこうとか二人で色々話してたんだから!」
「…そうですか。失礼なことを言ってすいません」
また逆鱗に触れかねない。これ以上の聴取は難しそうだ。
「そろそろ終わりにします。最後に一つだけ教えてください。ご主人の旧姓は何とおっしゃるのですか?」
ほんの確認のつもりだった。しかし彼女は予想外の返答をした。
「旧姓?ああ、結婚前の名前ってことね。古井だけどそれが何か?」
*
聴取すべきかどうか迷ったが、私は彼女にも来てもらった。そう、離陸前に間違って安土弘樹の席に座っていた彼女。どうして自分が呼ばれたのかわからない…といった不安げな顔で細身の女性客は静かに着席する。
「突然すいません。先ほど目にされたように、あなたの前の席に座っていた男性が急変されたのです。残念ながらお亡くなりになったのですが、私は警察官として捜査をせねばなりません。ご協力頂けますか?」
「警察官…だったんですか」
「はい、警視庁で刑事をしています。男性が亡くなった原因がわからないので、彼が機内で接触した人に一応お話を伺いたいのです」
「…わかりました」
彼女の声は飛行機のエンジン音で消えてしまいそうなほど小さかった。身元を確認すると、彼女は東京在住の中村由加(なかむら・ゆか)、25歳と名乗った。
「男性が苦しみだすまでの間、彼について気になったことはありませんか?」
「気になったことですか…。いいえ、あたしにはあの人の後頭部が少し見えてただけですから。それにあたし、ずっと窓の方を向いていたので…すみません、何も気付きませんでした」
深々と頭を下げる彼女。私は「いえいえ、いいんですよ。気にしないでください」とねぎらう。それを謝られたらすぐ近くにいたのにグースカ寝ていて何も見ていない私の立場がない。
「中村さんはお休みをとって旅行中とのことでしたが、お仕事は何をされているんですか?」
緊張を緩めるため私は話題を逸らすことにした。
「あ、はい、接客業です…喫茶店の」
「ウエイトレスさんですか。中村さんは可愛いから似合いそうですね」
「いえいえ、そんな…」
ようやく彼女が少し笑う。
「あたしなんかダメダメですよ。いつも先輩に怒られてばっかりで…。先月もお水を配っている時にスキップしちゃって大目玉を食らいました」
ルンルン気分の接客か…可愛いけどさすがにそれは怒られるだろう。そういえば…私が警部に叱ってもらったことってあまりないかも。
「刑事さんはかっこいいですね。バリバリ働いてて憧れちゃいます。それにすっごい美人だし…なんかドラマの中の刑事さんみたい」
「そんなことないです。それに私もまだまだ見習いです。どうしていいかわからなくて現場であたふたしてばかりで…」
「ほんとですか?あたしもいつもあたふたして、ギャレーでてんてこ舞いです」
「ギャレーって何ですか?」
「あ、すみません。お料理やお飲み物を用意する場所で…厨房のことです」
ようやく会話が温まってきた。私は世間話を続けながら頭の中で考える。この可愛いがどこか儚い雰囲気を持つ女性が彼の死に関わっていることが果たして有り得るだろうか?機内で交わした言葉もほんの僅か、座席を間違えるトラブルはあったがあんなことで殺意が生じるはずもない。それに後ろの席にいてどうやって毒を盛る?
私は会話の最後に念のため確認した。
「中村さん、亡くなった男性と面識がありましたか?」
「え、あたしが?そんなまさか」
彼女は大きく驚いてから、また可愛く笑った。…そりゃそうか。
3
聴取を終えた私は医務室に戻る。遺体のポケットを確認するためだ。妻が証言していたように確かにスーツの左ポケットには薬がジャラジャラ入っていた。錠剤が入ったシートを1錠ずつ切り刻んでいる。いつでも取り出して飲めるようにだろう。薬は数種類あり大きさが微妙に異なっている。
ポケットには二つ分、錠剤が抜かれた殻も入っていた。飛行機に乗る前に1錠、ドリンクサービスの時に1錠…計算も合う。
私は念のために遺体の手の指も確認した。特に爪を噛む癖の痕跡はない。何らかの方法で指先に毒を付着させて自動的に口に運ばせる…というのも難しそうだ。
簡易ベッドの上、若き支社長は苦悶の顔のまま永眠している。名門の安土グループに婿入りしたわけだから当然戸籍は確認されているだろう。彼の旧姓が古井であることは間違いない。では一年前に岡本仁美に名乗った『三枝』という名前は何だったのか?
その場でしばし考えているとドアがノックされた。「はい」と返すとそこには仁美の姿。
「刑事さん、間もなく着陸態勢に入りますので席にお着きください。先ほどの乗務員控室の席で構いませんので。着席されたらベルトもお願いします」
「わかりました」
私は事情聴取で使用した部屋に戻る。そこで仁美と奈々に並んで腰を下ろしシートベルトを締めた。間もなく機内アナウンスでも乗客に着席が告げられた。
*
機体は水平飛行から少しずつ高度を下げていく。
これ以上の捜査は空港に着いてからだ。私はここまでの情報をもとに頭の中で考えを整理する。そう、いつも警部がホワイトボードでしているように。
まず他殺説とした場合。疑問①、毒はどうやって盛られたのか?そして疑問②、犯人は誰か?
まず服毒経路として最も可能性が高いのは酔い止め薬。あの錠剤に毒が仕込まれていたとしたら?誰かが毒入り錠剤をスーツのポケットに放り込んだことになる。ではそれが可能なのは誰か?
もちろん妻ならできる。しかし夫婦二人で旅行する最中に夫を毒殺するメリットが果たしてあるだろうか?どう考えても容疑は妻にかかるのに。
では妻以外が犯人の可能性。安土弘樹は今日おろしたてのスーツを家で着てから出かけている。空港までの移動はマイカー。しかも彼は飛行機の席に座るまでスーツの上にジャンパーを着ていた。誰かが彼に近付いてジャンパーのジッパーを下ろし手を入れてスーツのポケットに毒入り錠剤を…?さすがに無理がある。
では酔い止め薬以外の可能性を考えてみよう。彼が口にしたのは機内でサービスされたアップルジュース。あれに毒が仕込まれていたとしたら?
私はそこでちらりと仁美を見る。一年前に彼にナンパされた彼女…誘いは断わったと言っていたが実は応じていたとしたら?恋愛に発展していたとしたら?彼が地位に目がくらんで総帥令嬢を選び、彼女が手ひどく捨てられたとしたら?
そう考えれば動機はある。乗務員としてドリンクサービスをしていた彼女ならもちろん毒は仕込める。しかし…それはあまりにもあからさまな方法だ。彼女が渡したジュースを飲んだ途端に彼が苦しみだせばすぐに彼女が疑われてしまう。しかも毒物は青酸系化合物、となれば強烈な苦みがある。錠剤やカプセルでコーティングしているならまだしも、液体に溶かせばその味で相手に気付かれてしまうリスクが高い。
それに…そうだ!夫婦はお互いの飲み物を味見し合っていたじゃないか。もしジュースに毒があれば彼だけでなく妻も急変したはずだ。
…やはり他殺説は行き詰ってしまう。いやまだあきらめるのは早い。安土弘樹に接触したもう一人の容疑者がいる。彼の席に間違えて座っていた中村由加。
彼女は席を移動する時に彼のすぐそばを通った。その瞬間にスーツのポケットに毒入り錠剤を?…それはないか。その時点では彼はまだジャンパーを着ていた。手品師でもなければ不可能だ。
いや、彼女が犯人だとすれば酔い止め薬にこだわることはない。実はわざと35のA席に座っていて、座席の彼が触りそうな部分…例えば肘掛けに毒を塗っていたとしたら?彼がその部分に触れ、彼の指に毒が付着、そしてその指で酔い止め薬を飲んだため体内に毒が入ったとしたら…?
…無理がある。彼が必ず肘掛けに触るとは限らないし彼が酔い止め薬を飲むかどうかもわからない。そもそも彼女がわざと席を間違えていたとすれば彼が35のA席に座ることを事前に知っていたことになる。どうやって調べる?航空会社のデータをハッキングしたとしても、夫婦で予約しているから絶対に彼が窓際のA席に座るとは限らないのだ。
それに…席を間違っていると指摘された時の彼女の顔、あれは演技ではなく心底驚いているように私には見えた。
ダメだダメだ、この推理も行き詰まる。ええと他に容疑者はいるか?もちろん機内にはたくさんの乗客がいた。しかし安土弘樹は一番最後に搭乗したので彼が現れた時には他の乗客は全員着席していた。そして彼が苦しみだすまで誰も席を立っていない。
では乗務員か?しかしドリンクサービスをした岡本仁美以外に彼に近付いた乗務員もいない。乗客でも乗務員でも、接触せずして毒を盛るなんてのは何かトリックでもなければ不可能だ。
ダメだダメだダメだ、やはり行き詰ってしまう。では自殺説が有力か?
確かに彼が自分で毒を用意し自分で飲んだとすれば物理的な疑問は何もなくなる。しかし逆に心理的な疑問はかなり大きくなる。夫婦で旅行している最中、しかも空を飛んでいる飛行機の中で決行する理由があるか?そう、自殺説の最大の謎はこれ。あまりにも状況が不自然なのだ。これを疑問③にしようか。
「皆様、間もなく着陸致します。座席のベルトをしっかり締め、これ以降の化粧室の利用はお控えください」
アナウンスが入る。そこで機体が前下方に傾き、揺れが強くなってきた。降下速度がどんどん上がっている。地上が近いのだ。室内の緊張が高まる。奈々は思い詰めたように目をぎゅっとつぶり、仁美はまっすぐ前方の壁を見つめていた。
…ガガガン。
そして私の疑問は宙を舞ったままだが、巨大な鉄の鳥は無事に大地に羽根を下ろした。
■第三章 ARRIVALS
1
新千歳空港に到着。殺人事件と断定されていない現状では、当然乗客たちを足止めすることはできなかった。
午後11時、乗客たちがいなくなった機内で、私は空港警察の捜査員と共に現場検証を続けている。鑑識からの報告によれば、夫婦の使用した紙コップからは毒物の反応は出なかった。安土弘樹が座っていた35のA席の肘掛けや机からも同様だ。念のため周辺の席も調べてもらったがどこかに毒が塗られていた痕跡はなし。遺体は搬出され解剖に回されたが、現場で検死した監察医の話では青酸系化合物による中毒死で間違いないだろうとのことだった。
さて…どうしたものか。このままでは風変わりな自殺ということで決着してしまいそうだ。あるいは本当にそれが真相なのかもしれないが。
そう思いかけたところで鑑識から新たな報告が。安土弘樹の携帯電話を調べたところ、彼は飛行機に乗る直前に映画のDVDの通信販売を申し込んでいたことがわかった。注文確認のメールが届いていたのだ。おそらく妻が買い物に没頭している間に注文したのだろう。
なんてこった。自殺する直前にDVDを注文するはずがない。となればやはりこれは他殺ということになる。でもそれなら誰が?一体どうやって?
そこで私は自分の携帯電話の電源をオフにしたままだったことを思い出す。電源を入れると警部からの着信が来ていた。私は急いで折り返す。
「…はいもしもし」
いつもの低くてよく通る声が現れる。
「夜分にすいません警部、私です」
「やあムーン、無事北の大地に降り立ったかい?」
「ええ、着きました。すいません、電話の電源を切ったままにしてしまって…。今、空港警察と機内を調べているところなんです。警部、事件のことはお聞きになりましたか?」
「坂井機長から無線で君の伝言をもらったよ。君の近くに座っていた男性が亡くなったらしいね。それでどう?真相は解明できそうかい?」
「それが…まだ何とも言えない状況でして」
つい声が暗くなってしまう。私は中毒死であること、自殺説は否定されたこと、それ以上はまだ何もわかっていないことを説明した。
「そう、他殺だとしても犯人も犯行手段も見えてこないんだね?」
「あの、すいません警部、すぐ近くにいたのに私は眠っていました。私がもっと注意深く観察していれば…」
「バカ、何を言ってるんだ」
そこで急に警部の声が厳しくなる。警部からバカなんて言われたのはおそらく初めてだ。
「いいかいムーン、私たちの仕事は人を見定めようとするとても無礼な仕事だ。本来なら許されないおこがましい仕事だ。だから仕事以外の時間まで人を見定めようとする目なんて持たなくていいんだよ。
私はね、君に優秀な刑事にはなってほしいと思っているけど、人をそんな目でしか見れない人間にはなってほしくないんだ」
顔を見ずに話しているせいだろうか。警部がどこかいつもと違うように感じた。室内でもボロボロのコートとハットに身を包み、長い前髪で右目を隠した警視庁きっての不審人物。それが視覚を遮って声だけ聞くと案外まともな上司に感じてしまう。
「だからね、事件が起こる前のことなんて注意して観察してなくていいんだよ。それが当たり前なんだから。あくまで個人の視点として君が憶えていることを教えてくれ」
「…了解しました」
不思議な安心を得た私は、搭乗してから安土弘樹が急死するまでのこと、三人の容疑者に聴取したことなどをできるだけ細かく説明していく。その最中、電話の向こうからはモグモグという音…どうやら警部がおしゃぶり昆布を口にくわえたらしい。そう、これもこの人の奇妙極まりない習慣。
…よかった、私の上司はやっぱり変人だ。
*
「…ナルホド」
一通り聞き終えた警部は独特のイントネーションでそう言った。その後は沈黙。きっと右手の人差し指を立ててそこに長い前髪をクルクル巻き付けているのだろう。考え事をする時の癖だから。
「…もしかしたら」
やがて低い声は小さくそう呟いた。
「何かわかりましたか、警部?」
「ちょっとビンさんに確認したいことがある。また電話するよ」
そこで通話は切れる。ビンさん、というのは警部と私の上司でミットの長でもあるビン警視のこと。警部が発想の名人ならビンさんはまさに生き字引、教養から雑学まで幅広い知識を持っている。
私が電話をしまうと、待っていたかのように近くの捜査員が声をかけてきた。
「もうじき道警の担当警部がここに到着されます」
2
警部からのコールが鳴ったのは三十分後だった。再び携帯電話を頬に当てるとあの低い声が早口にまくし立ててくる。
「ムーン、一つの推理が成立した。安土洋樹の死の真相がわかったぞ」
私は息を呑んだ。警部の真相解明が唐突なのはいつものことだが、さすがに遠く離れた東京から電光石火で告げられると驚く。この三十分で一体何をどうしたらそうなるのだろう。
「警部、申し訳ありません、私には何が何だか…」
「いいかいムーン?君の絞った容疑者も、君が整理した疑問も妥当なものだ。でも君は最も根本的な疑問を忘れている。そのせいで答えが出ないんだよ」
…根本的な疑問?
「そしてある意味では自殺説も他殺説も正しかったことになる」
どんどん言葉を続ける警部に私は全くついていけていない。
「ムーン、しっかり考えるんだ。ここからは時間との勝負だ」
そこで警部がくわえていた昆布を飲み込む音がした。
■読者への挑戦状
ムーン刑事の見聞だけを元にしてカイカンは一つの推理を構築しました。果たして事件の真相は?
ぜひ謎という名の飛行機を論理という名の誘導灯で無事大地に着陸させてみてください。
TO BE CONCLUDED.
(文:福場将太)