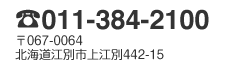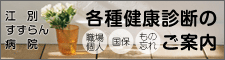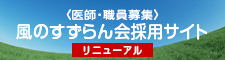- ホーム(法人トップ) >
- 江別すずらん病院 >
- コラム >
- コラム2014年06月『★連載小説★Medical Wars 第3話』
コラム
コラム2014年06月『★連載小説★Medical Wars 第3話』
Medical Wars (福場将太・著)
*この小説はフィクションです。
■第3話「幹細胞のように」 (血液内科)
1
さてさて、季節は春から夏に変わった6月最初の土曜日。この日すずらん医科大学は密かな賑わいを見せていた。といってもそれは病院ではなく、1・2年生が授業を受ける校舎側でのこと。その体育館の出口には人だかりができている。
時刻は午前11時、体育館から出てくるのはナース服に身を包んだ若き女性たち。そう、先ほどまで中で行なわれていたものこそ『戴帽式』、看護学生が病棟実習に出る証としてナースキャップを授与される儀式である。続々と青空の下に出てくる嬉しさと恥ずかしさを浮かべた笑顔たち。それを迎えるのが部活の仲間たちだ。すずらん医大は3年制の看護専門学校も併設しているため、医学生・看護学生が一緒に所属する部活も多い。迎えられた彼女たちは抱えきれないほどの花束やプレゼントを手渡され、記念撮影に引っ張りだこ…と、ちょっとしたアイドル気分を味わえる。
そろそろ全ての看護学生が表に出たようだ。人だかりはいくつものグループに分かれそれぞれの盛り上がりを見せている。では我らが14班の面々はと言いますと…いたいた、休日返上でちゃんとお祝いに駆けつけている。
例えば白衣の天使を胴上げして本当に宙に舞わせているのは柔道部、そこには長の姿がある。その向こうにはポーズを変えて何枚も記念撮影をしている音楽部、カメラマンはもちろん美唄。おっと、その隣でアコーディオンの男がBGMを奏でている…向島だ。ポリクリはサボってもここには来るのね。
あとは…いたいた、人だかりの端っこ、木陰で小さな花束を渡しているのが総勢5人の文芸部。迎える白衣の天使もわずか1名、同村含めどう見ても地味な仲間たちに拍手を贈られている。プレゼントの品もどうやら本らしい。まあ、これはこれでいいでしょう。そして人だかりの中心、恒例のお姫様抱っこで白衣の天使と記念撮影おしているのは最大の部員数を誇るサッカー部。マネージャー所属数も最多のため天使の数もダントツだ。井沢も次々と彼女たちを抱きかかえながら爽やかな笑顔を見せている。…青春ですなあ。
そのうちに文芸部は早々に解散したが、サッカー部の盛り上がりはまだまだ終わりそうもない。同村は遠めに井沢の姿を見ている。井沢の笑顔とは対照的に、そこには時折見せる訝しみの表情が浮かんでいる。
まあ弱小同好会と超がつくメジャーサークル、その差は明らかだが…同村の感慨はどうもそういうことではないらしい。
…ではでは、そんなことを念頭に置きつつ今月の物語です。
*
時は流れて6月第4週。ポリクリも3ヶ月目となり、彼らもこの生活にすっかり慣れてきたようだ。まあ良くも悪くも手の抜き所がわかってきた、という感じだろうか。その身なりもケーシーと呼ばれる半袖の白衣に変わり、病院内での立ち振る舞いも板についてきた。
今週14版が実習するのは血液内科。一般的にはあまり耳馴染みがないかもしれないが、大雑把に言えば貧血や白血病・血友病といった血液に関する病気を扱う内科である。
その初日の月曜日を終えて、彼らは学生ロビーで一休みしていた。時刻は午後7時、他の班もいくらか同じようにそこで寛いでいる。
「いやあ、結構遅くなったな。あ〜あ」
と、長があくびする。それに井沢が「そうですね。でも、血液内科は割と楽だって先輩が言ってましたよ」と缶コーヒーを飲みながら答える。続いてまりかが言った。
「血液内科はクルズスが多いみたい。明日は朝9時から15階のカンファレンスルームで河野先生のクルズスから」
「了解、班長。それじゃあお疲れ様!」
そう言うと向島はソファから立ち上がり、ロッカールームに向かった。彼は相変わらずポリクリをさぼりがちである。今日のように出席していたとしても、こんなふうにあっさり1人で帰ってしまう…おそらく音楽活動が忙しいのだろう。
「あ、もう!MJさ〜ん!」
美唄は不服そうに呼びかけるが、先輩はそれに振り返ることなく姿を消す。彼女が見い出した『14班が仲良くなる可能性』も、あのゲームセンターの夜をピークに停留状態。別に仲が悪いわけではないのだが…彼女が臨む『班飲み会』もいまだ実現されずにいる。
まあそれは珍しい話でもない。仲良し度合いは班によって様々だ。いわゆるアタリ班であれば頻繁に飲み会を企画したり、卒業旅行まで一緒に行ってしまう場合も確かにある。しかし班によっては仕事の付き合いのごとく病棟でだけ行動を共にし、それ以外は学生ロビーでさえ一緒にいない場合も当然ある。確執を持った者同士が一緒になってしまったいわゆるハズレ班などでは、それこそ周囲から見ても痛々しいほどバラバラなこともあるのだ。その意味では14班の仲良し度合いは平均的…いや、苦痛がないだけむしろ恵まれているのかもしれない。う〜ん、美唄が高望みなのかな?
現状の14班で飲み会が実現しない理由としては、春は勧誘活動やゴールデンウイークなどでタイミングを逸したこと、向島がいたりいなかったりすること、そして美唄以外にそれを切望している班員がいないことなどだろう。
さらに言うなら、それほどあからさまではないが同村と井沢の間にある溝を班員たちが無意識に感じ取っていることも、飲み会が実現しない一因かもしれない。溝、といっても何か確執があるわけではない。ただこの2人の間には根本的な価値観のずれがある、それはこの3ヶ月で本人たちも少しずつ気付き始めていることだった。
「また向島さんは音楽か。…ったく、俺たちはどうせ医者になるのにあんなに音楽ゴリゴリやってどうすんだ?」
井沢は向島の消えた方向に冷たい視線を送りながら言う。
「あの人、今年進級大丈夫か?」
「まあまあ井沢くん、MJさんはあれで幸せなんだから」
美唄が笑顔でそうたしなめる。同村はその隣で井沢の様子をまた訝しげに見ていた。
「まあいいけどさ…、俺なんか留年したら絶対生きていけないけどね」
井沢はそう言って缶コーヒーを飲み干す。そこで同村が少し強めの口調で言った。
「それは留年した人たちに、死ねって言ってるのか?」
「いや、別に…そういうわけじゃないけど」
井沢はややバツが悪そうに目を逸らすと、空き缶をゴミ箱に投げ入れた。
…このように、時々空気が淀む場面が14班にはある。それは、同村と井沢が奏でる不協和音のようなものだ。
「ま、ウチの大学は確かに留年多いからな〜俺も怖いよ」
「そうですよ、多すぎですよね〜アハハ」
長と美唄が場を取り繕う。まりかも慌てて「そうそう、油断禁物」と口にした。
その後10分ほど談笑してその場は解散となったが、同村と井沢が言葉を交わすことはなかった。
*
「ごめん、さっきは…」
帰りの地下鉄の中、同村はまずそう切り出した。「え、何のこと?」と美唄が首を傾げる。
「井沢の言葉に、イラッときちゃってさ…」
「あ、うん…」
美唄はそこで弱い笑顔を見せた。あ、読者のみなさん、断っておきますがこの2人まだデキていませんから。
「井沢は悪い奴じゃないのはわかるけど…時々カチンときちゃうんだ」
普段無口な同村がこんなふうに自分の内心を美唄に話すのは…何故だろう。彼女に惹かれているからなのか、彼女なら本心で答えてくれると思えるからなのか。
「ごめん、遠藤さんや長さんが14版を盛り上げようとしているのはわかってるんだけど」
「そんなの、気にしないでよ」
美唄はその大きな瞳で同村の瞳を見る。
「確かに井沢くんって時々…ちょっと無神経なこと言ったり、MJさんのことも本人がいなくなったらよく悪口言ってるけど…。まああれはMJさんが悪いのか」
彼女はそこでクスッと笑う。
「でも、井沢くんっていい人だと思うな。先輩にも後輩にもすごく顔が広いし、ポリクリでも先生によく気に入られてるし…」
「…そうだね」
「頼んだことは絶対やってくるし、遅刻も絶対しないし。…真面目なんだよ」
同村はそこで彼女から瞳を逸らす。
「それに同村くんって、普段あんまり思ってること言わないじゃない?だからあんなふうにちゃんと発言するのっていいと思うな」
「そう…かな」
「そうだよ」
同村はそこでまた美唄に視線を戻す。
「遠藤さんって、本当に人をよく見てるね」
「え?そっかなー」
「人の行動、もあるけど…なんか人の心をよく見てるっていうか」
「…そう?なんか、すごく嬉しいな」
美唄はそこで下を向いて微笑む。それは、いつもの元気100パーセントとは違う微笑み方だった。
「ありがとう同村くん。大丈夫、14班は大丈夫だよ。そりゃ仲良くしたいけど、それは表面的にじゃなくて、それこそ心からだもん。時間かかったっていいじゃない。まだまだ、これからだよ!」
そこで電車は同村の降りる駅に到着した。くり返しますが、2人はデキておりません。ここで降りるのはもちろん彼1人です。
*
駅からの帰り道、同村は考えていた。
自分は何にイラついているのだろう。確かに井沢は遠藤さんの言うように真面目な奴だ。友達も多いし、みんなで約束したことは必ずやってくる。人を裏切ったり騙したりすることもない。向島さんに対する発言だって、当然といえば当然だ。…なら、何故?
同村にはその答えがわかっていた。入学して以来、ずっと考え続けている『個性をなくした医学生』…その典型が彼、井沢なのだ。
医学部にいることや、医学部のシステムに何の疑問も抱かず、与えられる環境を全て受け入れる。大多数から外れることを何より恐れ、みんなと同じことをしていれば大丈夫という意識にとりつかれた、無個性人間。自分の恵まれた環境を当然と考え、逸脱した金銭感覚にも、自分が世間知らずの苦労知らずであることにも気付かず、医学生という優越感だけが肥大している。
実際に井沢がそういう人間だと断定できるほど彼と語りあっ多ことなどない。しかし同村の瞳にはそう映っていた。考えれば考えるほどイライラしてくる。
もちろん勝手に人を判断するのはおこがましいこと、自分が人を批判できるほど優れているわけではないことも同村にはわかっていた。ただ、井沢の言動が時として、彼の耐えられない部分に触れるのだ。
これまでの井沢の言葉が頭の中で反響する。
…「看護婦のくせに」
なんだよ、くせにって!お前は何様だ?自分の家が代々医者で、自分もその流れで医学部に来ただけのくせに!
…「留年したら生きていけない」
留年した同級生たちは、そんなに恥ずかしいのか?生きる価値がないっていうのか?自分が順調に進級してるから言えるんだろうが!
…「俺たちはどうせ医者になるんだから」
どうせってなんだ?たいした人生の選択もしてこなかったくせに、何がどうせだ!それともお前は医者になる運命で生まれてきたっていうのか?
同村の表情がどんどん険しくなる。まあまあ、あんまり考え過ぎると精神衛生上よくないよ、同村くん。ほらほら、美唄ちゃんのことでも考えてさ、穏やかになりなさいな。健全じゃないぞ!
結局その日は眠りにつくまで、イライラ顔の彼であった。
*
水曜日、14班は15階のカンファレンスルームで河野医師のクルズスを受けていた。河野は細身の体にブカブカの白衣をまとった40前の男性医師。彼はその細い指で教科書をめくりながら話す。
「いいですか?血液の病気はたくさんあるけど、まず大切なのはその分類です。赤血球の病気なのか、白血球の病気なのか、それとも血小板や凝固因子の病気なのか…。つまりどこが障害されているのかということをちゃんと整理してください。4年生の講義でもやりましたね?例えば貧血といっても色々な種類があって、鉄分が足りないのか、足りていてもうまく使えていないのか…」
室内には河野の細い声とページがめくられる音だけが響く。
「ではもう一度基本を押さえておきましょう。21ページの表は何度も見たことがありますね?」
学生たちは急いでそのページを開く。そこには1つの細胞から樹形図のように枝分かれしていき、やがて役割の違う別々の細胞に成長していく過程が描かれている。
「このように、赤血球も白血球も血小板も…すべては同じ造血幹細胞から分化します。幹細胞の特徴は、自己再生能と分化能という2つの能力を持つことです。
うーん、まあ簡単に言えば、何度でも再生するし何にでもなれるってことですね」
まりかがものすごいスピードでノートを取る。その他の班員も各自教科書にマーカーでラインを引いている。ただし、向島だけは爆睡中…オイオイ。
「幹細胞は様々な因子の影響を受け、赤血球になるグループ、白血球になるグループ、血小板になるグループなどに分かれていきます。この幹細胞の分化の図はとても有名で、卒業試験にもここから毎年問題出てるから要チェックです」
そこで河野のPHSが鳴った。院内では、医療機器への影響を考慮し携帯電話ではなくPHSが用いられている。
「はい、河野です。あ、わかりました…」
河野は電話を切ると「君たち、ちょっとごめんね、すぐ戻る」と言いながら足早に部屋を出て行った。大学病院の医師は診療の合間に学生の相手をしている。急用で呼ばれれば中座することもよくある話。14班にとってももちろん初めてのことではなかった。
「あれからもう30分は経つね…ウ〜ン」
待ちぼうけの続く中、美唄が大きく伸びをして立ち上がった。まあ待たされるのもポリクリのうち、とはいえさすがに座りっぱなしは疲れる。彼女は午前の陽光が差し込む窓辺に寄る。
「あ、キーヤンカレーが見える!あそこのカレーってメチャクチャおいしいんだって。ほら、まりかちゃん!」
呼ばれたまりかも教科書を置いて立ち上がる。
「へえ…そうなんだ」
「本当においしいらしいよ!今度みんなで行こうよ」
「ここから見えるんだな、キーヤンカレー。俺も1回行ったけど相当うまいぜ」
そう言って長も立ち上がり、2人の所へ行った。それに続いて井沢も立ち上がる。同村はそんな彼の姿をまたまた訝しげに見る。そして、窓辺の会話がどんなに盛り上がっていようと、彼は相変わらず爆睡中の向島の横に座り続けるのだった。
…まあまあ同村くん、そこまで意固地にならなくても。
2
木曜日、教授回診。ドラマや映画でご存知の方も多いだろう、教授を筆頭とした大名行列が病棟を闊歩する例のあれだ。入院している患者たちにはもちろんそれぞれに主治医がいるが、週に1回教授が全ての患者の現状を把握するためにこの回診は行なわれる。まあぞろぞろ医者や看護師が教授の後をついて歩くのは確かに権威的である。もっと効率的なやり方もあるような気がするが…大学病院では白黒映画の頃と同じこの儀式が未だに続けられている。
そんな中ポリクリ生の指定席は、もちろん大名行列の最後尾。14班の5人(誰がさぼっているかは言わずもがな)も黙々とついて歩いていた。この位置では教授の診察の様子などほとんどわからない。正直あまり勉強にはならないが、まあこれもまたポリクリのうち。将来の職場体験だと思えばこれはこれで意味がある。2時間立ちっぱなしや歩きっぱなしはもう慣れっこだし、それに先頭にいる教授は学生の何十倍も大変なのだから文句は言えない。
大名行列は1つずつ病室を訪ねていく。もちろん大きな病室だけではない。小さな病室やベッドが1つしかない個室の場合だってある。その時は行列全員が入りきらないことも当然あり、溢れた者は廊下で立ちんぼとなる。
ある病室では医局員と井沢が入ったところで部屋は満員となり、残りの4人は廊下に留まった。井沢はふと振り返り、自分だけ飛び込んでしまったことに気付く。すると彼は、おずおずと廊下に戻ってきた。
そんな行動を見てまたイラッとしてしまうのが同村。彼は井沢の代わりに病室へ飛び込んだ。2人の様子を見て、長と美唄は目配せをする。おそらく、「またこのパターンだね」ってところだろう。まりかはそんな班員たちの様子を何ともなしに眺めていた。
…どうですか?同村と井沢の、些細ではあるが決定的な感覚の違いがおわかりかな?
*
教授回診の後、午前の実習は終了と宣言され、彼らは病院食堂に向かった。20階のフロアの3分の1ほどを占拠する巨大な食堂。利用できるのは病院職員と学生だけなので客の大半は白衣姿だ。ちょうど6人がけのテーブルが空いていたため彼らはそこに陣取る。本来なら向島がいるはずの空席に荷物を置き、各自のランチを取りに行く。
「ではここで、14班ク〜イズ!」
料理が揃ったところで、美唄がそう言った。
「お、何打それ」
長がうどんをすすりながら反応する。
「また何か思いついたの、美唄ちゃん?」
と、まりか。彼女もいつしか『遠藤さん』ではなく『美唄ちゃん』と呼んでいる。まあ2人しかいない女の子同士の仲がよいのは結構なことだ。同村くんと井沢くんも見習いたまえ。
「そうなのまりかちゃん。実はこの前すごいことを発見しちゃってさ!…さあ、そこで問題です!14班のみんなが集まると、さてどうなるでしょう?」
美唄はやたらに得意げだ。
「え、どういう意味?」
と、井沢。続いて同村もカレーを口に運びながら言う。
「みんなが集まったらって…毎日集まってるじゃない。まあ向島さんは時々いないけど」
「みんながひとつになるとどうなるかって感じかな?どう、まりかちゃん、わかる?」
「…ん〜何だろう?クイズとか苦手なの」
まりかは笑顔で答える。4年生まで同級生たちとほとんど交友せずに過ごしてきた彼女にとってここでの語らいは、きっと楽しい…好きな時間なのだろう。
「う〜ん、わかんねえ」
と、長。同村もスプーンを止めてブツブツ言う。
「メンバーの頭文字だと…あ、い、え、ち、ど、む…並び換えて…う〜ん、わからないな」
「あ、同村くん、ちょっとおしいかも!」
「え?う〜ん…」
「わかんないよ、美唄ちゃん」
井沢がそう言って彼女を見る。
「みんな降参?なら、答えは宿題で〜す!」
「おお、気になる!今教えてよ!」
「ダメですよ長さん!…そうだ、いつか14班で飲み会しましょ!その時みんな揃ったら、そこで発表します!」
美唄…君は究極のエンターテイナーだ、拍手!まあこの明るさが時に疎まれてしまうのだが、14班のメンバーは向島はもとより彼女のノリが嫌いではないらしい。何よりである。
「う〜ん、悔しいな〜」
と、井沢が頭をかく。
「それ、口頭試問に出たらどうしよう」
まりかも時々こんな冗談を言うのだ。彼女が14版で笑顔になれる理由…そう、少なくともここでは『特待生』というレッテルを意識しないですむ。今まではいつも授業中最前列に座り、ひたすらノートを取りながらも、その背中に同級生たちの視線を感じていた。誰も直接口にはしないが「特待生ってすごいね」という言葉の裏にある「なにそんなに勉強ばっかやってんの」という侮蔑。もちろん医学部で毎年特待生となるのは容易なことではない。彼女もそれなりに誇りに思っているし、彼女には彼女の勉強したい理由がある。それでも、偏った見方をされるのはやはりよい気持ちはしない。それが14班においては、そんなことを考えずにすむ。ただ単に特待生がどうしたってくらい個性派揃いだからなのかもしれないが…ともかく彼女は居心地のよさを感じている。自然と口数が増えるのがその証拠だ。
「う〜ん、わからん!このままじゃ悔しいから、今度は俺がクイズを出すよ」
そう同村が言った。ちなみに彼もまりか同様、入学以来今年が一番同級生と話しているのは間違いない。
「お、同村もか。みんなすごいな!」
いつしか長も彼を呼び捨てにしていた。この3ヶ月で少しずつそれぞれの距離は縮まりつつあるようだ。
「出して出して!」
美唄も笑顔100パーセントで大はしゃぎ。
「ではいきます。この14班の中で、逆立ちして淡路に行ったのは誰でしょう?」
「あ、逆立ちってことは、きっと逆から読むのね」
「さすが班長!」
そう言って同村は指をパチンと鳴らす。
「淡路…じあわ?淡路って言えば淡路島だから、…ましじあわ?あれ?」
美唄も楽しそうに悩む。「逆にしても誰の名前にもならないぞ」と井沢も言う。「お〜いまた宿題かよ」と長も半ば降参のようだ。しかしここで、まりかがひらめいた。
「あ、わかった!答えは井沢くんね」
「え、俺?」
「そう、君だよ」
同村は笑顔で井沢を見る。この2人…けして仲が悪いわけではないのだ。時に生まれる不協和音も距離が縮まったからこそのものなのだろう。
「井沢はローマ字でIZAWA、それを逆から読むとAWAZI…淡路。さすがは班長だね」
同村はそう言ってまた指を鳴らす。
「なるほど…」
井沢は目を閉じて上を向く。頭の中でローマ字を浮かべているようだ。
「ホンとだ、すごいすごい!」
美唄は実際に手帳を取り出し書いて確認している。ここまで喜んでもらえると、出題者冥利に尽きますね。
「へえ、ローマ字で逆から読めるなんて珍しいな」
長も感心したように食事の手を止めて腕を組んだ。
「そうでもないですよ、結構たくさん例はあります」
同村もそう言ってスプーンを置く。
「例えば、このローマ字にして逆さ読みって方法で変換すると、『犬』は『ウニ』、『イカ』は『秋』になります。人の名前なら…『悦子』が『オクテ』、『赤野』が『お腹』とか。あとこの前地下鉄に乗ってて気付いたんですけど、『赤坂』は逆からでも『赤坂』…」
「わ〜スゴイ!」
と、美唄。
「お前はローマ字研究家か?」
井沢が興味深そうに尋ねる。
「いや、そうじゃなくて…推理小説の暗号とかでよくあるんだよ。俺、自分でも時々書くから普段からアイデア探してるんだ。あ、だから『まりか』なら『アキラM』になる、とか。ね、使えそうなネタだろ?」
「なるほどね…」
井沢が呟いた。美唄が「同村くん、また新しい小説書いてるの?」と尋ねる。
「ああ、うん。今書いてるのは推理モノじゃないんだけど…まあでもポリクリのレポートとかあるから、毎日1時間ずつくらいだけどね」
彼は執筆の話だと子供のように純真な笑顔になる。
「そうなんだ〜すごいね」
「別にすごくないよ…ただ、好きだからさ。そういう遠藤さんは家で何やってるのさ」
「へっへ〜、実は最近ちょっとずつギター練習してるの。MJさんにお古もらったんだ。ギター弾きながら歌えたらいいなと思って」
そんな会話を、井沢は興味深そうに聞いていた。美唄が今度は「長さんは暇な時何してるんですか?」と質問を回す。
「俺?う〜ん、俺は…そうだな、バイクのメンテナンスかな」
「なるほど〜。じゃあまりかちゃんは?」
「う〜ん、…テレビゲームかな」
そこで同村が「お、意外!」と反応する。
「結構…好きなの。あとは…やっぱ勉強かな」
まりかはそこでまた笑う。彼女も14班以外では、おそらくこんな発言はしないだろう。
「さっすがまりかちゃん!それじゃ、井沢くんは?」
「お、俺は…」
美唄の大きな瞳に見つめられ、井沢は一瞬戸惑う。
「俺は…テレビでドラマ見たりとか…あ、あとそう、サッカーの試合見たりとか」
「そっか〜、サッカー部だもんね、フンフン」
美唄は何かを納得したように大袈裟に頷く。そこでまりかが時計を見て、「美唄ちゃん、お話もいいけど早く食べないと、次遅れちゃうよ」と忠告。
「あ、ほんとだ!わかりました、アキラMちゃん」
そこでまた笑いが起こる。ポリクリは日によってはゆっくり食事もできないくらい忙しい時もある。たまにはこんな昼食もよいものだ。
*
午後3時、再び15階カンファレンスルーム。ようやくやって来た向島も加わり、6人は昨日仮提出したレポートの審査を受けていた。担当はクルズスでも登場した河野医師。
「基本的にはみなさんよく書けていました。特に井沢くん、よく質問に来ただけあって、大変きれいにまとまってます。明日までに、血球の分化と、その過程のどこが障害されるとどの病気になるか、もう少し文献調べて書いてみて」
「はい、わかりました」
レポートを受け取りながら井沢は頭を下げる。その顔は完全にポリクリモードだ。
「あと、君、同村くん」
河野は少し神妙な顔で彼を見た。
「君は…何だろうね、文章力がありすぎるっていうか、表現が情緒的すぎるっていうか…」
同村は少し嬉しそうに「はい」と答える。
「いや、別に誉めてないよ。小説家になるんじゃないんだから…いや、すごい才能だと思うけど、レポートはもっと無感情に書きなさい。一般の人向けの、医学紹介の本とか書いたらいいかもね」
河野の皮肉を含んだ指摘に、同村は肩を落として頷く。
「あと感想のコーナーも…勝手に作ってるけど、別に求めてないものをここまでたくさん書かなくても」
河野はそう言うと、あきれ顔でレポートを手渡した。同村はちょっと落ち込み気味だが、そんな君を美唄は優しく見つめていたから…まあいいじゃないか!
*
午後8時、その後もろもろの実習を終え、6人は学生ロビーに落ち着いた。遅い時刻だからか、もう他の班の姿はなかった。
「今日はこれでおしまい。明日、直したレポートを提出して血液内科は終了ね」
と、まりかがソファに腰を下ろしながら言う。美唄も「は〜い、班長!」と勢いよく座った。疲れ知らずの明るさは顕在だ。残る男性陣も続いて腰を下ろす。
「それにしても、相変わらずレポート挑戦してるね、同村」
長が缶コーヒーを開けながら言った。同村は「ええ、まあ…」と小さく答える。そんな彼に美唄がエールを贈る。
「まあ、河野先生はあんまり喜んでなかったけど…いいじゃない。時々すごく誉めてくれる先生もいるんだし」
「まあ、そうなんだけど…」
「何で、形式どおりに書かないんだよ?先に血液内科を回った班からの資料、渡しただろ?」
井沢が問う。同村は下を向いたまま答えた。
「なんていうか、それじゃ面白くないっていうか…。この大学にいるとすごく感じるんだ。人と違うことをする勇気を…忘れちゃいけないって」
「そう…」
と、まりかが呟く。
「俺はそれを勇気とは思わないけどな」
井沢は手厳しい。また空気が淀みかけるが、長が「まあ人それぞれだからね」とその場を和ませた。
と、そこで井沢の携帯電話が鳴る。もちろん院内では電源を切っているのだが、病院を出ると彼はすかさず電源を入れるようにしているらしい。
「ちょっとごめん。あ、もしもし哲ちゃん?」
そう言って井沢は席を立つ。どうやら相手はサッカー部の古川のようだ。
「あ、そうそうMJさん、ギター教えてくださいよ」
ソファでは美唄がそう切り出した。
「ん?でも、どの辺りを?」
音楽部先輩は眠そうな瞳で美唄を見る。
「え〜と、コードチェンジとかです」
「そんなの…本を見て押さえ方を憶えるしかないよ。コツとしては、コードチェンジの時は、必要最小限の指の動きにすること。指をバタバタさせずに、そのままでいい指は指板から離さないこと」
彼は特に得意げになる様子もなく答える。すると後輩は頭の中で何やらイメージトレーニングを始めたようなので、代わって同村が会話を続けた。
「向島さんって、キーボードを弾くんじゃないんですか?4月の勧誘ライブでちょっと見て…」
「あ、色々やるんだ、俺。ドラムの時もあればベースの時もあるし、ボーカルも時々ね」
長が「すごいっすね」と驚くと、向島は今度は少し得意げに瞳を閉じた。
「MJさんはオリジナルのCDもたくさん作ってるのよ」
と、美唄。イメージトレーニングは終わったようだ。
「へえ、今度聴かせてくださいよ」
同村がそう言った時、井沢が戻ってきた。長が「おう、お疲れ」と彼を迎える。
「いや〜哲ちゃんが消化器外科回った時、オペ室の看護婦と仲良くなったらしくて、今日飲み会やってるんですよ」
「へえ〜すごいな」
と、長。まりかは興味なさそうに手帳を開き、明日の予定に視線を落とした。美唄は「さすがはサッカー部!もてるね」と冷やかす。
「別にそんなんじゃないよ、美唄ちゃん。まあ盛り上がってたら俺も行こうかと思ったんだけど…別にそうでもないみたいだから行くのやめようかなって」
長が「ありゃ、もったいない」と笑う。
「別にいいですよ。オペ看って、マスクとかで顔隠れてるから、つい美人に思えちゃうんですよね」
「ハハハ、そうかもね」
「それに盛り上がってもないのに、途中から行って看護婦なんかに金出すのもバカらしいし…」
そこで井沢はあくびをしながら大きく伸びをする。
「看護婦なんか…?」
同村が小声でリピートした。こ、これは、まずいムードだ。
「ふざけんなよ井沢!」
同村が怒鳴って立ち上がった。みんな驚いて彼を見る。
「お前、何様だよ!いつもいつも…そんな肩書きばっかりで人を判断しやがって!」
「何だと!」
井沢も声を荒げる。ま、まずい…!
「看護婦なんかとか、所詮看護婦とか…なんでそんなことが言えるんだよ!サッカー部には看護学校の女の子だっていっぱいマネージャーやってるじゃないか!そんな、そんなふうに思ってるんなら…偉そうに仲間だなんて思ってんじゃねーよ!」
井沢は口をつぐんで瞳を逸らした。
「肩書きだけで言ったら、お前なんかただのレールに乗って生きてるだけの、世間知らずのボンボンだろうが!」
同村、それは言ってはならないことだ。
「いつもいつも何なんだよ、お前は!俺たちはどうせ医者になるとか言いやがって、なんだよどうせって?なに偉そうにあきらめてんだよ!自分で…自分で、決めろよ!」
「どういう…意味だ?」
井沢は視線を戻し、静かに尋ねる。長は2人を抑えようと身構えていたが、しばし静観することにしたらしい。美唄は黙ったままうつむいており、まりかと向島はそっぽを向いている。再び夜の学生ロビーに同村の声が響いた。
「お前は…いつも周りを見て動いてる!実習でも、日常でも、いつも大多数の方に入ろうとしてる!過半数が立ち上がるまでお前は座ってる、過半数が座ったままなら立ち上がらない!最初に立ち上がることも、最後まで座ってることもない…お前の、お前自身の考えはどこにあるんだよ!この3ヶ月、ずっとそうだ!」
井沢は黙って聞いている。
「お前が正しいと思ってることは何なんだよ?お前の意志はどこにあるんだよ?お、お前の人生を生きてんのは…誰なんだよ!!」
溜まっていたものを一気に吐き出すように同村は言う。井沢が「わかったようなコと言うな」と小さく返したが、さらに同村の訴えは続く。
「さっきの飲み会だってそうだ!盛り上がってなかったら行かないのかよ!そんなふうに…人間関係って都合のいい時だけ繋がってるもんじゃねえだろ?どうしていつもアタリの方を選ぼうとするんだよ!」
「ふざけんな!」
今度は井沢が叫んだ。
「勝手に人を判断すんな!お前はどれだけ考えてるっていうんだよ!お前だって現役で私立医学部にいる世間知らずだろうが!何がみんなと違うことをする勇気だよ、ただ人付き合いが下手なだけなのに、自分は人と違うってカッコつけてるだけだろ!
みんなと違うレポート書いて、大学の体制を批判してりゃ考えてることになんのかよ?そんなのただの天邪鬼だ!お前こそ、みんなと違うようにするってことばかり意識して、結局周囲に左右されてんだよ!」
今度は同村が視線を逸らす。
「勝手にレポートに感想書いて、結局自分のわがままを通してるだけだろ?目立ちたくて自分のやりたいことをやってるだけだろうが!」
「違う!」
「もうやめて!」
同村と美唄がほぼ同時に叫んだ。そこで同村も井沢も言葉を止める。
…ついに割ってしまった。これまでなんとか運んできたガラスの造形を。
夜の学生ロビーには重い沈黙が流れる。普段聞こえない時計の秒針の音、自動販売機のうなり声だけが、その場を支配していた。
…パン!
少しの後、まりかが大きな音で手帳を閉じた。
「ではみなさん、明日は8時にここ集合です。お疲れ様でした」
そう言うと彼女は立ち上がり足早に歩き出す。それに続くように、みんな無言のまま学生ロビーを出て行った…ただ1人、同村だけを残して。
同村は、学生ロビーを出て行く美唄の、かすかな泣き声を聞いたような気がした。
*
午後9時半、同村はまだ1人学生ロビーに座っている。彼は考え続けていた。何度も何度も、井沢の言葉を頭の中でくり返しながら…。
井沢が言ったことは…当たっているのかもしれない。
俺は自分を証明したくて…井沢を否定しようとしていただけなのかもしれない。医学部の在り方を批判しても、小説を書いても、結局それはただそれだけ…。何の結果も出せていない。何も、変えられていない。そんな自分自身に…一番イラついていたのかもしれない。
…最低だ、俺は。
そんな想いが彼の心に溢れてくる。入学以来ずっと抱えてきた葛藤…それが無価値で無意味なものに変貌してしまうのか。彼は打ちのめされたボクサーのごとく、ただその場に脱力していた。
その時、携帯電話が鳴った。同村は力なくその画面を見る…長からだ。
「…もしもし」
「おう同村、もしかしてまだ学ロビ?」
長の声はいつものように明るい。
「…はい。さっきは、すいませんでした」
「いいよいいよ」
長はやさしくそう言った。
「たまにはあんなふうにぶつかるのも大切さ。お互い、自分では気付いていないことに気付いたんじゃないかな?」
同村は黙ったままだ。
「大丈夫、俺、こんな話が出来るのってすごいことだと思うよ。本当に相手のことがどうでもよかったら、あんなケンカにはならないよ」
「…ありがとうございます」
「確かに井沢は、同村の言うようなところがある。でもね、彼のような真面目な人間がいないと、絶対に組織は回らないんだよ。医者が全員パッチ・アダムスだったら大学病院は崩壊だ、ハハハ…」
「そう…ですね、ハハハ」
同村も無理に笑う。
「それにね、前に井沢と話したことあるんだけど、彼のお家は代々医者で親戚も医者だらけなんだって。しかも、彼の父親は産婦人科医…やがては彼もその病院を継がなくちゃいけないんだって」
同村はまた黙る。
「子供ってのは、親が言わなくてもその辺を敏感に感じ取るじゃない?そんな環境にずっと生きていたら…洗脳とまでは言わないけど、彼が医学部に進んだのも、まあ無理もない話じゃないかな。
それに、産婦人科医ってのはずっと病院の近くにいなくちゃいけないからね。彼は子供の頃から父親と家族旅行なんて、ほとんどしたことがないそうだよ。たまに日帰りで行っても、父親は途中で病院に呼ばれて帰っちゃったり…」
「そう…なんですか」
「確かに、お金持ちで世間知らずのところもあるけど…だからって、井沢が何もかも満たされているわけじゃない。苦労を知らないわけじゃないよ」
同村の父は自宅で開業している歯科医だ。…思えば、朝食も昼食も夕食も、いつも父親と一緒にいた。家族旅行もたくさんしたし、よく2人で出掛けたりもした。彼は父親とはそういうもの、それが当たり前だと思っていた。
「俺さ…」
少し長のトーンが下がる。
「ずっと好き勝手やってて、遊んでる時間が長かったじゃないか?浪人も長かったし、真面目にもやってなかった。親に苦労かけっぱなしなんだよね…未だにスネかじりだし。だから…親の期待に応えて生きてる井沢とか、すごく立派だなって思うんだよ」
「…はい」
同村は素直に答える。
「ハハハ、な〜んてね、キャラじゃないか!まあ話はそんなとこ。じゃ、同村、気をつけて帰れよ!また明日な!」
「はい、ありがとうございました」
「ホイホイ、じゃ〜ね〜」
長の電話は陽気に切れる。
同村はしばらくそのまま携帯電話を握り締めていた。
グッジョブ副班長!さすが長さん、年の功!
*
同時刻、井沢は自室でパソコンに向かっていた。新宿で2LDKのマンション、家賃は余裕で2ケタを超える。
レポートの直しをしながら、井沢も考えていた。同村の言葉が頭の中でくり返される。
…痛いところを突かれた。それがまずは正直な想い。
自分でもわかっている。自分に何が欠けているのか。
看護婦に対する発言だって、別に妙な差別意識があるわけじゃない。サッカー部の男仲間や先輩たちは、よくそういうことを言って盛り上がっていた。だから…いつしか自分も癖になってしまった。
…最低だ、俺は。
同村の言うことも、悔しいが的を得ている。俺が正しいと思っていることは、何だろう?
俺は、実習をサボって音楽に明け暮れる向島さんも、5年生になってギターを始める美唄ちゃんも、この忙しいさなか小説を書く同村も…理解できない。いや、理解は出来る。実感ができない。
みんながそんなことをする理由は1つ…『好きだから』だ。好きだから、どんな状況でもそれをやるし、それを面倒臭いとも思わない。
俺には…そこまで好きなものがない。
休みの日があっても、何をしようか考えてしまう。だから、今日の昼食の会話の時、正直みんながうらやましかった。好きなものを堂々と答えることが出来るみんなが。
サッカー部だって、この大学では盛り上がってるというから入った。この大学の勝ち組になれると言われて…。
考えたら俺はいつから医者になろうと思っていたんだ?
物心ついた頃からそう思っていたような気がする。小学校・中学校・高校…いつも自分は医者になることを前提に過ごしていた気がする。白紙の未来などなく、いつも将来が見えていた。だから、何かに純粋に夢中になったことなんて…もしかしたらなかったのかもしれない。
俺はそのことを考えないようにしていた。今までの人生、取り返しのつかない過ちだと思いたくなかった。自分で動かなければ手に入らないものがたくさんあって、自分はそれを全部気付かずに見過ごしてきたなんて…考えたくない!
もちろん、夢を描けば幸せな人生だなんて思わない。そんなに甘くはないし、夢だけでは生きていけない。夢が全部叶う人なんて、ほんの一握りだ。あとの連中は夢をあきらめるか、懲りずに追い続けるか…。
でも、俺は…どうだろう?
夢が見つからない?…いや、そうじゃない。そもそも夢を探してもこなかった。
「くそっ!」
井沢はそう吐き出す。いつしかレポートを打つ手は止まっていた。そして想いはまだまだこみ上げる。
このレポートだって、明らかに先生の望むように書いている。先輩や先に回った班から情報をもらって、評価された人のを真似ている。
そう、俺は病院ではいつも先生に気に入られるように動いている。この大学に入ってから、いつしかそれも癖になってしまっている。正直、無理をしてないとは言えない。そうだ、努力しているつもりだ!
そのおかげでたくさんの先生に名前を憶えてもらった。俺は、みんなと違ってしまうのが何より怖いくせに、そのどこかで、みんなを出し抜こうとしている。みんなに内緒で河野先生に質問に行ったりした。
…姑息だ。
同村は自分の思うようなレポートを書き、よく怒られてもいるが、逆にすごく誉められている時もある。俺みたいに無理しないで、ありのままの自分で先生に憶えられている。
…俺は間違っていたのか?
…俺の人生を生きているのは、一体、誰なんだ?
畜生、同村の言う通りだよ。
そこで井沢はキーボードにIZAWAと打った。
「井沢…淡路、か」
誰よりもこの名前を見てきたのに、俺はこんなこと、考えつきもしなかった。こんなクイズができるなんて…。
誰よりもアタリを選んで生きてきたつもりだったけど…きっと世の中、俺の知らない幸せがたくさんあるんだろうな。
劣等感というものをここまで感じたのは初めてだ。俺は、医者になるために生まれてきたのか?最初からそのことが決まっていたのか?
そこで部屋の電話が鳴る。彼は椅子に座ったまま手を伸ばした。
「はい、あ…母さん」
「もしもし大輝、元気かい?」
電話の向こうの声は、とても明るい。
「ああ元気だよ。母さん、どうしたの?」
「あのね、来週の日曜、こっちに帰って来れる?嘉彦おじさんがね、今度教授になるんだって。そのお祝いに家でホームパーティするの」
「ああ、わかった、帰るよ」
井沢は力なく答える。
「どうしたの大輝、元気ないわね」
「そ、そんなことないよ」
そこで井沢は笑顔を作る。…これも彼の悲しい癖だ。
「ちょっと疲れてるだけ。それじゃ母さん、レポートがあるから」
そう言って電話を切ると、机に向き直る。
「ハア…」
大きく溜息。
…とその時、パソコンの横に広げた教科書が目に入る。河野医師がクルズスで説明していた、造血幹細胞の分化の図だ。
「幹細胞…」
思わずそう呟く。そしてその図から瞳が逸らせない。
井沢の頭の中で、何かが繋がろうとしていた。
似てる…この図、人間の人生にそっくりだ。
最初は何にでもなれる幹細胞、それが色々な因子の影響を受け、いつしか道が分かれ、あるものは赤血球に、あるものは白血球に、あるものは血小板に…。
そうだ、そうだよ…!
「ハ、ハハハハ…」
他に誰もいない室内に笑い声が上がる。彼の中で何かが繋がり、何かがふっ切れた。
…そうだよ。最初は何度でも再生し、何にだってなれる可能性を持った肝細胞、人間だってそうだ。赤ちゃんは、何にだってなれる可能性のカタマリ。そう、親父の病院でみたたくさんの赤ちゃんはみんなそうだ。運命なんか決まっちゃいない。
俺だって医者になることが決まって生まれたわけじゃない。最初は、幹細胞だったんだ。そうだ、そうだよ…。まだ、分化は終わってない。まだ俺は再生できる。俺はまだまだ幹細胞だ!
何を思い込んでいたんだ、俺は!
「ハ、ハハハハ…!」
井沢は1人痛快に笑った。
どうやら同村だけではなかったようだ。彼の胸にもまた、毎日少しずつ少しずつ積もる葛藤があったのだ。そして今、それを撒き散らすように彼は高らかに笑っている。
そうだよ、井沢くん。君だけじゃない。君たちはまだまだ、無限の可能性を秘めている。そうでなくてはこの物語も困ります。
*
午後10時過ぎ、同村はようやく病院の敷地を出た。その時、出口で声をかけられる。
「同村先生!」
「あ、鮫島先生」
産婦人科で学生指導だった鮫島医師だ。私服姿だが、どうやらまだ仕事があるらしく彼は病院の敷地に入ってきたところだった。…遅くまでご苦労様です。
「どうもお久しぶりです」
「今までポリクリかい?大変だね」
「いえ、勝手に残ってただけで…」
「へ〜。そうそう、君のレポート、僕も読んだよ。志田先生に見せられてね」
「は、はい…勝手な内容ですいません」
河野医師の件もあり、同村は謙虚に答える。
「いや、すごいね、君。あんなふうにいろんなこと考えて実習に臨んでくれていると思うと、こっちも指導しがいがあるよ。コピーして医局員に配ったくらいだよ、ハハハ…」
鮫島は大きく笑う。白衣姿ではないせいか、今夜の鮫島は病棟で会った時より気安い雰囲気がある。同村も一応合わせて笑った。
「ありゃ、なんか元気ないな。今はどこ回ってるの?」
「は、はい、血液内科です」
「そうか。うん、じゃあ明日も元気出して頑張らないとな。血液の知識は将来どの科に進んでも必ず必要だから」
そこで鮫島は同村の肩を叩く。
「君が将来、病院の中でどんな血球になるのか、楽しみにしているよ!」
「そんな、幹細胞じゃないんですから…」
「よく勉強してるね、ハハハ…」
鮫島は笑いながら去っていった。
その後同村は大通りに出て歩道橋を歩く。夜の新宿、彼の下には何台もの車が列をなす。左車線には車の赤いテールライトがいくつも流れていき、右車線には黄色いヘッドライトがいくつも流れてくる。
同村は立ち止まり、その光景をしばし眺めた。
「まるで…赤血球と白血球だ」
彼は呟く。
「そうだ、幹細胞…幹細胞なんだよ、俺も…井沢も」
鮫島にレポートを誉められたこともあり、心の奥底からまた元気が湧いてくる。
「よ〜し、帰ってレポート頑張ろう。感想ももちろん書くぞ〜うおお〜!!」
そう1人で叫ぶと同村は駅に向かって走り出した。
この大都会にはいくつもの血球が泳いでいる。それぞれの能力とそれぞれの役割を担って。しかし忘れてはならない。それらはみな同じものから生まれたのだ。
3
翌朝金曜日、14班は6人ばっちり学生ロビーに集合した。
同村の第一声は、「昨日はごめん、井沢」。井沢も「いや、俺も言い過ぎた、ごめんな」と笑った。
「井沢、今度レポートのデータのまとめ方、教えてくれよ。どうも数値を整理するの苦手でさあ」
「いいよ。じゃあ代わりに俺に面白い推理小説教えてくんない?」
そんな2人のやりとりを見ながら、長と美唄は目配せして微笑む。
「では、行きましょうか!」
と、まりかが歩き出す。みんなもそれに合わせて歩き出した。
「ところで感想コーナーはまた書いたの?同村くん」
と、向島。「もちろんです」と同村は元気に答える。
「さすがだね〜同村。でも、昨日俺も幹細胞の図で面白い発見したんだよ」
井沢が得意気に言った。
「マジ?実は俺も昨日夜の歩道橋で面白い発見をしたんだ」
「じゃあ、今日もお昼はクイズ大会ね!あ、そうだ、もし時間あったらキーヤンカレーに行こうよ」
と、美唄も大はしゃぎ。
まあ何はともあれ、一応めでたしめでたし…かな?
今日も頑張ってくれたまえ、幹細胞諸君!
7月、耳鼻咽喉科編に続く!