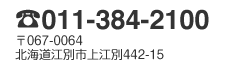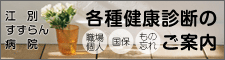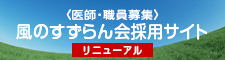- ホーム(法人トップ) >
- 江別すずらん病院 >
- コラム >
- コラム2015年02月「★連載小説★Medical Wars 第11話」
コラム
コラム2015年02月「★連載小説★Medical Wars 第11話」
Medical Wars (福場将太・著)
*この小説はフィクションです。
■第11話「中途半端な最終戦争」
1
秋月まりか留年決定の噂は瞬く間に同級生たちへ、ひいては学内全土へと広まっていった。まったくどこから漏れたのか…尾ひれに背びれに胸びれまでついた悪評は、今日も無責任に医学生たちの間を泳ぎ回っている。それはもちろん14班メンバーの耳にも飛び込んできた。
同村はあの夜偶然立ち聞きしてしまったことを誰にも話さなかった。確かなことが何もわからないのに何かを言うべきではない…無口な男が決め込んだ沈黙はまさに鋼の強度を誇る。
2月第3週。個人戦だった神経内科の二週目も無事通過し、14班はまた新たな科での実習に臨んでいた。朝の学生ロビー集合、医局での実習説明、指導医に連れ立っての診療見学…これまでと何も変わらないポリクリの日々だ。ただひとつ、まりかがいないことを除いては。
沈黙を守りながらも同村は待っていた…彼女からの連絡を。彼だけではない。井沢、長、向島、そして美唄…誰もがまりかの言葉を待っていた。しかし、一身上の都合でしばらく実習に出られないという簡単なメールが届いたきり、班長は音信を絶っていた。そしてそんな毎日についにしびれを切らし、望まずも出番が回ってきた副班長が動き出す。彼はまず班員に緊急招集をかけた。
*
水曜日実習後の午後6時、場所はすずらん医大病院から少し離れたファミレス。夕食の頃合いではあったがコーヒー以外を注文する者はいない。長もそれを見越しての店の選択だったのだろう。それにまりか不在となってからキーヤンカレーからは自然と足が遠のいていた。
「一体何がどうなってるのかわからないけど…このままじゃいけない気がするんだ」
飲み物が来るのも待たずに長がそう切り出す。
「いろんな噂が飛び交ってるけど、秋月さんに何が起こってるんだ?どうしてポリクリに来ないんだよ」
誰も何も答えない。副班長は美唄を見たが、彼女も不安な瞳で俯いているだけだった。やがて向島が口を開く。
「なんか病院で問題になるようなことをしたっていう噂は聞いたよ。それで謹慎処分になったってことだけど…どこまで本当なのかな」
続いて井沢が言う。
「俺も同学年とか先輩とかに訊いてみたんですけど…どれが事実なのかわからなくて。秋月さんが患者に色目を使ったとか、手を出したとか勝手な話まであって、聞いてて腹が立ちました」
…またしても沈黙。店員がトレイを運んできたが、その雰囲気を察して人数分のカップを置くとすぐに退散した。
「同村…何か知ってるんじゃないのか?」
一口だけ飲んで長がやや厳しい声で尋ねる。視線が集まった男はそれでも黙っていたが、美唄の「同村くん、ちゃんと答えて」の言葉に顔を挙げる。
「遠藤さん…」
「何かを隠してるのは私にもわかるよ。多分まりかちゃんのために黙ってるんだろうけど…ここにいるのはみんな仲間でしょ?実は私も知ってることがあるから先に話すね」
そこで彼女もコーヒーに口をつける。
「まりかちゃんとは秘密にするって約束したけど、みんなになら…きっと許してくれると思うから」
「ポリクリに来ない理由を知ってるの?」
井沢が訊く。美唄は首を振り、「でもきっと関係あることだと思う」と返した。秘密を打ち明けることの辛さと大切さは誰より知っている彼女。親友のためにあの日まりかから相談されたアカシアという後輩のことを打ち明けた。そしてまりかが苦悩の末に彼との外出を決断したということも。一同はただ黙ってそれを聞いていた。
「実は…」
美唄の決意に押されるように続いて同村が口を開く。そしてあの夜学務課の前で立ち聞きしたことを語った。一緒に外出した先で酔っ払いにからまれ後輩を怪我させてしまったこと、後輩が入院中の患者であったため大きな問題になっていること、そして処分としてまりかの留年が確定的だということ…。今度は一同もその瞳に驚きの色を浮かべてそれを聞く。
「ごめん…言い出せなくて」
そう締めくくった彼に、長は深く頷きながら言った。
「いや、その内容ならためらっても仕方ないさ。秋月さんの人生に関わることだ。同村のことだから、秋月さんのプライドとかにも配慮したんだろ」
続いて向島が言う。
「大丈夫、同村くんは何も悪くないよ。それより問題は秋月さんだ。そういう状況になってるんなら、早く手を打たないと本当にまずいよ」
美唄が「手を打つってどういうことですか?」と問う。
「このまま何もしないと、本当に留年になっちゃうってことさ。うちの大学は留年が日常茶飯事、簡単に決定しちゃうと思うよ」
「向島さんの言うとおりだ。一度決定しちゃうとそれを覆すのはかなり難しいぞ」
と、長。そこで同村が学内で署名運動をする策を提案したが井沢が却下する。
「無理だ同村。一体どれだけの奴が協力してくれると思う?秋月さんは部活も入ってないし、友達が多いタイプじゃないし…。それ以前に特待生がついに留年だって喜んでる連中までいるんだぜ。…最低だよな」
苦々しく言う彼に同村が「喜ぶ?どうして?」と尋ねる。
「そりゃみんな自分のことを考えてるからさ。5年進級試験で留年するのは毎年五人前後…秋月さんは学年トップだから、いなくなれば確実に進級の枠がひとつ増えるってことだ」
「そんな!」
「すっかり…そういうふうに考える癖がついちゃったんだ、みんな。自分の下に何人いるか、そんなことばっかり考えて勉強してる。まあ…この班になれなかったら俺もそうだっただろうけど」
爽やか青年はそこでコーヒーを一口飲む。
「俺、この14班になって本当によかったと思ってる。正直に白状しちゃうと、最初はハズレ班だと思ってたんだ。この一年、まあ無難につき合おうかなって。
でもこの班のおかげで…いつか同村に言われたけど、自分で考えるってことをしなくなってることに気付いた。自分には欠けている点がたくさんあるんだなってわかったんだ」
「それは俺もだよ、井沢」
同村が静かに言った。井沢はそっと微笑んで続ける。
「俺、今まで色々な人にいい顔して気に入られて…それで勝ち組だ、うまくやれてるんだって思ってた。でも同村の小説とか、向島さんの音楽とか…みんな自分の好きな物の話をしてる時すっごく幸せそうだった。なんて言うか…勝ちとか負けとかばっかり考えてた自分がしょうもなくて…俺もみんなみたいに幸せな顔したいなって」
「私も…14班、大好きよ」
続いて美唄が言う。
「あのゲームセンターから始まって、色んな科を回って、実習して勉強して…」
彼女は指折りいくつもの場面を挙げた。産婦人科ではなかなか出産に立ち会えなかったこと、外科では初めての手術見学に戸惑ったこと、緩和ケア病棟では余命少ない患者に出会って生きる意味を考えたこと、精神科では心の解釈をみんなで議論したこと、九十九里の病院ではいつも怒っていたおじいさんが微笑む瞬間を見たこと、クリスマス・イブに現れたサンタクロースのこと、そして何度も通ったキーヤンカレーのこと…。それを聞きながら、導かれるように誰もが同じ記憶を持ち寄っていた。
「私、この一年間想い出ばっかり。私の病気のこともみんな優しく受け止めてくれて…こうしてやってこれたのもみんながたくさんたくさん助けてくれたおかげだもん」
そこで得意の笑顔を100パーセント。
「みんな、本当にありがとう。私、この班で本当によかった」
「俺も…自分がどれだけ身勝手で、思い上がってたかがわかったよ。大学に入って、こんなに楽しい一年はなかった」
同村もそう言って微笑む。そうだね、君にとってこの一年はまさに青春だったと思うよ。可愛い彼女もできたことだし…いや、こりゃ失敬。
続いて浪人生のボスも言う。
「俺も…みんなに感謝してる。こんなオッサンを仲間に入れてくれて。この一念なんか若返ったっていうか…青春再びって感じ?」
あんたも青春ですか。そして生涯青春のミュージシャンも口を開く。
「僕も…先輩なのに迷惑かけてごめん。気を遣わずに過ごせたのはみんなのおかげだよ」
美唄が「もっと気を遣ってほしかったかな〜」とツッコミを入れ、その場に笑いが起こる。それがおさまったところで、彼女がポツリと言った。
「まりかちゃんも、きっとそうだよ」
みんな真剣な顔に戻る。
「まりかちゃんも、きっと14班大好きだと思うよ。だって今まであんな楽しそうなまりかちゃん見たことなかったもん」
「そうだな…」
と、同村。
「秋月さん、本当にみんなのためによくしてくれたよな。集合時間の連絡とか、医局や学務課とのやりとりとか…絶対手抜きしなかった。口頭試問の前だって、みんなに色々教えてくれたし」
「本当に最高の班長だったよなあ…」
長もしみじみと言う。
「それに一日も休まなかったし、患者さんへの対応もいつも丁寧だった。実習もレポートも…誰よりも真面目にやってた」
そこまで聞いて同村ははっとしたように「そうですよ、それなのにどうして留年とかいう話になるんですか」と投げかける。井沢が返した。
「そりゃ責任の問題じゃないか?秋月さんが患者を連れ出して怪我させちまったのは事実なんだから」
「でもそれは医学生としてやったわけじゃない、高校時代の後輩と出掛けて…たまたまトラブルに巻き込まれただけだぞ。後輩にたいした怪我もなかったし、遊びに行った先でトラブルに巻き込まれるなんてよくあることじゃないか」
今度は長が反論する。
「そんなに簡単じゃないだろ、同村。怪我が少なかったのはあくまで偶然で、もしかしたらもっと大変なことになってたかもしれない」
「でもそんなこと言ったら、公園に酔っ払いが現れたのだって偶然じゃないですか。予想できるはずない。そいつが現れなければ、何の問題もなかったわけですよね?」
「それはそうだけど、結果は結果だ」
「そんな…」
釈然としていない男に井沢が「だからな」と説明する。
「結局、立場の問題なんだよ。例えばその後輩くんがただの友達と散歩してて同じ目に遭ったならそれは単なる事故さ。でも一緒にいたのがよりによって入院してる病院の医学生だったから責任が生じてくるんだ」
「そんな…秋月さんはただの友達として出掛けたんだろ?誘ったのも相手だし、その日は日曜で別にポリクリしてたわけじゃない」
「そんなのわかってる。でも、立場がある」
「立場って…じゃあ何か?医学生の俺たちは全員もう二度とただの友達として行動できないのか?」
少し興奮している彼を長がなだめた。
「落ち着け、今回は…明石くんがうちに入院中の患者だったからまずかったんだ。運が悪かったんだよ」
唇を噛む同村。美唄が言った。
「私、まりかちゃんがどれだけ悩んで明石くんと出掛けることを決めたか知ってる。それに明石くんだって…すっごく悩んだと思うよ。そんなことしたら迷惑かけちゃうかもしれないって」
彼女の語調が強まる。
「それでも勇気出して誘って、まりかちゃんも一生懸命それに応えたんだよ。お互い患者とか医学生とかそんな立場を乗り越えて…」
頷いてから長はゆっくりと言う。
「でもね美唄ちゃん、いくら本人たちがそうでも、立場ってのは消えるもんじゃない。何か起これば責任は生じる。医学生が患者を怪我させた以上、大学は責任を示さないわけにはいかないのさ」
同村が何か言いかけたが、その隙を与えずに副班長は続ける。
「だから秋月さんを留年にして、それで体面を整えようとしてるんだ。理不尽だけど…社会ってそういうものだよ」
その言葉は重く響いた。同村も開きかけた口を閉ざし、場に沈黙が訪れる。しばらく無言でカップに口をつけた後、井沢が空気を和ませるように言った。
「でもさ…まだ絶対留年って決まったわけじゃないんだろ?謹慎だけで戻ってくる可能性もあるんじゃない?」
誰も何も言わない。ただポツリと向島が「そうだね」と呟いた。
その後コーヒーをおかわりしてもう一度議論を交わしたが…大学、病院、医学生、患者、立場、責任…と同じ単語がくり返されただけで何も生まれることはなく、その場は散会となった。
*
帰りの地下鉄で二人になり、美唄が言った。
「…私、やっぱりまりかちゃんと進級したい。一緒に卒業したいよ」
隣で黙って頷く同村。
「まりかちゃんね、何度も助けてくれたの。字が小さい資料を拡大コピーするのとか、一緒に残って読んでくれたりとか…。私、恩返ししたいよ。友達だもん、何とかしてあげたいよ!」
「そうだね…」
彼は考えていた。友情…もちろんそれは大切なものだがその理屈では大学を説得することはできないだろう。あの日二人は医学生と患者ではなくあくまで友達だった、という理屈と同じことだ。そんな感情論では長や井沢の言う責任論に太刀打ちできない。
もしかしたら留年という処分は正しいのかもしれない…とそんな気さえしてくる。まりかもそれを受け入れているのかもしれない。だとしたら…。
「ねえ同村くん、どうすればいいかな?」
二つの大きな瞳に見つめられながら、彼は無言を返すしかなかった。
2
翌日木曜日の昼休憩。同村と向島は久しぶりにアウトローチームを結成し学務課のドアを叩いた。
「君たちが来てもしょうがない話ですよ」
用件がまりかのことだとわかると、喜多村はそう突っぱねた。
「それより実習はどうしました、ちゃんと戻ってください」
「今は空き時間です」
同村が答える。昨夜弱気になりかけたが、美唄の情熱も会って心は再び奮起していた。
「それより、秋月さんがこのまま留年になるなんてこと…俺たち納得できません」
「しかしね、彼女が患者さんを傷つけてしまった以上、責任を取らされるのは社会のルールですよ。大学としても患者さんと家族に誠意を見せなくちゃいけませんしね」
「外出に誘ったのは患者本人です」
今度は向島が言った。
「秋月さんはそれに応じただけです。患者も、そしておそらくは家族も…罰を与えることなんて望んでいないと思いますが?」
「例えそうでも、大学は誠意を示さなくてはならないんです」
「誰も望んでいない誠意に何の意味があるんですか?」
強気に出る同村。これまで医学部に対して溜め込んできた不満を今はパワーに変えている。
「君たちみたいにいい歳して学生やってるとわからないかもしれませんが、世の中とはそういうもの。失敗の責任は取らされて当然です」
「失敗ですか?」
と、同村。
「そうです。残念ながら彼女は失敗した…間違えたんです、判断を」
「じゃあ秋月さんはどうすれば正解だったんですか?」
向島が問う。
「後輩からの誘いを無下に断るべきだったんですか?」
「怪我をさせるよりは…その方がずっとよいでしょう」
メガネの奥の瞳に冷淡の色を浮かべて喜多村は事務的に答える。同村が一歩前に出た。
「でもそれは結果論で…」
「結果に責任が伴うのは当然です。いい加減大人になりなさい」
「本当に留年になるんですか?」
「それは上の人たちが考えてますけど…そんなこと君たちには関係ないでしょう。それに一年留年したからって何です?秋月さんなら来年ちゃんと進級するでしょう。まったく…医学生ってのはプライドばかり高くて挫折に弱過ぎる」
どうやらこちらもこれまで医学生に対して蓄積していたストレスが口をついて出ているようだ。
「何年か前にも留年したからって自殺騒ぎを起こした学生がいましたよ、本当に馬鹿げてる。君たちもこんなことしてる暇があったらちゃんと勉強してくださいね。そうそう、ポリクリ発表会も明後日でしょう、準備は大丈夫ですか?」
「どうせ誰も聞いてない茶番の発表会じゃないですか」
苛立ってそう言い捨てる同村。…う〜ん、ここまできたか。喜多村は呆れたように嘲笑した。
「それでもみんな医師免許が欲しいんでしょう?同村くん、昨年のような成績では今年の進級は危ないですよ。頑張りなさい」
「今、関係ないでしょう。それより秋月さんは…」
「それと向島くん」
喜多村は同村の言葉を無視して視線を移す。
「君は前期の欠席が多いし、何度も院内で問題を起こしていますね。病室で楽器を演奏したとか…。これ以上やらかすと君も進級できなくなりますよ」
「どうして問題を起こしたら留年なんですか?」
「理由を決めるのは大学です。なんだかんだ言って君たちも医者になりたいんでしょう?だったら大学のルールに従いなさい」
そう面倒臭そうに言うと、彼はカウンターから自分のデスクに戻ってしまう。同村は呼びかけようとしたがそれをやめる。また昨日と同じ、感情論と責任論の平行線になってしまうことは明らかだった。隣を見ると、向島もこれ以上は無駄だと瞳で返す。
…トントン、とその時ドアがノックされた。
「守田です、失礼します」
ああ、どうぞどうぞ」
喜多村が打って変わった笑顔で立ち上がった。入ってきたのは守田、同村の同級生にして1年生の頃からのクラス委員…まあつまり学級委員長のような存在だ。学年代表として頻繁に学務課や教授陣と交流を持ち、大学・学生間の連絡並びに調整役を果たしている。学業でも優秀でいつもまりかの次点の成績だ。それゆえ大学側からも気に入られ、同級生からは「将来は厚生労働省の役人」と揶揄されている。まあ物語の終盤で登場したくらいだから当然今後の展開に絡んでくるのだが…それは読んでのお楽しみ。
「あれ、同村?それに向島さんまで」
守田はカウンター前の二人に気付くと少し驚いたように言った。その出で立ちは黒いジャケットにポマードたっぷりのオールバック。
「同村も学務課に用事か?」
「いや、彼らの用はもう済みました。それより守田くん、君に来てもらったのはポリクリ発表会の段取りについて確認してほしいと思いましてね。教授先生方もたくさんいらっしゃるので抜かりが合ってはいけませんから」
穏やかな口調の喜多村。守田もすっかりお手の物といった具合に「ええ、そうですね」と打ち合わせに応じた。所在なくなった二人はいそいそと学務課を退室する。
「彼…森田くんだっけ」
廊下を少し歩いた所で向島が言った。同村は「ええ」と返す。
「クラス委員だったよね。ああやって学務課と連携してるんだ」
「あいつはやり手ですよ。学生たちの要望を大学側に伝えたり、それを実現する代わりに大学からの条件を学生に呑ませたり…。実際に試験の時に問題用紙を持ち帰ってもよくなったのはあいつのおかげですし」
「なるほどね。じゃあ彼が味方についてくれたら秋月さんのこともなんとかなるかもよ」
それは名案だと一瞬同村も思った。しかし…すぐに思い直して「難しいでしょうね」と返す。守田に限ってではない、ポリクリ発表会や進級試験を控えたこの時期に他人のために協力してくれる奴がいるはずがない。しかも大学に目をつけられるリスクを冒してまで…。
ノート盗難事件以来、彼は医学生たちへの絶望感を禁じ得ない。そんな胸中を察したかのように先輩はポンと彼の肩を叩く。
「まあまあ、何事もやってみなくちゃ始まらないよ」
そんなわけで二人は学務課から出てくる守田を廊下で待ち構えることにした。間もなく姿を見せた彼を捕まえてまりか救済の相談をする…と、さすがの守田は彼女の現状を大学から聞いておおよそ知っているようだった。
「なあ守田、何とかならないかな」
「そうだなあ。気の毒だとは思うけど、これは大学と学生だけの問題じゃないからなあ。ご家族とか病院とかも絡んでるんだろうし…」
はっきりとは言わなかったが、その様子から自分を巻き込まないでくれと思っているのは明らかだった。結局当たり障りない言葉を交わしクラス委員は去っていく。その背中を見送りながら同村が力なく言う。
「やっぱりダメでしたね」
「…世知辛いねえ」
向島はそっと虚空を仰いだ。
さて…現状打破の鍵は一体どこにある?
*
同じ頃、井沢と長は明石の病室を訪ねていた。まりかが謹慎処分を受けたことは大学から聞かされていたらしく、車椅子の青年はまるで子供のように泣きじゃくっている。
「ぼ、僕のせいです。僕が先輩を誘ったりしなければ…う、うう…」
こんなに大泣きされてはまたこれが問題になってしまうかもしれない。井沢は「大丈夫、落ち着いて」と彼をなだめた。
「僕、が、学長先生にも院長先生にも何度も言いました。先輩は何も悪くないって。だから先輩が責任を取ることなんかないって…」
興奮して車椅子から飛び出しそうになる体を長が支える。
「何度も頼みました、でも、みんなこれは大学のけじめだからって。う、うう…僕が悪いんだ、全部僕が!」
自分を責め続けている彼に、二人は何も言えなかった。
*
そしてその頃美唄はまりかの携帯電話を鳴らしていた。病院駐車場の片隅、周囲に誰もいない場所。
「出てよ…まりかちゃん」
電話を握る右手に力が入る。そして左手には一枚の写真…それはいつかキーヤンカレーで撮影した六人の集合写真。笑顔全快の美唄、その隣でちょっと照れてピースをするまりか、二人を囲む男連中…誰もが微笑んでいる。
「まりかちゃん…」
しかしその願いも空しく、押し当てた耳に返されるのは無機質なコール音だけだった。
*
同日午後5時の学生ロビー。実習を終えた彼らはいつものソファで土曜日の発表会の準備をしていた。当然身が入るはずもない。本来は班長を中心にこの一年の集大成として盛り上がるはずだったこの作業、今はただ機械的に進めるだけ…ふとするとすぐにその手は止まってしまう。
「みんな集中しようよ…って言っても無理か」
長が力なく言う。昼休憩に行なったそれぞれの戦況報告を聞き、事態はさらに最悪の色を深めていた。どこにも突破口の糸口さえ見当たらない。このまま何をしてよいかもわからず、何もできず…ただまりかに処分が下されるのを待つしかないのか。
もちろんたかが留年。命を奪われるわけではない。最悪もう一回5年生をやるというだけの話だ。それでも成績トップで実習に誰より心血を注いでいた彼女が人生に足止めを食らうことに…やはりやりきれなさは大きい。
美唄が暗い声で言った。
「いつかまりかちゃん言ってたよね。お医者さんになったら本当はオールラウンド研修なんかより、早く神経内科に進みたいって。もしかしたらあれも…明石くんのことがあってだったのかもしれない」
進行性の病を抱える者にとって同じ一年でもその重みが違う。それは美唄自身も誰より感じているところだ。そしてそんな患者を治療しようとする医者にとっても…それは同じなのかもしれない。
「すごく泣いてたな…明石くん」
井沢が呟く。長も黙って頷いた。
「まりかちゃんだけじゃないよ。このままだと明石くんもダメになっちゃう。このままじゃ自分の病気を恨んで、もう幸せになろうとか、人を好きになろうとかできなくなっちゃうよ」
そう言った美唄の顔を見て同村は思う。彼女も一度はそんな孤独を覚悟しようとしていたのかもしれないな、と。
だがどうする…このままじゃいけないとは思うが、一体何をどうすればいいんだ?まりかのため、あるいは明石のために大学に直訴するか?でもそれでは結局個人的な感情論、ただの私闘だ。誰も味方にはつかないし大学も相手にしないだろう。
それに…とさらに同村は考えを巡らせる。
二人を思うとやりきれないのはもちろんだが、それ以上に何かが間違っている気がする。今回の出来事にはそのままにしてはいけない大切な問題が含まれている気がする。それが果たして何なのか…わかりそうでわからない。それはずっと感じてきたもので、今もすぐそこにあるもののはずなのに!
頭を抱えてしまう主人公、その隣でいつも達観した眼差しの向島も視線を落として黙り込んでいる。頼む天才、何か思いついてくれ!
五人は二時間ほどその場にいたが、結局作業は完了せず残りはまた明日やることとなった。
*
アパートの部屋に帰りつき、夕食もそこそこに同村はいつもの机に向かう。試験勉強もしなくてはならないのだがこれも手につきそうにない。趣味の執筆でもするかとパソコンの電源を入れてみるが…これも言わずもがなだ。溜め息をついてふと正面の壁を見ると、そこには14班六人の名前と役割を記した紙が貼ってある。そう、初めて集まったあの日の夜に作った物だ。
「まさか、最後の最後でこんなことになるなんて…」
と、独り言。彼の頭の中で再びこの一年の記憶がリプレイする。やがてそれはこの一年に留まらず、入学してからの様々な場面に広がっていく。そしてその都度感じた理不尽や葛藤、矛盾や希望が蘇ってくる。
彼は無意識にパソコンの中の文書データを開いていた。そう、それはポリクリで各科を回りながら作成してきたレポートたち。誉められたり怒られたりしながらそれでも貫いた『乾燥のコーナー』も含まれている。彼はそこに記されたその時その時の自分の想いを読み返していった。
人が生きていく中で最も難しいことはその時の心を留め置くことだろう。どんなに望んでも感情や感覚を保管することはできず、時の流れの中で心は自ずと変化していく。それでもそれを文字にしてしたためることで、ほんの少しだけ思い出すことができる…その時大切だと感じたことを、正しいと考えたことを。
彼は探していた…医学部に入ってから今日までの日々の中に、今目の前の道を示してくれる手掛かりが必ずあるはずだと。夜が更けていくのも忘れ、彼は何度も何度も自分の心を読み返していった。
3
明けて金曜日、同村はポリクリを休んだ。幸い今週回っている科の口頭試問は昨日終わっているため休んでも単位はもらえたのだが…考えてみれば彼の欠席はいつかお湯をかぶって熱傷を負った時以来だった。無口な男の無言の欠席を気にかけながらも四人となった14班はとりあえず実習をこなした。そして夕方からは昨日の続きで発表会の準備作業。完成したのはまあ無難な内容で、他の多くの班と同様棒読みしてやり過ごせるような代物だった。みんなお疲れ様、と長が労いの言葉を発する。
「一応できたな。まあこれで明日の本番も何とかなるでしょ。今日は同村もいないから、明日は少し早く集まって最終確認しよう」
「そうっすね。日本語がおかしくないかのチェックも明日文芸部にお願いしましょう」
井沢がそう言うと美唄と向島も力なく笑う。では帰りますかと全員立ち上がったところで…、学生ロビーの入り口からあの男が飛び込んできた。
「みんな、今日はごめん」
「ちょっと同村くん、遅刻…っていうかもうとっくに終わってるよ」
美唄がツッコミを入れるが彼は気にせず言葉を続ける。
「実は…ずっと考えてたんだけど。今回の秋月さんのこと、もしかしたら何とかできるかもしれない」
当然驚きの視線が息を切らした男に集まる。同村はみんなを4階の教室に有同した。明日の発表会にも使われる5年生用のその部屋にはこの時刻誰もいない。
「おい同村、今日お前そのことを考えてて休んだのか?」
到着するや井沢が言う。
「ああそうだ。それでわかったんだよ、今俺たちは何をするべきなのか」
「まりかちゃんを助けてあげられるの?」
すがるような眼差しを向ける美唄。彼は「もしかしたら」と答えた。
「どういうことなんだい?説明してよ」
向島も言う。そこで同村は全員に着席を促し一人正面に立って説明を始めた。医学部に来てから抱いてきた様々な想い、一晩中振り返った自分の心…そこから導いた今すべきことの答え。そしてそれを実現するアイデアをも彼は示してみせる。
黙ってそれを聞きながら、みんな改めてこの男の特性を思い知った。誰もがそういうものだと当たり前に通り過ぎる場所にその都度足を止め考え込む。わずらわしく不器用な生き方だが、時としてそれが見過ごしてはいけない大切な物を掴み取るのだ。同村はそんな大切な物を守るための突拍子もない手段を提示し、最後は「みんな、協力してくれ」と締めくくった。
しかし流れるのは沈黙…誰もすぐには何も返さない。まあ無理もないだろう。彼の論理は間違ってはいないが、それを通すにはかなりのリスクを覚悟しなくてはならないからだ。
「いくらなんでも…無茶だろ」
最初に発言したのは井沢だった。
「それをやろうと思ったら、今から大急ぎで準備しなくちゃいけないんだぞ」
同村は頷き、しかしみんなでやれば間に合うと言い切った。
「だとしてもさ…協力したいけど、さすがに勝算がなさ過ぎないか?いや、同村がすっごく考えたのはわかるよ。正直その通りだなって感動した。でも、下手したら秋月さんを救うどころか俺たち全員留年だぞ」
「これは俺たちのための戦いでもあるんだぞ」
そう返した同村に今度は長が言う。
「わかるよ同村。でもみんなそれぞれ事情がある。正しいからってそれをやれるわけじゃない。俺だって…やっぱり自分の人生が大切だ」
「長さん…」
悲しい声で言った同村に、向島が口を開いた。
「同村くんは本当にこの作戦やる気でいるの?君だって留年処分になるかもしれない。本当にそんなリスク冒せるのかい?それに…」
彼はちらと音楽部後輩を見る。それで同村も察した。もしみんな留年なんてことになれば、彼女の視力もその一年間でさらに低下してしまう。もしかしたら卒業試験や国家試験に辿り着けなくなってしまう可能性だってある。
美唄はずっと黙っていた。彼女の人生を考えた時、余計な足踏みをさせるわけにはいかないことは同村にもわかっている。
「そうですね…強制はできません。希望者参加、ということにしましょう」
その言葉を最後に再び沈黙が訪れる。やがてゆっくりと腰を上げたのは長だった。
「ごめん…俺には無理だ」
そう言って申し訳なさそうに教室を出ていく。井沢もごめんとだけ呟き彼に続く。二人が退室するとドアの閉まる音が広い室内に悲しく響いた。
取り残されたのは三人。昨年春、偶然によってこの場所に集結した彼ら。少しずつ絆を深めながらやがてそれは奇跡の色にも染まってきたのだが…やはり偶然以上には届かないのか。
次は美唄が無言で席を立つ。同村はただ退室する彼女を黙って見送った。
…また一人減り、残された二人にはさらに重い沈黙がのしかかる。
*
教室を出た遠藤美唄はそのまま会談を上り教育棟の屋上に出た。もう日も落ちて辺りは十分に暗い。手探りでその中央まで進み夜空を見上げる…大きな二つの瞳に星は映らない。そこで彼女は汚れた東京の空気を胸いっぱいに吸い込んだ。
「ワン、ツー、スリー、フォー!」
そう言ってステップを踏み、遠藤美唄は歌い出す。進行する障害を抱えながら自分は医者になるのか?その命題に答えを見つけたあの日、初めて作ったオリジナル曲だ。誰もいない闇のステージに歌声はどんどん強さを増しながら響き渡っていく。祈るように、嘆くように、彼女はコンサートを続けた。
*
「僕は…協力するよ」
やがて向島が静かに言った。そこには穏やかな眼差しがある。
「…ありがとうございます」
優しく返す同村。そしてその瞬間、「ジャジャーン!」という明るい声とともにドアが開かれた。二人が驚いてそちらを見ると、そこには…。
「遠藤さん!」
「私も、やる」
ガッツポーズで美唄は言った。
「私もやるよ、同村くん、MJさん!」
そして100パーセントの笑顔が炸裂。
「たくさん助けてもらったのに、まりかちゃんを置いて前になんか進めないもん!大丈夫、絶対うまくいくから」
本当に君って子は…同村はまた心の中で抱きしめてしまう。それを知ってか知らずか、美唄はおどけて言った。
「もしお医者さんになれなかったら同村くん、責任取ってもらうからね」
「え?え、え〜と…」
赤くなる男を笑い、その場に僅かだが明るさが灯る。向島がパンと手を叩いて立ち上がった。
「よしじゃあさっそく作戦会議開始!」
こうして、小さな反乱軍は集結した。
*
同日午後7時。バイクを走らせ自宅に戻った長は両親と夕食を囲みながら考えていた。何年も好き勝手してようやく医学部に入った自分。それを支えてくれた年老いた両親。一刻も早く医者になって安心させてやりたい、楽させてやりたい、その気持ちでこの5年間頑張ってきたのだ。それを棒に振ることは…できない。
「実習の方はどうなんだい?」「実際に患者さんと触れ合うんだから大変よねえ」などとかけられる言葉に笑顔で答えながら長は会話を弾ませる。
「まあでもお前がお医者になろうとはねえ…しかもちゃんと勉強して来年は6年生なんだもんねえ。驚いちゃうわ」
母が言う。
「自分でもびっくりだよ、本当は一番応援してくれたじいちゃんに医者になった姿を見せたかったけど」
「見守ってくれてるだろう」
と、父。
「それに親父はよく言ってた。ゆっくりでもまっすぐ進めってな。猛はたくさん回り道をしてたから心配だったけど、やっと道を見つけたんだからな」
あとはじっくり歩いたらいい、と付け加えて父は熱燗を希望する。仲の良い夫婦は明るい会話を交わし、妻はその用意に立った。
「まあお前はどんなに回り道してもグレなかったしな。だから安心してるよ。これからもまっすぐ行きなさい」
まるで事情を知ってるかのように言い、父はテレビを見て笑い出す。やがてご所望の品も運ばれてくる。そうじゃよ、と仏壇からも聞こえた気がして長はそっと微笑んだ。
*
同じ頃、井沢もマンションの自室で考えていた。改めて感じさせられた自分の臆病さ、そして平凡さ。いつか幹細胞の分化の図を見て思った…けして医者になることが決まって生まれてきたわけじゃない、自分は自由なんだと。それなのに…人生を賭ける勇気がなければ結局は不自由と同じだ。
電話が鳴る。力なく受話器を取ると…父親だった。
「元気にしているか?5年生ももうじき終わりだが…進級試験の勉強はどうだ?」
「はい、大丈夫です」
「そうか、まあ心配はしとらんがな」
その力強い声に自然と背筋が正される。
「実は知り合いの病院の先生がな、卒業したらお前を預かりたいって言ってくれてるんだ。ほら、オールラウンド研修で。優秀な先生だし、実家の病院を継ぐ前に腕を磨くにはちょうどいいと思ってな」
そんな話に生返事をしていると疲れているのかと尋ねられる。
「いや、そんなことないですけど…あの、一つ相談していいですか?」
「どうしたんだ、改まって」
「あの、もし俺が医者になれなかったら…どうします?」
返される沈黙。それはことごとく期待に応えて生きてきた息子が初めて親に投げかけた疑問だった。やがて電話の向こうの声が言う。
「大輝、何があったのかはあえて聞かないが…これだけは言っておく。医者ってのはな、なれるとかなれないとかじゃないんだ。ましてやならされるものでは決してない」
「…はい」
「なるのかならないのかだ、それを忘れるなよ」
人生の、そして医学者としての大先輩の言葉。井沢は「わかりました」と微笑んだ。
*
同日午後9時、教育棟4階の教室では三人が作業を続けていた。同村のアイデアを実現するための方法を、作戦を、演出を…何度も試行錯誤していく。それは細い細い綱渡りだったが…「うん、それいけるよ!」「やっぱMJさん天才!」などの美唄の明るさが小さな可能性を拾い集めていく。頼りない希望を繋ぎ合わせていく。
「それにしても腹減ったなあ、キーヤンカレーでも買ってくる?」
「ダメですよMJさん。それはまりかちゃんが復活してからみんなで行くんだから」
「それにもう閉店時刻ですって…じゃあコンビニでも行ってきます?」
同村がそう言った時、「それには及びませんぜ」と入り口のドアが開く。
「井沢くん!」
美唄が嬉しそうに言う。恥ずかしそうに鼻を擦りながら、爽やか青年は買ってきた差し入れを示した。
「俺も一緒に戦うよ、同村」
「ありがとう、心強いよ」
そこで小休止してお菓子や飲み物を広げていると、再びドアが開かれる。その音は明るく室内に響く。現れたのはもちろん…。
「みんな、ごめん」
「いえいえ副班長、来てくれると思ってましたよ」
現れた長に井沢が言う。美唄も嬉しそうに声をかけるが、彼は部屋に入らずにその場で言葉を続けた。
「遅れたお詫びと言っちゃなんだけど、連れてきたよ」
そこで長に導かれ、目を伏せがちに彼女が姿を現す。
「まりかちゃん!」
美唄が駆け出し、相手を突き飛ばすかのような勢いで抱きついた。
「まりかちゃん、まりかちゃん…」
「ごめんね心配かけて…」
今にも泣きそうな親友に彼女は優しく返す。
「長さんから…話は聞いたの。何にも言わずに部屋に篭ってるのは班長失格だって怒られちゃって…」
「長さん、なに班長をいじめてんですか!」
井沢がおどけてツッコむ。大きな功績を果たした副班長は苦笑い。
「長さんからね、同村くんの作戦も聞いたの。でも、本当にみんなそんなこと…」
不安そうなまりかに一歩歩み寄って主人公が言った。
「俺たちはやるよ、自分たちのためにね」
美唄もまりかの肩に埋めていた顔を上げて言う。
「そうだよ。まりかちゃんがダメって言っても私たちやるからね!」
班長はもう何も言わずに頷く。きっと長からすでに色々説得されてきたのだろう。そこで向島が「ところで秋月さん、もしかしてバイクで来たの?」と尋ねる。
「はい…長さんの後ろに。バイクなんて初めて乗りました」
「うわ〜、そのタンデムかなり面白い」
美唄が言うとその場に笑いが起こる。同村が何故か拍手を始め、みんなも自然にそれに続く。
「じゃあ全員集合したところで、あれをいきますか。遠藤さんよろしく!」
「任せて同村くん!」
と、輪の中心に歩み出る美唄。
「じゃあみんな、明日は頑張るぞー!エイエイオー!」
「エイエイオー!」
六つの拳が振り上げられる。そして美唄の手にはラブちゃん…。採集戦争前夜、聳え立つ病院の隣の小さな一室で、最後の奇跡に火が着こうとしていた。
かくして最強の布陣を敷いた反乱軍。自分たちのため、そして医学部のために頑張ってくれたまえ、14班諸君!健闘を祈る!
4
そして迎えた当日土曜日。午前10時、ポリクリ発表会の前に図書室で自習していた守田の所に美唄がひょっこり現れた。
「ああいたいた、守田くん!」
彼はペンを止め、「遠藤さんどうしたの?」と振り返る。
「あのね、守田くんにお願いがあるの」
「…何かな?」
「今日の発表会なんだけど、14班を一番最後にしてくれないかな?」
怪訝な顔をする彼に美唄は笑顔でそう告げた。
「え、順番を?でももうプログラムは学務課に渡してあるからなあ。一体どうして?」
「ちょっと長引いちゃうかもしれないから」
「でも時間オーバーすると減点になっちゃうよ?」
「わかった、気を付けるね。だからお願い!」
美唄は両手を合わせて頼む。困った顔のクラス委員。そこで彼女はポケットから秘密兵器を取り出した。守田の顔色が変わる。
「お願い、協力してほしいの」
*
いよいよ午後1時から教育棟4階の教室でポリクリ発表会が始まった。2週間前と同じく前列には各科の教授陣が並ぶ。そして相変わらず発表者以外の学生たちは後ろの席で試験勉強に向かっている。棒読みの説明の後は予定調和の質疑応答、そんな不毛な発表がくり返された後、ついに彼らの順番が巡ってくる。守田のおかげで出番は大トリ、白衣姿の五人は正面に出ると、まるで何かの授賞式のように横一列に並んだ。それはちょうど教授陣と対面する形になる。そして美唄が合図すると廊下から同じく白衣姿のまりかが入ってきて列に加わった。
「ちょっと、どういうことですか」
脇に控えていた喜多村が立ち上がる。久しぶりの特待生の姿に学生たちもざわめき始めた。そんな中同村が切り出す。
「発表を始める前に先生方にお願いがあります」
一斉に教授たちの視線が集まるが彼はひるまない。
「どうか六人全員でこの場に参加させてください。現在秋月さんは事情で謹慎となっていますが…僕たちはこの一年、この六人で実習を回ったんです。どうか班員全員で発表させてください、お願いします」
そこで六人同時に「お願いします」と頭を下げる。このおじぎ合わせもポリクリの賜物かな?
「ちょっと君たち、勝手なことはやめなさい」
焦った喜多村が駆け寄るが、彼らは頭を下げたまま動かない。
「どうか、お願いします」
学生たちのざわめきもさらに大きくなる。前列中央に座った人物が落ち着いた声で言った。
「まあまあ喜多村さん、せっかくの発表会ですから」
それは満を持しての再登場、耳鼻咽喉科の瀬山教授!学生たちの命運を握る閻魔…もとい学生部長その人である。その言葉に室内のざわめきもおさまる。
「謹慎といっても…病棟に上がるわけじゃないですし、秋月先生も発表に参加されてよいのではありませんかね。どうです、みなさん?」
左右の教授陣の何人かが頷く。六人は「ありがとうございます」とまた合わせて頭を下げた。不愉快そうに脇に引っ込む喜多村。
「じゃあ…発表をお願いします」
瀬山は微笑むでも怒るでもなく、ただ冷静な瞳でそう言った。同村が「はい」と返すと各自配置につく。まずスクリーン右に同村が立ち、その隣に向島がノートパソコンを操作する形で座る。残る四人はスクリーン左側に立つ。室内はまたにわかにざわめき始めた。
「それでは、始めさせて頂きます」
同村がマイクを持ってそう言い、向島がパソコンを操作するとスクリーンにタイトルが映し出された。
「14班の発表テーマは、『この一年で感じた医学部教育の問題点』です」
さあ…ぶちかましてやれ、戦闘開始だ!
*
「まず基本的なことですが、ここは『すずらん医科大学』、そこで学ぶ僕たちは『医学生』ですよね」
一体こいつら何を考えてんだ…そんな不穏な空気の中、同村が平然と話し始める。スクリーンには『大学とは?』『学生とは?』と表示される。
「高校までの勉強と、大学での勉強は大きく違います。高校までは教科書に書かれた正解をとにかく頭に入れることが勉強…それをするのが『生徒』です。でも大学からは違う、何が正解かを自分で考えなくてはいけない」
これまでいつも無口で特定の友人としか会話も交わさなかった男が、今は壇上に立ち謎の演説をしている…同級生たちにとってはこの構図だけでもかなりのインパクトだったに違いない。
「教科書に書いてあるから正解とは限らない、論文に書いてあるから正解とは限らない。何が正解かを見極める力、自分で正解を見つける力を養う場所が大学です。そしてそれをする者こそが『学生』なのです。すずらん医大も当然大学であり、僕たち医学生は当然学生のはずです。それなのに…」
スクリーンには『医学部の現状』の表示。
「残念ながら自分で学問を探求できる場所とはお世辞にも言いがたい。大学から提示される正解をひたすら勉強するだけ…これでは学生ではなく生徒です。しかも勉強の動悸は医者になることであり、学問への探求心ではない」
スクリーンにはさらに『医大は大学ではない』の文字が加わる。
「医大は大学ではなく実質的に医者養成の専門学校である…これはよく言われていることですよね?まあ自由に探求できるほど医学は簡単な学問ではないというのも理由だとは思いますが、仮にも大学がこれでよいのでしょうか?」
同村はそこで教室内をぐるっと見回した。
「例えばこの発表会だって…何人の学生が真剣にやっていますか?形だけの発表と質疑応答をして、あとはみんな聞かずに試験勉強。これが大学ですか?」
学生たちが慌てて教科書や問題集を隠す音。教授の何人かが振り返った。そして同級生からは当然冷たい視線が注がれる…おいおい同村、君はさらに敵を増やすつもりか?
「まあそれも来月の進級試験のことを考えれば仕方ないですよね。誰だって留年はしたくない。でもそもそも…どうして今年の進級が試験で決まってしまうのでしょう。今年はポリクリの一年なのに、これでは実習よりも問題集を頑張れってことになりませんか?」
一息ついてさらに彼は続ける。
「学問の探求ができない以上、確かに学生の勉学意慾を維持するには進級を狭めて危機感を煽るしかありません。まるで毎年受験戦争です。しかしその結果何が起こっているかわかりますか?それは…人間性の喪失です」
「おい、君!」
さすがに耐えかねた喜多村が声を上げ割り込もうとしたが、瀬山が無言でそれを制する。閻魔は変わらず感情の読めない視線を同村に注ぎ、「続けて」とだけ告げた。
「人間を育てるという意味では…ここは最悪の環境です」
いつしか室内はまた静まり返っている。喜多村だけではない。多くの学生が呆気に取られていた。何たる愚考、何たる暴挙…多くの教授たちを相手に彼は医学部の在り方を説いている。身の程知らずもはなはだしい。
それでも同村は続ける。まるで何かに憑りつかれたかのように。
彼は言った、ただでさえ世間知らずが多いのにこの環境では自分で考える力を失ってしまうと。留年しない秘訣は大多数と同じ勉強をすること、失敗しない秘訣はみんなと同じであること…そればかりを憶えてしまい、個性や人間性がどんどん削がれていくと。入学以降ずっと感じてきた違和感を、苛立ちを、戸惑いを…彼は言葉に変えていく。それがかろうじてでもこの場の雰囲気に許容されたのは、その語りが礼節を守っていたからだろう。
「先生方はご存知ですか?進級のために裏でどんな汚いことが起きているかを。特定の人間にしか試験情報を伝えなかったり、試験資料を隠したり盗んだり…人を救わなくちゃいけない医者が、こんな貧しい心になってよいのでしょうか?」
言葉は無言の医学生たちに、そしてかつて医学生だった教授たちに投げかけられる。そこで向島がパソコンを操作し、スクリーンには『事例検討』と表示された。
「そこで僕たちは考えてみました。この現状を改善するにはどうすればよいのかを。ここからは実際の事例を紹介していきます」
*
「最初の事例はDさん、23歳男性です。彼は父親が歯科医であったことと医学そのものに興味を持ち医学部に来ました。しかし医学部は医者になることを前提とした場所であり、自由に医学を学ぶ場所ではありませんでした。医者になる覚悟なんてしていなかった彼は、5年生になった今も将来を迷い続けています」
スクリーンにはDさんの経歴が表示された。まあDさんの正体については…言うまでもないだろう。そこで同村が井沢にマイクをバトンタッチし、頷いて彼が一歩前に出る。
「続いてIさん、同じく23歳の男性です。彼は両親が医者、従兄弟も叔父さんも親戚も医者だらけでした。しかも父親が産婦人科病院をやっていたため将来は後を継ぐのだと子供の頃から当たり前のように考え、何の疑いもなく医学部に来ました。そして今彼は、自分に欠けている物が多くあることに気付いて戸惑っています」
言い終わると井沢は同村に目配せした。続いて長が登場する。
「Cさんは33歳の男性です。サラリーマン家庭に育った彼は高校卒業後進学も就職もせずブラブラしていましたが、一念発起して28歳で医学部に入りました。動機は両親への恩返しです。早く医者になりたいと考えて5年生にまでなった彼ですが、医者になることの意味を簡単に考え過ぎていたと…最近恥じています」
続いてマイクは美唄に渡る。
「Eさんは24歳の女性です。母親は看護師です。精神病院にいる父親を理解したいという動機で彼女は医学部に来ました。しかし残念ながら彼女にもまた病気がありました」
同村はそこで彼女を心配そうに見る。病気の話はしなくてもいいと伝えたのだが、彼女自身がそれを言わなければ意味がないと押し切ったのだ。美唄はステージの上に立った時のように、堂々と声を発した。
「彼女は医学部に来て強く思いました…自分の病気を学びたい、そしていつか誰かの役に立ちたいと。もし病気のせいで医者になれなかったとしても彼女は医学部に来たことを後悔しないと思います」
そう言い切ると彼女は微笑む。14班の五人も彼女に笑顔を向けた。
言うなれば自己主張の叫び…しかし学生も教授も黙って彼らを見守っている。この斬新で型破りな発表の果てにどんな結論が示されるのかを…。
そしてついにまりかがマイクを手に前に出る。深呼吸すると、「Aさんは…23歳の女性です」とゆっくり語りが始まった。
「高校の時に友人が難病を患い、自分の無力さを痛感して医学部に来ました。そしてひたすら勉強することに集中しました」
多くの同級生にとって、彼女が話すのを聞くこと自体初めてだったかもしれない。いつも教室の最前列で講義を受け続けた伝説の特待生は、今仲間たちに囲まれながら一世一代の告白に臨んでいる。
「でも5年生になり実際に患者さんと触れ合った時、勉強だけじゃ何もできないんだなって思いました。もっともっと、色々な知識も経験も必要なんだなって思いました」
マイクを握る手に力が入る。
「そしてある時、彼女は身体の不自由な友人を連れ出しました。少しでも幸福な時間を作ってあげたかった…それは勉強ばかりしてきた彼女の挑戦でした。でもその結果、友人に怪我を負わせ、精神的にも追い詰めることとなりました。今彼女は改めて自分の浅はかさを感じています」
班長はそう言うと一礼し、同村にマイクを戻した。再び彼が前に出る。
「僕らはこれらの事例を通して考えました。医学生にとって大切なことは何だろうかと…」
その声に勇気が込められていく。
「そしてひとつの結論に達しました。今僕たちに必要なこと、それは…『挑戦』です。それこそが今僕たちに一番欠けている物であり、一番しなくてはいけないことだと気が付きました」
スクリーンにも『挑戦』の文字が大きく表示される。
「医学部は自由に学問を探求できる環境にはありません。それで挑戦することさえしなくなってしまったら、医学生は本当にそこで終わってしまいます。医学に関することでもそうじゃないことでもいい、今必要なのは挑戦です!」
彼は仲間たちを見る。
「Iさんはきっとこれから挑戦することで欠けていた物を取り戻していけるでしょう。Cさんもきっと挑戦することで医者になることの意味を考え直せる」
井沢と長が微笑んだ。
「そしてEさんもきっと、挑戦を続けることで自分の生き方を見つけることができる。必ず…誰かの役に立てる」
美唄も笑って頷く。彼はそこでまた教授に向き直る。
「Dさんも挑戦せずに悩んでいたからダメだった。ちゃんと挑戦すれば、医者になるのかならないのか…その覚悟が決まると思います」
そう告げられた瀬山も、左右の教授たちも何も反応しない。同村はまりかを見た。
「そしてAさんが今回挑戦したことも…とても大切なことだったと思うんです。確かに結果は失敗でした。でも僕たちは彼女の挑戦を…支持します」
そこで向島も立ち上がり、六人は再び一列になる。
「先生方、これが僕たちの結論です。どうか医学生に…挑戦することを許してください」
全員で頭を下げる。そして顔を上げると、同村は「以上です」と締めくくった。
…これが彼の作戦。感情論でも責任論でもなく教育論で勝負する。まりかの挑戦が失敗だったことも認めた上で、それこそが今医学生にとって最も必要なものだと訴える。しかも学生と教授たちが一同に会するこの場所で。湿った枝一本一本には火が着かなくても、まとめてなら燃え上がらせることができる…その可能性に賭けたのだ。
さあ、果たして着火するか?
*
室内に訪れる沈黙。喜多村がそれを見かねたように再び立ち上がって言った。
「発表は終わりですね。それでは席に戻ってくださ…」
「ちょっと待ってください」
瀬山が言った。
「…質疑応答、よいですか?」
同村は「もちろんです」と返す。所在無く着席する喜多村。
「確かに医学部は大学でありながら、学生が学問を探求する場としては不十分ですね。まさにみなさんの言うとおりでしょう。では、具体的にはどのようになればよいと思いますか?」
瀬山の言葉に答えたのは美唄だった。
「お医者さんになりたい人じゃなくても、医学を学びたい人ならみんな学べるような場所だったら素敵だなと思います。自分自身が病気を抱えた人、自分の大切な人が病気を抱えた人、そんな人たちが医学を学ぼうとするのって…おかしくないと思います」
「なるほど。しかし現実には先ほど同村先生が言ったように医学部は医者養成の専門学校であるのが実状ですね」
だからこそ入学した後でなかなか進路変更ができない、不適格な人間でも医者を目指すしかなくなってしまうと瀬山は続けた。
「君たちは…」
別の教授が口を開く。消化器内科の小俣だ。
「発表を聞いていると、君たちは医学生や医者をあまり立派だと思っていないように感じるんだが…その点はどうですか?」
「はい、それはですね」
と、今度は井沢が答える。
「僕も昔は医者は立派だと思ってました。医者になれば立派になれるんだって。でもこの一年色々なことを考えてそれは違うと気付きました」
確かに最も価値観が変わったのは彼かもしれない。医者が立派なわけではなく、大切なのは医者をやっている自分が立派かどうかだと爽やか青年は言った。一年前の彼が今座席にいたとしたら、きっと鼻で笑っていただろう。
小俣は黙って少しだけ頷く。続いて精神科の吉川が口を開いた。
「いやあ…こんな新鮮な発表は初めてですよ。堪能させて頂きました」
相変わらずのバリトンボイス。
「みなさんが結論として挙げた挑戦の大切さですが…それは結果が成功だけでなく失敗の場合も大切という意味ですか?」
「はい、もちろんです」
長が答えた。
「むしろ失敗が必要だと思うんです。僕自身がそうでしたが、失敗しないように失敗しないようにっていつも考えてました。でもポリクリを通して、失敗だと思っていた経験が自分にとってどれだけ武器になっていたかがわかったんです」
同級生より10年も出遅れた浪人生のボス。しかしその経験からくる人生観と包容力は確かに何度も14班の危機を救ってくれた。
「しかしねえ、医療では失敗は許されんよ」
別の教授が言う。そんなやりとりを喜多村はハラハラしながら見つめている。
「だからこそですよ」
同村が口を開く。
「失敗が許されない仕事だからこそ、今失敗しておくことが必要だと思うんです。挑戦して、失敗して、そこから学ぶことが。学生のうちから失敗しない練習をする必要はありません」
そこで眼科の三玉教授が「よく言った若造!」と手を叩いてガハハ笑いをする。さすがに昼から酔っているわけではないだろうが…しかしそのおかげで見守る学生たちにも少しだけ笑いがこぼれた。続いてまた瀬山が言う。
「秋月先生にお訊きしたいのですが」
まりかは「はい」とだけ返す。
「先ほどあなたが挙げられた事例…患者を怪我させてしまった医学生のことですが、大学としては彼女には留年処分が妥当と考えています」
突然の閻魔の宣告。室内に緊張が走る。瀬山はさらに「それについてあなたはどう思いますか?」と問った。同村たちの顔にも不安が浮かぶ。彼女は少し考えてからゆっくりと口を開いた。
「今回のことは…勉強の知識しかない馬鹿な医学生の浅はかな行動だったと思います。ただ浅はかではありますが…けして軽はずみではありませんでした。あの時の彼女にはどれだけ考えても…あの答えしかなかったと思います」
まりかは瀬山の目を見ながら続ける。
「真剣な答えでした。真剣な…挑戦でした。結果は失敗でしたが、この経験から学んだことを一生忘れません」
閻魔は何も言わない。ただ感情のない目で彼女を見つめている。その時、向島が突然口を開いた。
「先生方、本当に申し訳ありませんでした」
そう深々と頭を下げる。問題児の意外な行動に注意が集まる。
「僕は勉学よりも自分の興味を優先して音楽ばかりやっていました。でもそれは…医学生として間違った姿でした。僕には大学の在り方を批判する資格はありません」
アウトローの独白。彼はそんな不真面目な自分ではなく、真剣に医学に向き合った結果失敗した学生が処分を受けるのはおかしいと発言した。
「君たちがこんな発表をしているのは彼女を救うためですか?」
さらに問う瀬山。それには同村が迎え撃つ。
「僕たち医学生全員のためです。挑戦する気持ちを失くさないために」
まりかも言う。
「先生、私は医師になりたい…今回のことで前より強くそう思いました。そしてそのためにこれからも真剣に挑戦をしていく覚悟です。それさえお伝えできたら、どんな処分でもお受け致します」
学生部長はそっと瞳を閉じた…そして何かを考えているようだ。周囲の教授たちもお互いに目で伺いを立てている。
議論は出尽くしたようだ。さて、彼らの叫びは届くのか?
*
「最後に、ひとついいかな?」
やがて瀬山が瞳を開いて言う。
「確かに君たちの発表は素晴らしかったです。教授たちの質問にも全て堂々と答えていたし、医学部や医学生を批判しても医学そのものには純粋な敬意を感じました。正直なところ、これだけの情熱を学生が持っているとは思いませんでした。非常に有意義な質疑応答でしたよ」
閻魔はそっと微笑んだ。
「医学生は挑戦と失敗をするべきだという提案も斬新でした。その通りだと頷かされる点も多くありましたよ」
そこで少し厳しい顔になって彼は続ける。
「ですがね、医療の世界はそんなに甘いものではありません。きっとこの発表も君たちの挑戦だったのでしょうが…所詮は仲間意識に支えられた綺麗事のように感じます。これで本当に医学生が変わると思いますか?」
六人は固まる。閻魔も黙ったまま見つめる。そして喜多村はもうどうしていいかわからず青い顔をしていた。
同級生たちが息を呑む中、やがて同村が一歩前に出た。
「先生…これを見てください」
白衣の胸からネームプレートを外しそれを掲げる。
「僕たちのネームプレートには、まだ何の肩書きも書かれていません。そこは空欄になっています。まさに医学生は医者ではない、でも部外者でもないという中途半端な存在です」
何人かの学生、そして何人かの教授が自分のプレートを見た。
「でもこの真っ白な空欄が…僕たちの存在価値なんです。今は中途半端だからこそ、僕たちには挑戦する義務がある。だから必ず…変わってみせます!」
半分以上虚勢だったかもしれない。それでも同村はそう言い切った。
…パンパンパンパン!
教室にひとつの拍手が響いた。その主は…守田だ。彼は教授陣の後ろから大きく手を叩いている。無表情ながらも必死でそうするクラス委員の姿に周囲も驚いている。
…パンパンパン!
また別方向から拍手が飛ぶ。見ると山田がはにかんで手を叩いていた。教授たちもそれを振り返る。
するとどうだろう、あちこちから拍手の音が上がり始めるではないか。三玉教授も笑いながらそれに参加したことで教授陣にもその波紋は広がっていく。
いつの間にか…学生の全員が手を叩いていた。ある者は魅せられたように、ある者は頷き合いながら、ある者は笑顔を浮かべながら…そう、満場一致である。着火成功!
瀬山はそんな光景にしばし目をやる。
どうですか、瀬山教授?どうですか!
やがて学生部長は席を立ち、正面に歩み出た。そして拍手がおさまっていく中、同村からマイクを借りる。
「驚きました…みなさん」
机の学生たちも、壇上の六人もその言葉に集中する。そして閻魔はついに言った。
「この勝負…君たちの勝ちです。秋月先生の処分は見直しましょう」
美唄が「やったあ!」と叫んだ。再び巻き起こる大きな拍手の中、同村も「ありがとうございます!」と頭を下げる。井沢と長もガッツポーズ!いつしかパソコン前に戻っていた向島も、そっと満足そうにそれを閉じる。
呆然としているまりかに、瀬山はマイクを放して言った。
「秋月先生、今回の経験を考察しレポートにして提出してください。最終的にはその内容を見て判断します」
「ありがとうございます」
涙ぐんで礼を言う彼女に、瀬山は続ける。
「いえ、その方が留年させるよりも学べる物が多いと判断しただけです。ポリクリにも来週から復帰してください」
何度も「はい」と頭を下げる彼女を美唄が抱きしめる。
なりやまぬ拍手の中、ようやくお呼びのかかった喜多村が前に出て発表会を締めくくる。その後学生も教授たちもどこか満足そうに部屋を出ていった。
こうしてわずか三十分足らずの戦争は終結を迎えた。戦利品はたったひとつの留年の撤回、ただそれだけ。あまりにも小さく、あまりにもしょうもないことかもしれない。だが挑戦することを禁じられた医学部という国で、彼らの起こした戦いの意味はけして小さくない。そう、これは決戦でも聖戦でもないただの挑戦。だからこそ価値があるのだ。
この時医学生の心に宿った未完成な火種がいつか激しく燃え上がり、医療の未来を照らす炎の一端になることを信じようではないか。
5
週明け、さっそくのレポート提出により秋月まりかの留年は正式に撤回された。彼女はもちろんだがそれ以上に喜んだのは14班の仲間たち、そしてまりかの後輩・アカシアである。彼女が人を助けることの難しさを学んだように、彼もまた助けてもらうことの難しさを学んだ。そう、医者も患者も共に成長していくことが治療の深まりであり、互いを支え合うことの意味なのだ。アーチェリーの天才は自らの障害について改めて考え、現在また新しい未来へと的を絞っているらしい。
そんなこんなで晴れて全員集合した14班だが、喜んでばかりはいられない。あと二週間、ポリクリの日々は残っているのだ。彼らはこの一年で得た知識を総動員するように、そして一緒にいられる終わりの幸福を噛みしめるように、最後の実習を過ごした。
*
そして2月最終週の金曜日、14班はついに最後の科の実習を終えた。昨年4月から連れ立った長い旅もこれで完結、その夜彼らは久しぶりにキーヤンカレーに集った。
「じゃあ、いただきまーす!」
すっかり慣れ親しんだ味、それでもやっぱりおいしいカレーを頬張りながらみんなでこの一年を振り返っていく。導き手はもちろん美唄。彼女のポケットにはラブちゃんも顔を覗かせている。
色々あった一年。楽しかったことも悲しかったことも、うまくいったこともいかなかったことも、なんとかなったこともどうしようもなかったことも…全ては学んだことであった。医学生として、あるいは一人の人間として、彼らそれぞれの心は一年前とはまるで違う様相を呈している。そしてそれはこれから先もまだまだ変わりゆけるということだ。世間知らずの私大医学生だって、そう捨てたもんじゃないね!
「でも、発表会の作戦は本当にうまくいってよかったなあ」
やがて想い出巡りは先日の戦いにまで辿り付く。そう言った長に同村が「そうですね」と返す。まりかも「本当にみんな…ありがとう」と改めて礼を言った。
「何言ってんの秋月さん。あれは俺たちのための戦いでもあったんだから気にしないで」
と、笑顔の井沢。続いてスプーン片手に美唄が言う。
「でも本番はドキドキだったね。同村くんなんかすっごく手が震えてたから大丈夫かなとか思っちゃった」
「気が付いてたんだね、遠藤さん」
と、最後の最後でようやく活躍した主人公が照れる。彼は医学部に対して抱いていた気持ちを言葉にして伝えられるよう、そして教授陣の質問にちゃんと切り返せるように、演劇部顔負けの練習をして本番に臨んだのだ。これまでの無口を取り戻すかのようなまさに一世一代の舞台であった。彼にとってはもう一生分くらい話したのかもしれない…今後の反動が心配です。
「それにしても発表の最後、みんなが賛同してくれてよかったよな」
長が笑う。そう、同村の作戦の要は同級生たちを巻き込めるかにかかっていた。どんな論理も六人だけで叫んでは説得力がない。それを教授陣に響かせるには、医学生が一丸となるしかなかったのだ。
「信じてみて…よかったです、医学生の良心を」
これが同村の賭けだった。自分のレポートを読み返した時、やはり医学に携わる者には良心がある…そうでなくてはいけないと強く感じた。東南事件で医学生に絶望していた彼だったが、もう一度だけその良心を信じてみたくなったのだ。
「悩んでるのは…おかしいと思ってるのはきっと自分だけじゃない。誰かがそれを訴えればきっとみんな共感してくれると思ったんです」
そう言うと満足そうに笑う同村。井沢も頷いて言う。
「みんな…いい奴らだよな。俺もなんか安心したよ。まあできれば向島さんの人生も発表してほしかったけどね」
「僕はパソコン操作があったからね。なかなか難しかったんだよ、特に最後の拍手のタイミングとか」
と、ミュージシャン。そう、実は拍手の一部は彼が流した効果音だったのだ。美唄が言う。
「すっごくリアルでしたよ、MJさん!」
ボリュームや角度を計算して教室のあちこちにいくつもスピーカーを設置しておいたから…と音楽部先輩は得意げに笑う。
「でも、効果音を使ったのは最初のだんだん拍手が増えていくところだけで、満場一致になってからはもう消してたよ。これも同村くんの読み通り」
みんな心では正しいと思ってもなかなかそれを言えないだろう、でも拍手が増えていけばきっとやってくれると同村は予想した。みんなと同じなら安心する、という医学生の習性を逆に利用したのだ。それが功を奏して無事彼が擦ったマッチの火は全員に燃え広がった。「それに…」と向島は続ける。
「守田くんの拍手には感謝だよね。クラス委員が先陣を切ってくれたからみんなが続いたんだ。さすがに最初から効果音の拍手じゃバレちゃうから」
「意外にいい奴だな、これなら将来お役人になっても安心だ」
井沢がそう言ってスプーンを口に運ぶ。すると美唄がクスクスと笑った。「どうしたの、美唄ちゃん?」とまりかが尋ねる。
「なーんでもないよ、みんないい人ってこと!」
実はここにもちょっとした秘密がある。まあ知っているのは彼女だけなのだが。
ポリクリ発表会当日の朝、図書室の守田を訪ねた美唄はこんな会話をしていた。撮影した写真を確認している時、彼女はそこに盗難事件の犯人が写っていることに気付いたのだ。まりかのノートをコピーしてその仕分け作業を同村・長とやったあの時、彼女は何枚も写真を撮っていた。その一枚の片隅に写っていたのは…まりかのノートが入った紙袋を持って学生ロビーを出て行く守田の姿だった。写真を見せてそのことを伝えると、彼は突然涙を浮かべ、床に崩れ落ちるように謝罪した。
「守田くん、そんなことしないで顔を上げてよ」
彼は訴えた。どんなに頑張っても四年間成績でまりかに勝てなかった、だからどんな勉強をしているのかつい彼女のノートを盗み見たくなったと。ちょっと見せてと頼むことはプライドが許さなかった。そして実際見てみると…その内容に改めて敗北を感じ、悔しさと情けなさでノートを返すことができなかったと。
「ごめん、本当にごめん」
しゃくり上げる優等生に、美唄は優しく言った。
「私は別にこのことを誰かに言おうとか問題にしようとか思ってないの。守田くんがいつもみんなのために学校と色々交渉してくれてるのも知ってるしね」
ここにもまた他人にはわからないストレスに苦しむ医学生がいたようだ。彼女は彼を立ち上がらせる。
「今まりかちゃんが大変なことになってるのは守田くんも知ってるよね。私たち、何とかしたいって思ってるの。だからもしまりかちゃんにごめんねって思うんだったら…協力してほしいな」
美唄はそれだけ言うと、微笑んでその場を去った。脅迫…いや、それは守田にとって救済だったに違いない。彼はあの時、心から六人に拍手を贈ったのだから。クラス委員に芽生えたちょっとした出来心…その良心と美唄ちゃんに免じてこれも不問と致しましょう。
*
やがて食後のコーヒーが運ばれてくる。その香りの中、しばし六人は無言でカップを口に運んだ。大森カレーでお腹はいっぱい、そしてそれ以上に想い出と感情で胸がいっぱいだ。忙しかったけど充実した日々、そしてもう二度とこのメンバーで過ごすことのない時間。懐かしさと淋しさ、そして何よりの愛しさが込み上げてくる。
「みなさん、一週間後には進級試験があります」
まりかがそっと口を開く。班長からの最後の連絡、と彼女は試験の時間割や流れを丁寧に説明した。「了解です!」とみんな微笑む。
「無事進級したら、実習で使ったネームプレートも学務課に返さなくちゃいけません」
こうやってひとつずつ終わっていくポリクリの日々。続いて長が言う。
「ええと、副班長からは特に連絡ありませんが…みんな試験頑張ろう」
これにもみんな「了解です」と返した。卒業試験対策医院である向島と国家試験対策医院の井沢、この二人の仕事は六年生になってからだ。14班が解散しても試験情報はちゃんとみんなに回すと彼らは約束した。
「MJさん大丈夫ですか?卒業試験サボらないでくださいよ」
美唄がからかいその場に笑いが起こる。「まだそれを言うか!」と返す音楽部先輩。井沢も「お願いしますぜ」と敬愛を込めて言った。続いて同村が話す。
「5年進級試験対策医院からですが…試験の日程はさっき秋月さんが言った通りです。試験試料はもうみんなに配ってあるけど、何か新しい情報がきたらすぐメールで回すから」
「いやいや、同村はもうしっかり役目を果たしたよ」
井沢がそう言って肩を組む。確かに、教授陣とやり合って一人の留年を覆すなんて…これ以上の進級対策はない。同村も少し調子に乗って「仕事をしただけさ」と返した。「なにカッコつけてんの」と美唄に小突かれまた笑いが起こる。
「痛いな遠藤さん、冗談だって」
「同村くん、試験頑張ってよ?これで同村くんが留年したらわけわかんないよ」
美唄のとびっきりの笑顔がそこにある。やがて全員のコーヒーがなくなった頃、まりかが言った。
「ではみなさん、これで14班のポリクリは終わり…」
「あ、ちょっと待ってまりかちゃん!」
思い出したように美唄が言う。
「ごめんね、忘れるところだった。卒業アルバム医院からです。試験の結果発表の日に実はもうひとつイベントがあります」
それが14班としての本当に最後の最後の活動。彼女の説明を聞き、みんな了解を示す。
「じゃあそれに参加するためにも試験頑張らないとな」
と、長。井沢も「そうっすね」と意気込む。同村も「楽しみだなあ」と笑った。頼むからちゃんと進級してよ、主人公!
「じゃあせっかくだから、その日も学生ロビー集合にしようか。白衣着て、時刻は…」
まりかも嬉しそうに段取りする。そして向島はまた虚空を見つめていた。
「じゃあ全員で試験を突破して、必ずみんなで集まろうね!エイエイオー!」
閉店時刻の近い店内に美唄の明るい声が響く。みんながシーッと指を立てる…こんなことももうすぐおしまいだね。
それではひとまずお疲れ様でした、14班諸君!あの日の勇気を忘れずに、ぜひともみんなで6年生になってくだされ!
3月、エピローグにて完結!