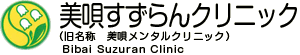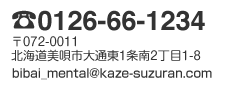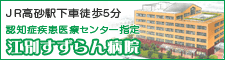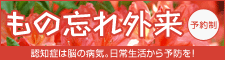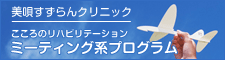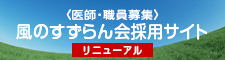- ホーム(法人トップ) >
- 美唄すずらんクリニック >
- コラム >
- コラム2025年4月「医療で患者は患者になる」
コラム
コラム2025年4月「医療で患者は患者になる」
心の病気でも体の病気でも具合を悪化させる原因は色々あるが、その一つに病院がある。いやいや、病院は病気を治療して具合を良くする所だと思われるかもしれない。もちろんそれはそうなのだが、病院にかかるという行為によって、あるいは医師や看護師のそばにいるという状況によって、患者の具合、とりわけ自覚症状というものは悪化してしまうことがあるのだ。
何も難しい話ではない。例えば道端で転んだ人。周りに誰もいなければさっさと立ち上がってまた歩き出す。痛みを訴えても聞いてくれる人がいないからだ。しかし周りに誰か、特に自分に対して優しくしてくれる人がいると、なかなか起き上がれなかったり、しばらく痛みを感じてそれを訴えたりしてしまう。
これは痛み以外の症状でもそうで、苦しいとかつらいとか、一人暮らしの部屋で訴える人はあまりいない。そばに優しい誰かがいてくれるとつい訴えたくなり、訴えているうちにどんどん具合が悪くなってしまうのだ。
外来の待合室で待っている時もそう、病棟のベッドの上にいる時もそう、人間はつい無意識も含めて「患者」という役割を演じてしまう。できることまでできなくなって、つい「助けて看護師さん」と甘えてしまう。これは『退行』と呼ばれる現象で、ケアにおいてどの程度患者の退行を許容するかというのは大切なポイントである。
もちろん苦痛を訴えるのがいけないことというわけではない。訴えて受けとめてもらえることで楽になるし、心配してもらえることで治療を頑張る勇気が持てる。人は支えてくれる誰かの存在によって、弱くもなってしまうが、強くもなれるのである。
ただ支援者としては、自分たちの存在が患者を患者にしてしまうことがあることを忘れてはならない。本来は自分で何とかなっていた人に、診断をつけ、不要の治療や支援を施し、何にもできない人にしてしまう。特に心の医療はそのリスクが高いことを肝に銘じておきたい。
(文:福場将太)