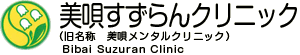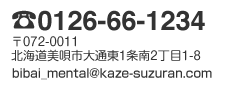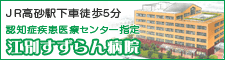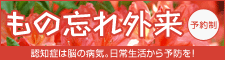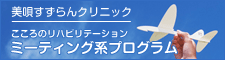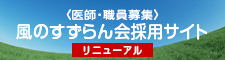- ホーム(法人トップ) >
- 美唄すずらんクリニック >
- コラム >
- コラム2025年9月「当然の権利」
コラム
コラム2025年9月「当然の権利」
就労において、障害のある者でもそこで働けるように、本人と職場が相談しながら環境やルールを調整することを『合理的配慮』と呼ぶ。もちろん就労に限らず教育においても、障害のある学生がそこで学べるように、本人と学校が相談しながら環境やルールを調整することもまた『合理的配慮』である。
昨年の4月から民間の会社や学校でも、この『合理的配慮』を行なうことが法律上の義務となった。よって病気や障害のある者が職場や学校に対して合理的配慮の相談を求めるのは当然の権利である。だがここで難しいのは「やってもらって当然」というふうになり過ぎると、相手にそれをよく思わない感情が生まれてしまうということだ。
日本には謙虚や忍耐を美徳とする文化がある。時代劇でも顔で笑って心で泣いている姿が名場面だったり、現代劇でも本当は大変なのに平気なふりをして頑張る人物が魅力的に描かれたり、どうも苦労を語ったり、助けを求めたりできる土壌がこの国には乏しいらしい。僕だってそうだ。視覚障害の当事者として多くの助けを借りながら仕事や生活をしているが、助けはなるべく借りないようにと意地を張ってしまったり、助けてもらえなかったことに不平を叫んでいる人を見ると嫌な気持ちになったりする。
当然の権利でも、助けを求めることに心苦しさを感じたり、助けてもらって当然のような態度をされると苦々しい気持ちになったり。手を借りるのも手を差し伸べるのも不器用な国民性。もちろんそこには日本人が長年大切にしてきた心情もあってこその不器用さなのだと思う。
それでも時代は変わっていく。『合理的配慮』の義務化はみんなでこのことを考えるよいきっかけだ。『配慮』という翻訳が当てられているために誤解も多いが、本来は『調整』と訳す方が正確。この制度はそもそも「やってもらう」とか「やってあげる」というニュアンスのものではなく、本人と相手で行なう共同作業の調整なのだ。
だから、やってもらうのが当然の権利なわけでも、やってあげるのが強制の義務なわけでもない。病気や障害のために職場でうまくいかずに困っている時、ちゃんと本人と職場で相談しましょう、しないのはダメですよという話。そこに礼節があるのは当たり前。
謙虚さも大切だけど卑屈にならず、柔軟さも大切だけどグダグダにならず、厳しさも大切だけど頑なにならず、そんな難しい力加減をみんなで勉強していこう。
(文:福場将太)