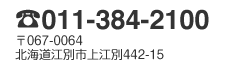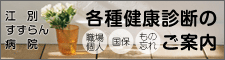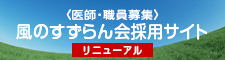- ホーム(法人トップ) >
- 江別すずらん病院 >
- コラム >
- コラム2014年04月『★連載小説★Medical Wars 第1話』
コラム
コラム2014年04月『★連載小説★Medical Wars 第1話』
Medical Wars (福場将太・著)
*この小説はフィクションです。
■第1話「天使のラッパ」 (産婦人科)
1
4月第1週の月曜日、教育棟1階ロッカールーム。白いワイシャツに青いネクタイ、シワのない白衣には輝くネームプレート、そこにある名前は…同村重一。最後にもう一度鏡でチェック、そして教科書とノートを抱え、ポリクリ生・同村くんの完成だ。
「よし、いざ行きますか」
また誰にでもなく彼は言う。時刻は午前8時ジャスト、待ち合わせまではまだ15分もあるが…まあ初日ですもの、このくらいの余裕は必要だ。
同村はさっそうと学生ロビーに踏み出す。そこにはすでに長とまりかがソファで待っていた。周囲には同じく白衣姿の同級生がたむろしている。長がまず彼に気付いた。
「お、同村くんおはよう!」
「おはようございます」
同村も同じソファに腰かける。そこでまりかも「おはよう」と小さく微笑んだ。
「おはよう。いよいよポリクリだね、秋月さん」
「そうね。初日だから…ドキドキしちゃう」
実は意外にこんな可愛い発言もする彼女である。その横で「いや〜俺は絶対先生に年齢を突っ込まれるよ」と長も笑う。
「産婦人科って、どんな感じなんですかね」
と、同村。別にこの言葉は長だけに言ったわけではないのだが、やはり長もその場にいることを意識して彼は敬語を選択した。本来同級生だからタメ口でもいいのだが、さすがに10歳も上となると抵抗があるのも無理はない。
「柔道部の先輩に聞いたんだけど、出産を見学してレポートを提出するらしいよ」
「そうなんですか。それにしても長さん柔道部なんですね」
「そうだよ、いい歳して頑張ってますぜ。…同村くん、部活は?」
「文芸部です。正確には同好会ですけど」
そこでまりかも「へえ、そうなんだ」と少し興味を見せる。
「文芸部…そう言えば聞いたことあるかも」
「いやいや、弱小クラブだよ。この学年にも部員は俺だけ」
好きなことを話している時の同村は少し多弁になる。まりかは質問を続けた。
「じゃあ小説とか書いてるの?」
「あ、うん…一応」
「すごいじゃん、今度読ませてよ」
「長さんまでそんな…本当にたいしたものではないんで」
とか言いながらも、口元が綻んでいる。
「でも今年はたくさんレポートとか書くだろうからいいんじゃん?活かせるよ、文章力」
「そうですかね…」
長におだてられ、同村は満更でもない様子だ。その時…。
「オッハヨー!」
学生ロビーに響く大きな声、そしてそこには…もう言うまでもなく笑顔100パーセントの美唄。また一部の同級生女子からは少し冷たい視線も注がれるが…まあご愛嬌ご愛嬌。
「おはよう美唄ちゃん。今日も元気だね」
と、長。
「おはよう、遠藤さん」
「おはよう」
同村とまりかも続く。班員に迎えられながら美唄もソファに座った。
「長さん白衣似合いますね〜!すごい貫禄、もう本物のお医者さんみたい」
「歳のせいだって。美唄ちゃんも女医って感じ」
「そうですか?ヤッター!」
そんな感じでまた2人が場を明るくしてくれている間に、井沢も登場した。爽やかに白衣を着こなし、髪型も清潔に短くなっている。まさにポリクリモード。彼もまた挨拶を交わしながらソファに腰掛ける。
さて今のところ順調に集まっている14班だが…。
*
やっぱりと言うかまたかと言うか、現れないのはあの男。時刻は8時20分を回っている。
「そろそろ行かないと、間に合わねーよ」
と、井沢。かなり腹立たしげだ。
「さっきから何回も電話してるんだけど、繋がらなくて…」
と、携帯電話を耳に当てて美唄が言う。長もいささかあきれた感じで「初日から遅刻はまずいよな」と漏らす。
「しょうがない、行きましょう」
と、班長・まりかが腕時計を見ながら歩き出した。みんなもそれに従う。
「遠藤さん、院内では携帯電話は切っておいてね」
「了解!あ、呼び方は美唄でいいよ、まりかちゃん」
そんな会話をしながら5人は教育棟を出、敷地内にそびえる巨大な建物に向かう。そう、すずらん医科大学病院に。
「産婦人科の医局に8時半だろ、間に合うかな」
と、井沢が焦った様子で言う。それにまりかが答えた。
「大丈夫。産婦人科の医局は3階、階段で行っても5分もかからないわ。さっき場所を確認しておいたから」
「さっすが班長!素晴しい」
と、長が感心する。その横で同村はまた無口。
やがて5人は病院の正面玄関に入る。そこにいる警備員たちはさり気なくネームプレートをチェックしているようだ。美唄だけが警備員たちに「おはようございます」と挨拶する。
いよいよ病院に入った5人、そこはすでにたくさんの人間で溢れていた。足早に行き交う病院スタッフ、受付をする外来患者とその家族たち…それらをうまくすり抜けながら5人は班長先導のもと仲へと進んでいく。込み合うエレベーターホールを避け奥の階段に辿りつくと、足音を響かせながらそれを上る。もし彼らの動きを上から見たら、きっと1列で移動するロールプレイングゲームのキャラのようだろう。
「それにしても、向島さんって…すごい人だよね」
同村は振り返りながら後ろの美唄に言った。彼女は少し顔を曇らせ「う〜ん。悪い人じゃないんだけど…」と答える。
同村は別に向島に怒りは感じていなかった。多少あきれてはいたが、『すごい人』という感想は批判的なものではなくむしろその逆だった。
とかく医学部という所では何よりも『足並みを揃える』ことが要求される…それをこれまでの4年間で同村は思い知ってしまった。もちろんこの社会において『足並みを揃える』は大切なことだ。だからここはそれを学ぶための環境だと言われればそれまで。しかし何も学生の時からここまで個性を抑え付ける必要はないんじゃないか?…同村はずっとそう感じていた。
彼が入学した時、まず驚いたことは同級生たちがみな同じ色に見えたことだ。当然といえば当然なのだが医学生は将来医者になろうとしている。医学部というものは実質的には医者の養成学校と言っていい。他の学部のように「これでプロになるわけじゃないけど興味があったから医学を学びに来ました」なんて学生はまずいない。同級生はみんな医者の卵、いくら容姿や年齢が違っていても同村の目にはどこか同じ色に映ったのだ。しかもここは私立、国立とは学費が0ひとつ違う。代々医者をやっている家系の2世や3世もゴロゴロいる。家庭環境や経済状況を比べても確かに振れ幅は小さいかもしれない。
そしてその同類項の医学生たちからさらに個性を奪っていくのが『留年の恐怖』だというのが同村の考察。ここにいる医学生たちは極端に留年を恐れている…まるでそれが人生の終わりであるかのように。だからみんなと同じ資料で勉強し、同じようなレポートを書き、先生たちに目をつけられないようにする…それが留年しない秘訣だからだ。大多数と同じ知識で同じ点数を取れば、例えそれが低いものでも自分だけ落とされることはない。学校側から提示される課題が時に理不尽や矛盾を含んでいたとしても、それを逆らうことなく受け入れる。もちろん学生なのだから勉強はしなくてはいけない。しかし、ここまでみんなと同じようにすることはないんじゃないか?自分の興味や判断で学んではいけないのか?これでは毎年受験戦争をやっているようなものだ。
同村はそんなことを考え過ぎてしまう。みんなと同じ当たり障りないレポートを書くことに、彼は今まで何度も抵抗を感じてきた。しかし、それに逆らって留年する度胸も彼にはなかった。彼が山田と気が合ったのも、山田もこのジレンマを理解できる男だったからだ。山田も私立医学部という環境が個性をどんどん奪っていることに気付いていた。ただし彼と同村の大きな違いは、『割り切ることができる』という点だった。同村のように悶々と悩むより割り切って前に進んだ方が自分のためだというのが山田の性格。同村は幾度となく山田に叱咤され、割り切りの悪い彼にはそれが有難かった。
まあそんな同村だから、今回の進級試験にギリギリ合格した時も、嬉しい反面どこかがっかりもした。結局自分はまた流れに乗っている…。もちろんそんなことを言っては留年した同級生たちに申し訳ないのだが…。自分は器が小さい、彼はそう感じている。偉そうな理想ばかりを語り結局現実に屈している、と。だから、説明会もポリクリ初日さえも現れない向島がどこか魅力的に感じてしまうのだろう。大多数から外れることをいとわない人間…まだ直接話したこともない先輩に彼は密かな期待を感じていた。
おっと、同村の胸の内はこの辺にして話を戻そう。14版の5人は3階に到着し、産婦人科医局のドアの前に立った。
「では、行くね」
そう言うとまりかはドアをノックする。
「失礼します、ポリクリの学生です。よろしくお願いします」
まりかはドアをそっと開けた。 同村も唇を噛み締める。さてさて同村くん、頑張ってくれたまえ。君が矛盾や反感を感じている医学部の中枢をぜひその瞳で見極めてくれ!
*
間もなく医局では朝のミーティングが始まった。14班の5人は居心地悪く部屋の隅の方でそれを見学する。初めて間近に見る大学病院医局の朝の光景…。夜勤スタッフからの申し送り、本日の予定、業務連絡などが専門用語満載で飛び交う。何が何やらよくわからないままにミーティングは解散となり、ようやく5人の前に1人の医師が近づいてきた。体格のいい、40歳前後の男性医師…その涼しげな表情には自信と余裕だけでなく厳しさも感じられる。学生時代は体育会系だったのかもしれない。
「こんにちは、ポリクリさん。学生指導の鮫島です、よろしく」
5人は合わせて頭を下げる。
「君たち今日が初日なんだよね。まあそんなに緊張しないで。産婦人科のポリクリは、そんなに忙しくないから。まずは病院の雰囲気に慣れてください」
鮫島は優しく微笑んで話す。
「まず今週は産科を見てもらいます。君たち1人ずつオーベンについて、それぞれ指示を受けてください。あ、オーベンってのは指導医のことね」
5人はそこでまた「はい」と合わせて返事した。
「ええと、班長さんは…」
「私です」
まりかが緊張した面持ちで一歩前に出る。
「はい、秋月さんね。じゃこれ」
鮫島がまりかにプリントを渡す。
「そこに誰がどのオーベンにつくか書いてあるから。各オーベンについて、今週のどこかで1回は分娩を見学してくださいね。それをレポートにして提出、レポートのチェックもオーベンにしてもらってね。じゃ!」
早口にそう言うと、鮫島は足早に医局を出て行った。おそらくすぐに仕事が詰まっているのだろう。大学病院は診療・研究・教育が3本柱だ。そこで働く医師たちは日々の診療に追われながら研究も行ない、同時に学生指導までしなくてはならない…多忙を極めている。学生への対応が不親切になってしまうこともあるが、優先順位を考えればそれも仕方ない話。
そんなわけで鮫島は質問時間も与えず去ってしまった。医局に取り残される14班…。あまりの展開に5人はしばし呆然となる。向島がいないことさえ何も突っ込まれなかったわけだし…。
「まずプリント見よ。ど、どんな感じ?まりかちゃん」
美唄が口を開いた。まりかが答える。
「とにかくこのプリントに従って、それぞれのオーベンの所に行くしかないみたいね」
全員の視線が彼女の持つプリントに集まった。
「そうだな。ええと、俺のオーベンは…」
同村もゆっくりとプリントを覗き込んだ。
…前途多難だが、ファイトです。
*
午前9時…診療開始時刻となり、医局にはほとんど医師も看護師もいなくなった。同村以外の4人は全員それぞれのオーベンを捕まえて一緒に出て行ったが、彼だけはまだ自分の指導医を見つけられずにいた。
…さっそく出遅れているね〜同村くん。それではまあ、君を追ってみることにしますか。プリントに書かれていた彼のオーベンの名は『志田由香子』、女医だ。同村は考える…今ここに女性スタッフはいない。つまり、ここに志田医師はいない。よって、探しに行かなくてはならない。でも…一体どこに?この29階建ての巨大な病院のどこにいるというんだ?
もしかしたら迎えに来てくれるかもと同村はしばらくその場に立ち尽くしてみたが、9時15分を過ぎるとさすがに焦ってきた。どうやら志田医師が現れる様子はない。
「困ったな。こりゃ…」
おいおい、独り言を言ってる場合じゃないぞ。
「ポリクリさん?」
その時後ろから声をかけられた。
*
現れてくれた医局秘書さんのおかげでようやく志田医師の所在を突き止め、同村は2階・産科外来へと向かった。こりゃまるで本当にロールプレイングゲームだ。受付の事務員に尋ねたところ、すでに志田医師は患者さんを診ているとのことで、中に入るのは診察の合間にしてくれとのことだった。というわけで、同村はまたそこで立ち尽くすこととなった。
*
ようやく入れてもらえた診察室。志田医師は鋭い切れ長の瞳をした30台半ばの女医だった。大きなマスクをしているため余計に2つの瞳が印象に残る。
「同村くんね、…了解。外来中だから相手できないけど、まあそこに立って見学してて」
志田は早口でそう言うと、すぐに机に向き直り同村に背を向けた。先ほどの鮫島といい、大学病院の医師たちはまるで2倍速ビデオのように動いている。
「北澤さん、北澤ひとみさん、どうぞ診察室3番にお入りください」
志田はカルテをめくりながら机上のマイクに呼びかける。間もなく入ってきたのはまだ幼さの残る若い女性だった。
「こんにちは北澤さん。今日はどうされました?」
「先生、今朝転んでちょっとお腹ぶつけちゃって…それで心配になって来たんです」
「そうですか、それはご心配ですね。北澤さんは…妊娠19週…ですね」
志田はカルテを確認しながら話す。その雰囲気はとても暖かく、見学している同村にさえ安心感を与えるものだった。
「では、診てみましょう。どうぞ横になってください」
そう言って志田は診察台を促し患者を横にさせる。その一連の流れは実にスムーズで一切の無駄がない。1日に何人もの患者をさばいていく大学病院においては、手際のよさも重要なスキルなのである。
診察台の横で同村も持っていた教科書をめくった。『妊娠19週』の状態を調べようとしたのだ。しかし…。
突然志田が立ち上がり、同村の教科書を押さえつけた。何?何?どういうこと?
「患者さんの前で教科書は開かないで!」
志田は小声で、しかししっかりとそう言った。志田の瞳はさっきよりさらに鋭くなる。同村の背筋はその眼光に凍りついてしまう。
次の瞬間、志田はまた先ほどの雰囲気に戻り、患者の横に腰掛けた。
「では、診察しますね…リラックスしてください」
同村はただ呆然とそれを見ているしかなかった。
う〜ん、いきなりやっちゃったね同村くん。…ドンマイ!
*
やがて午前の外来が終わる…といってもすでに午後1時半。ここは都会の大学病院、午前だけでも数十人の患者の診察を1人の医師が担当している世界だ。午前の外来が午後に食い込むなんて日常茶飯事。
最後の患者のカルテを看護師に手渡すと、志田はようやく同村に向き直った。初めてマスクを外したその顔は、鋭い瞳に相応しい端正な作りをしている。
「お疲れ様、同村先生」
4時間も放置プレイで立ちっぱなし、ただ本当に透明人間のように見学していただけなので、正直同村は疲れていた。…が、学生がそんなことを言えるはずもない。いくらアウトローに憧れる彼でも、そのくらいの良識は持ち合わせている。それに志田は自分よりはるかに疲れているはずであることもわかっていた。
「いえ、大丈夫です志田先生。それにまだ僕は先生じゃ…」
「院内じゃ患者さんの手前もあって、学生さんも先生って呼ぶのよ」
そう言いながら志田は立ち上がる。
「ええと、じゃあ今から午後3時まで自習!お昼ごはんとか食べててよ。3時になったら12階の産科ナースステーションに来て。勉強してもらう患者さん決めるから。
…以上、かな。ハイ、じゃあ午前は終了!」
早口でそう言うと、志田は忙しそうに診察室を出て行った。かっこいいね!働く女性の姿、できる女医の姿である。それにしても…タフですねえ、お医者さんって。
それに引き換え、…またまたその場に立ち尽くす同村であった。
*
教育棟。同村が自販機でパンとコーヒーを買って学生ロビーに来ると、そこには井沢と長がいた。
「お疲れ、同村!」
白衣を脱いで一休みしていた井沢が軽く手を上げた。長も「お疲れ同村くん、どうだった?」と迎える。その隣に腰を下ろすと、同村は大きく息を吐いた。
「いやぁ、足が棒になりましたよ」
「そっかぁ…」
と、長。そこで井沢が尋ねる。
「何やってたんだ?」
「外来の見学。でも、教科書見るなって怒られちゃったよ」
「俺もエコーの検査室で看護婦に怒られたよ。何か触っちゃいけない機材触ったみたいなんだけど…そんなのいきなりわかんねえって!検査室の場所とかも説明受けてないのに。学務課もそういうことをちゃんと教えとけっての」
不平を吐露する井沢。長も「基本的にうちの学務課は説明不足だよな、肝心な部分が」と頷く。
「ま、今に始まったことじゃないですけどね。井沢は検査見学か。じゃあ長さんは何してたんですか?」
同村がパンをかじりながら尋ねた。
「俺は患者さんにカイザーの手術の説明をする場に立ち会ったんだ。術式とか所要時間とか、あと起こりうる合併症とかさ」
「帝王切開の合併症っていうと、腸閉塞とか肺塞栓とかですよね」
と、井沢。
「そうそう。あと大量出血した場合の輸血の可能性とかね。まあ説明自体はかなり丁寧でわかりやすかったんだけど…。いや、その説明の後でオーベンと話したんだけどさ…」
そこで長は少しトーンを落とす。
「いや、なんか『こういうふうに説明しないと訴えられた時に不利になる』とか『裁判に負けないように。責任とらされないように』とかさ、…そんな話ばっかで、ちょっとがっかりしたよ」
井沢が腕を組んで答えた。
「現実に医療裁判だらけですもんね、今。こっちも自分の身を守らないとやっていけないんですよ。親父もよくそう言ってます。うちも代々産婦人科なんで」
それを聞きながら同村は「世知辛いな…」とコーヒーを流し込んだ。
海外には病院の入り口にまるでティッシュ配りのように弁護士が待機し、患者や家族に裁判を持ちかける国もあるという。「必ず病院からお金を取ってみせますから、訴えませんか」と勧誘するらしい。
そして今、日本でも医療訴訟というものはけして珍しいものではなくなってきている。医師の意識が純粋に患者の病を治すことだけではなく、どうしても自己防衛に働いてしまうのも無理はない。しかし学生はまだその現実をよく知らない。少なからずの憧れや理想を医療に抱いている。だから今まで教科書のどこにも載っていなかった訴訟という話題にいきなり暴露されれば、そりゃテンションが下がるのもこれまた無理はない。
同村の言葉を最後にその場には沈黙が訪れた。どうやら身体的にも精神的にも打ちひしがれた3人のようである。
2
火曜日、朝の学生ロビー。ポリクリ2日目にしてついにあの男が現れた。
「どうも、昨日はすいません。向島です、よろしく」
たいして後ろめたさもないその態度を、いきなり歓迎したのは美唄だけだった。向島は一応白衣姿ではあるが、寝不足そうな顔にボサボサの頭はそのままだ。
「もうMJさん、ちゃんとしてくださいよ!でもこれでついに14班全員集合ですね」
美唄は盛り上がっているようだが、本来は全員集合しているのが当たり前。
「ええと、今日も各自のオーベンについて指示に従ってください。あと、午後4時から12階のカンファレンスルームで鮫島先生のクルズスがありますから、全員集合してください」
今日もまりかは明瞭に説明する。ちなみにクルズスというのは、ポリクリ中に院内で行なわれるミニ講義のようなもの。
「頼みますよMJさん、逃げちゃダメですからね!」
美唄がそう言って向島の背中をポンポン叩く。彼は「わかってるよ」と面倒臭そうに答える。やはり井沢や長からは不信の視線が送られていた。ただ同村だけはようやく出逢えたこのアウトローを、興味深そうに見ている。…人の評価ってのは様々ですな。
*
同日午後8時。クルズスの後、6人はそのまま12階カンファレンスルームに残っていた。鮫島から、今日生みそうな妊婦がいるから残って見学していけと言われたからだ。彼らはこの産科実習の間に一度は出産を見学しなくてはいけないわけだから、早く済むにこしたことはない。しかし、すでにクルズス終了から3時間余り…出産の時がきたら、看護師が呼びに来てくれる手筈なのだが…。実はすでに先ほど1回看護師が呼ぶのを忘れていて、出産は終わってしまった。今はもう1人の妊婦が産気づくのを待っているところだ。
6人は最初は自習などしていたが、さすがに疲れて今なお教科書を読んでいるのはまりかのみ。向島は机に突っ伏して爆睡、残りの4人もぼんやりしている。さすがの美唄も口数が少ない。
「それにしてもさっきの看護婦マジ有り得ねえよ。忘れてたって…こっちは何時間待ってると思ってんだ」
と、井沢が腹立たしげに言った。美唄が「しょうがないよ、看護師さんも忙しいんだろうし…」と返す。その後再び訪れる沈黙。
やがて午後9時半、全員の気力も尽きかけた頃…ついにドアが叩かれた。
「ポリクリさん、急いで!」
井沢を筆頭に全員が部屋を飛び出し分娩室に走る。眠っていた向島もガバッと起き上がり、遅れて後を追った。
井沢が分娩室のドアを開ける直前、中から…。
「オギャーッ」
高らかな産声が上がった。
井沢と長は顔を見合わせる。…まさか、そう、どうやらそのまさかのようだ。
井沢はゆっくりドアを開ける。すると、そこには赤ちゃんを抱いた鮫島が母親にその子を見せている光景…、笑顔でそれを囲むスタッフたち…。
少しの間の後、鮫島がようやく6人に気付いた。
「あ、君たち遅いよ〜。もう今夜は出産はないだろうから、今日はこれでおしまいね。大丈夫、また見学のチャンスはあるから」
早口にそう言うと、鮫島は赤ちゃんをあやしながらまた母親の方を見る。そこには涙を浮かべた至福の母親と、寄り添う夫…。
6人は何も言えずおずおずと廊下に引っ込む。まさにお呼びでない。こんな幸せな光景を見て落ち込む人間なんて、世界中でも彼らくらいだろう。
*
「マジ有り得ねえって!」
教育棟への帰り道、すっかり夜の闇に包まれた駐車場を6人は歩いていた。ずっとブツブツ言ってるのはやはり井沢だ。
「絶対あれはまた忘れてたんだって!そんな、産気づいてすぐ生まれるわけねえし!」
「まあ明らかにそうだね」
と、長も疲れた顔で言う。
「ポリクリへの嫌がらせか?馬鹿にしやがって、看護婦のくせに!出産なんて、俺、親父に頼めばいくらでも見られるのに!」
井沢は相当お冠のようだ。同村はそんな井沢の態度を訝しげに見ていたが…、そういえば美唄の口数が少ないことに気付き後ろを振り返る。美唄は向島の後ろを無言で歩いていた。
「遠藤さん…大丈夫?」
「え、何が?大丈夫よ」
そこでまた美唄はいつもの笑顔100パーセント。そんな彼女の様子に、向島は黙って小さく頷いた。
*
学生ロビー。さすがにこの時刻ともなると他の班の姿はない。
「じゃあみんな、今日はお疲れ様でした」
と、まりか。2日目にしてすっかり班長が板についている。
「明日は教授回診なので、朝9時に12階ナースステーション集合だから…ここに8時45分集合にしましょう」
みんな力なく頷く。本当にお疲れのようですな…1人以外は。
…パシャッ!
フラッシュがたかれた。それは元気娘・美唄のカメラだ。
「…遠藤さん?」
同村も驚いて彼女を見る。
「だって私、アルバム委員だもん!1年間、みんなの写真をバッチリ撮るからね!」
「こんなところも撮るんだ…」
「モチロン!夜の学ロビなんてレアでしょ」
笑顔のカメラマンに長は少し微笑んで言う。
「美唄ちゃんのパワーって、本当にスゴイな。なんかちょっとだけ元気出たよ」
「そうですか?じゃ、せっかくだしみんなでどっか行きます?」
「え、今から?」
と、同村。彼は気付いていないが、美唄へのリアクションという形で口数が増えている。
「そうよ!だってこのまま今日帰っても、みんなバタンキューでしょ?こんな遅くまで残ったことに何か意味を持たせようよ!」
「…って言ってもなあ…飲み会とか?」
そう戸惑う同村。長も「いや、そりゃまずいだろ。明日は教授回診だし、絶対遅刻できないぞ」と難色を示した。美唄が答える。
「そうですよね、じゃあなんかちょっとだけパアーッと遊びませんか?学ロビでだるまさんがころんだ、とか」
…彼女はどこまで本気なのだろう。だがその表情は笑顔100パーセント、完全にスイッチが入ってしまっている。
「私は早く帰りたいけど…」
「まあまあ、まりかちゃん。ちょっとだけ遊ぼうよ」
「じゃあ、近くのビルにあるゲーセン行く?そこ夜10時までだし、どうせあと40分くらいだから」
と、井沢。さすがに色々よくご存じで。それにノリノリな美唄が続く。
「うん!賛成!どう、みんな!」
「ゲーセンか…ま、こんなことでもないと行かないもんな。せっかく14班が全員揃ったわけだし、たまにはアルコールなしで健全にやりますか」
と、長も応じる。さすがは最年長!それにしても夜のゲームセンターははたして健全なのだろうか?
「おし、憂さを晴らすぜ!」
と、井沢もテンションを上げた。同村も「まあ、いいんじゃない」と頷く。向島は特に何も言わず、遠くを見ながら小さく鼻唄を奏でていた。
「じゃ、みんな、すぐ着替えてここに集合ね!」
美唄は嬉しそうにそう言うと、合図のように再びシャッターを切った。
*
最後まで渋っていたまりかを美唄が引っ張って、6人は近くのビルの2階にあるゲームセンター『マイクロワールド』に到着した。時刻は9時半、髪の色を原色に染めた若者たちが様々なゲームに興じており、店内にはその大音量のBGMが飛び交っている。
「うわ〜、すげえ久しぶり」
と、長。井沢も「あと30分しかない、何やります?」と続く。ここで冷静に考えれば、まだそんなに親しくもない6人がいきなりゲームセンターとは…美唄パワーの賜である。
「あ、あれやろう!」
美唄が指差した先は…クレーンゲーム、そう、あのぬいぐるみを取るヤツだ。
「君は…小学生か?」
と、思わず突っ込む同村。
「もう何よ、クレーンゲームは大人もやるのよ。ほらやろう、同村くん!」
彼女に導かれるままに、6人はそのゲーム機の前に集まる。もはや、みんなそのノリに慣れた…というかある種麻痺したのかもしれない。
「見て見て、500円で6回チャレンジできるって!ちょうど6人いるし、いいんじゃない?」
「うわ〜本当に懐かしい。で、どのぬいぐるみを狙うの?」
「お、長さん乗り気っすね!」
井沢も食いついてくる。
「え〜とね、あ、アレとかよくない?」
美唄がゲーム機のガラスに顔を引っ付けて指差す。そこには、赤ちゃんのような天使がラッパを持っているぬいぐるみがあった。大きさ25センチほどの、クレーンゲームとしては少し大きめなものだ。向島も瞳をまん丸に見開いて子供のように覗き込む。
「確かに、産婦人科っぽいね」
「ですよね、MJさん!」
「確かに、あれだけ1つしかないみたい。他のは同じのが何個かずつあるみたいだけど…」
と、同村。
「うんうん!ほら、まりかちゃんも見てよ!どう、あの子」
みんなの後ろで黙っていた班長も、美唄に言われて覗き込む。
「うん…可愛い」
「じゃ、決定ね!」
「それじゃ、俺が500円出すよ」
そう言って財布を出したのは向島。長が「いいんですか、向島さん?」と尋ねる。彼からすれば、向島は年下の先輩になる。
「いいよいいよ、昨日は迷惑かけちゃったしね」
「じゃあ、6回をうまく使って、あのぬいぐるみを穴まで引き寄せましょう」
と、まりか。案外乗り気なのかな?井沢も「了解です、班長!」と意気込む。
「14班、初めての共同作業だな」
と、文芸部・同村も少し洒落たことを言ってみせる。
「じゃ、いくぞー!」
向島が500円玉を投入する。軽快な音楽が流れ始め、操作ボタンが点滅した。
「よし、では僭越ながら失礼します」
まず長がトライする。まるで子供にいいところを見せようとするお父さんのように真剣だ…しかし、クレーンのフックはわずかに獲物をかすめただけ。ぬいぐるみは少し揺れた程度。
「も〜、長さん!」
美唄は嬉しそうだ。続いて同村が珍しくやる気を見せてトライする。
「いけ、同村!」
と、向島もノリノリだ。同村はうまくフックを獲物にフィットさせるが、パワーが足りずぬいぐるみは少し浮き上がった程度。「あ〜!」と美唄が全身で悔しがる。続いてまりかがトライ。
「さっきの感じを見た限りだと、多分こうやれば…」
何やら分析めいたことを言いながら、まりかはフックを獲物の横に落とす。みんなあまりに彼女がヘタクソなのかと思い、一瞬言葉を失うが…。
…コロン。
フックが元の位置に戻る時にぬいぐるみに当たり、一気に転がって大きく穴に近づいた。
「おお、すげえ!さすが特待生!」
「まりかちゃんすご〜い!」
まりかは照れたように笑う。化粧っけのないその顔は子供のようにあどけない。
「よし、次は俺だ」
井沢のトライ。なんでもそつなくこなす彼は、ここでも見事なアシストを見せた。ぬいぐるみは穴まであと5センチくらいまで迫る。
「よし、いけ、遠藤さん!」
続いて美唄のトライ。同村はまた気付いていないが、彼が山田以外の同級生にこんなふうに言葉をかけるのも初めてのことである。
美唄はぬいぐるみをじっと見ながら慎重にレバーを動かした。そしてついにぬいぐるみは穴まで2センチほどの位置に迫る!
最後の挑戦者は…そう、スーパーアウトロー・MJKだ。
「頼みます、向島さん!」
長もガラスにへばりついて応援する。向島は何やら妙なポーズでレバーを握り、ミュージシャンらしい細長い指でそれを繊細に操る。
フックは見事にぬいぐるみに引っかかり…かけたが空振り。
「お願い、MJさん!」
美唄の声。みんな息を呑む。
…ストン。
フックは天使の持っていたラッパに引っかかり、見事にぬいぐるみは穴に落ちた。
「やったー!」
6人が一斉にそう叫んだ。…まあ周囲から見れば、いい歳して何やってんだというダメな大人たちだろうけど。
美唄が嬉しそうにぬいぐるみを取り出し、掲げてみせた。残る5人は拍手を贈る。
「いや〜、うまくいったな」
と、井沢。
「ほんと、出来過ぎなくらい」
同村も珍しく屈託のない笑顔を見せる。
「あ、名札がついてる。…ええと、『ラブちゃん』だって」
美唄が大事そうにぬいぐるみ…失礼、ラブちゃんを抱く。まりかも笑顔でラブちゃんの頭をナデナデした。
「よろしく、ラブちゃん。班長の秋月です」
「よろしく」
「よろしくな」
まりかにならって、他のみんなもおどけて14班の新たなるメンバー(!?)に挨拶する。そして、お互い顔を見合わせて吹き出すのだった。
こんなふうに笑い会えるなんて、先週の説明会の時には想像もつかなかった…だからこそ余計にそうなのかもしれない。幸せで穏やかな空気が、いつしか彼らを包み込んでいた。
*
その後も10時までのわずかな時間、彼らは楽しんみに楽しんだ。長と井沢のレーシングゲーム対決、同村とまりかのクイズ対決、美唄と向島の音楽ゲーム対決…どれも笑いが絶えなかった。そして美唄はそんな14版の仲間たちを、何枚もの写真に収めたのだった。
いきなりこんなに仲良く…そんなことあるわけない、と思う読者もおられるかもしれない。急にそんな心の距離が縮まるはずがない、と。もしあなたがそう思うなら、それは淋しいことですよ。
もちろん14版の6人が心の底から打ち解けたわけではない。知られたくないことや、踏み込んでほしくないことはお互いあるだろう。理解できないことやすれ違いだってこれからいくつもあるだろう。でも、わかり合っていなくても、楽しい空間を作ることはできる。同じ幸せを過ごすことはできるのだ。
誰もみな、自分の人生という道の上を歩いている。どんなに他人と交わっても、結局はまた自分の道に戻らなくてはいけない。だから一緒に笑い合える今という交差点が大切なのだろう。
まあ今回の奇跡の正体は、疲れきっていたからこそのナチュラルハイだったのかもしれないが。いいじゃないですか、幸せの種明かしなんて野暮なまねはやめましょうぜ。
*
やがて閉店時刻となり、一同は解散した。帰り道の地下鉄、同村と美唄は座席に並んで腰掛けて話していた。さすがにこの時刻となれば空席もある。
「いや、遠藤さんってやっぱりすごいね」
「え、何が?」
美唄は相変わらずラブちゃんを胸に抱いている。ラブちゃんは今日の記念に彼女が預かることになったのだ。
「ポリクリの後あのまま帰ってたら、きっと疲れただけの日になってたよ。なんて言うか、大逆転してこんな楽しい日になるなんて…。遠藤さんのおかげだ」
同村はごく自然に話している。昨年までの彼からすればとても信じられない姿だ。いや、むしろこれが本当の彼なのかもしれない。
「うん、なんかあのまま帰っちゃうのはもったいない気がして。そういう時こそチャンスって気がするの…。私、可能性って好きなんだよね」
「…可能性?」
同村はそこで美唄の横顔を見る。
「そう…可能性ってすごい武器だと思うの。もちろん、可能性って絶対うまくいくっていう保証はないし、うまくいかないかもしれないんだけど…。だから、うちの班ってお互い今までほとんど絡んでなかったし、まだ仲良いも悪いもないじゃない?可能性のカタマリだと思うんだよね。だから、これからが楽しみなんだ」
美唄はそこで同村を見て微笑んだ。
確かに、まだ何も出来上がっていない未知数…それが14班の最大の武器なのかもしれない。同村も素直にそう感じた。無個性だらけのこの大學で自分だけが悩んでいるのだとどこかで思い上がっていた彼にとって、美唄の言葉は心に新鮮な感触を与えるものだった。
「そっか、そうだね…」
同村は優しくそう答える。美唄も続けた。
「それに今日ね、出産は見られなかったけどあの産声を聞いた時、なんか今日はいい日になる気がしたの。本当、天使のラッパみたいに心地よかった」
同村もあの産声を思い出す。
「そしたら、このラブちゃんがいたでしょ。ラッパを持った天使…この子のおかげで、一生の思い出ができたし、だから今日は素敵な日」
そこで同村は考える。一生の思い出…というには大袈裟かもしれないが、確かにこのラブちゃんを見ればみんな今夜のことを思い出せる。もちろん産声を聞いた後でこの天使のぬいぐるみを獲ったのは単なる偶然だ。でも、奇跡なんてものがあるのなら、それはきっとこんな小さな偶然から始まるのだろう。
「確かに、ラブちゃんのおかげで俺も今日はみんなと仲良くなれた気がしたしな。…こいつは14班の守り神かも」
そう言って同村はラブちゃんを撫でる。美唄も嬉しそうに微笑む。
「さすが小説家!」
「いや、そんなんじゃ…」
「そうだ同村くん、今度ライブ見に来てよ。新入生の勧誘で音楽部でやるの。MJさんも出るし、よかったらぜひ来て!」
そこで彼女は、今日最後のとびっきりの笑顔を見せた。地下鉄は2人を乗せて静かな闇を走っていく。
…長い一日、お疲れ様でした!
3
翌日の水曜日、彼らは無事出産に立ち会えた。そしてそれぞれのオーベンのもと、週の後半はレポートを作成する日々に追われた。
そして同村は、レポートの最後に『感想』という欄を勝手に作り、この1週間の想いを記入した。もちろんそんなことはオーベンから求められてはいない。しかし彼はそれを記した。今のこの想いを書き残しておくことが、将来必ず役に立つと信じたのだ。それに、これまでずっとためらっていた『自分ならではのレポート』を書いてみたかった。怒られるかもしれない、でももしかしたら…。そう、『可能性』を使ってみたかったのだ。
彼はレポートの最期に心を込めてその一文を書いた。
天使のラッパを聞いた、と。
*
実習最終日となる金曜日、志田は医局の机で同村のレポートを読んでいた。もちろん、その横には判定を待って立ち尽くす同村。この1週間で立ち尽くすのもだいぶ慣れてきたようだ。
読み終わると志田はレポートを机の上に置き、切れ長の鋭い瞳を同村に向けた。同村は背筋を伸ばして構える。
「同村先生…」
「はいっ」
「…おもしろいね、君」
そこで志田は静かに言った。
「天使のラッパ、か。…うん、子供は世界の宝だもんね」
「そ、そう…思います」
同村は上ずった声で答える。
「君も実習中に何度か噂で聞いたと思うけど…正直最近産婦人科医になろうって子が少ないのよ。いつ産気づくかわからないから産婦人科医は旅行にも行けない。人手が足りないから週に何回も当直。おまけに訴訟も多い…本当は出産って母も子も命懸けなのにみんな健康に生まれて当然だと思ってる。もし母子に何かあったら恨まれるのはいつも産婦人科医…」
志田はそこで優しい微笑みを見せた。
「でも君のレポート読んで、産婦人科医になってよかったって思ったわ、久しぶりに。君、文章うまいね」
「そ、そうですか。ありがとうございます」
同村もほっとして微笑む。そこで志田は「ただし!」といつもの厳しい顔になった。
「感想はどんなにドラマチックでもいいから、前半のデータは感情を込めずにもっと事実だけを書きなさい。考察も科学的に行なうこと。君はちょっと感動的にしすぎ!」
「わ、わかりました」
同村は慌てて頭を下げる。
「…よし、じゃあ…合格!同村先生、お疲れ様でした」
志田は最後にまた微笑んだ。
「ありがとうございました!」
同村はもう一度頭を深く下げる。
こうして彼の、そして14班の最初の実習が終わったのだった。
*
その夜、同村は音楽部の勧誘ライブを見に行った。
場所は1・2年生が通う校舎の食堂。3年生以上は病院敷地内の教育棟で授業を受けるのだが、2年生までの基礎授業は病院から少し離れたこの東新宿の校舎で行なわれている。前に触れた、教育棟に3年生以上の教室しかない理由はここにある。
すずらん医科大学がこのように基礎授業の校舎を離れた場所に有するおかげで、学生たちは病院の目を気にせず部活に没頭できる。音楽部も大きな音でバンド演奏を行なえるわけだ。
さてどうですか、同村くん?
彼が音楽部のライブを見るのはもちろん初めて。プロのミュージシャンのコンサートにだって行ったことはない。彼にとってはまさに人生初のライブ体験。
…飾り付けられた仮設ステージの上には、輝く美唄がいた。ライトを浴び、露出の多い服で飛んだり跳ねたりしながら歌う彼女の姿。それは音楽という羽根をまとった悪戯な天使。
…すごい。
客席の隅でそれを見ていた同村は素直にそう思った。白衣の時の美唄とは違う、全くリミッターをかけられていない彼女の魅力が所狭しと暴れまわる。その輝きは客席の新1年生たちの心を確実に掴んでいた。そして、美唄の後ろで踊り狂うようにキーボードを弾く向島。他のバンドメンバーもみんな微笑んでいる。
無個性な奴らだらけだなんて…自分はなんて無知だったんだ。こんなに魅力的な人たちが、ここにいるじゃないか…。
同村はうっすらと涙を浮かべ、そんな想いに浸っていた。そして思った。今日ここに来てよかったと、14班で美唄に出会えてよかったと。彼女の伸びやかなボーカルは、食堂内に…そして彼の心に響き渡っていた。
…さぁ、同村くんの春がやってくるのかな?
やがて曲が終わり、熱い拍手と歓声が贈られる。ステージの上の美唄は、あんなに動いていたのに全く疲れを見せず、大きな声で叫んだ。
「ありがとうみなさん!1年生さん、入学おめでとー!今日は楽しんで行ってね。興味があったらどんどん音楽部にウエルカムで〜す!」
気が付けば同村も手が脹れるほど拍手をしていた。
「ありがとう!じゃあ、次の曲を聴いてくださ〜い。MJさん、よろしく!」
その言葉に合わせて向島が軽快にイントロを奏で始める。その時同村は、そのキーボードの上に置かれているものに気付いた。
「フフフ、ハ、ハ、ハハハ…」
彼は涙を浮かべながら思わず大笑いする。そして、輝くステージの上のそれを改めて見た。
14班の守り神は、このライブをも成功に導いたようである。
5月、外科編に続く!